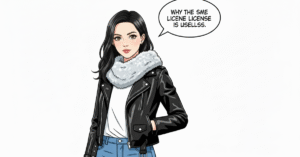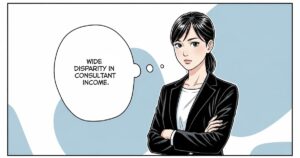中小企業診断士は「やめとけ」|資格取得前に知るべき厳しい現実


あなたは今、「中小企業診断士になれば年収アップ間違いなし!」「独立開業で成功への道が開ける!」こんな甘い言葉に踊らされていませんか?残念ながら、これらは多くの場合、予備校による巧妙なポジショントークに過ぎません。
なぜ「中小企業診断士はやめとけ」と言われるのか
現実を知らない人が多すぎる



昨日は知り合いの診断士と食事に行きましたが、やはり「診断士にかけるコストとリターンはあまり見合ってないですかね」という話になりました。
中小企業診断士という資格について、多くの人が抱いているイメージと現実の間には、深刻なギャップが存在します。このギャップこそが、後に多くの資格取得者を絶望の淵に追いやる原因となっているのです。
予備校のパンフレットや宣伝文句では、「経営コンサルタントとして活躍」「年収1000万円も夢ではない」「企業内でキャリアアップ確実」といった魅力的な言葉が並んでいます。しかし、これらの言葉の裏に隠された真実を、あなたは知っているでしょうか。
実際のところ、中小企業診断士の資格を取得しても、思い描いていたような華々しい成功を手にできる人は、全体のほんの一握りに過ぎません。大部分の資格取得者は、期待していたほどの収入アップも、キャリアアップも実現できずに、資格の維持費だけを支払い続けるという現実に直面しているのです。
予備校が語らない「不都合な真実」
予備校や資格学校は、あなたから受講料を得ることが目的です。そのため、資格取得後の厳しい現実については、意図的に触れようとしません。彼らにとって重要なのは、あなたが資格を取得することではなく、あなたが受講料を支払うことなのです。



考えてみてください。もし予備校が「この資格を取っても9割の人は思うような成果を得られません」と正直に話したら、誰が高額な受講料を支払うでしょうか。だからこそ、彼らは成功例ばかりを前面に押し出し、失敗例や平凡な現実については口をつぐむのです。
この構造的な問題こそが、多くの人が中小企業診断士という資格について誤解を抱く根本的な原因となっています。そして、その誤解が後に大きな後悔と失望を生み出すことになるのです。
中小企業診断士の年収の現実
実際の年収データが示す厳しい真実
中小企業診断士の年収について、あなたはどのような数字を想像しているでしょうか。おそらく、予備校の宣伝文句から、かなり高い数字を期待しているかもしれません。しかし、現実はその期待を大きく裏切るものです。
実際の調査データを見ると、中小企業診断士の年収の中央値は、一般的なサラリーマンとそれほど変わらない水準にあります。確かに、年収1000万円を超える診断士も存在しますが、それは全体のほんの数パーセントに過ぎません。
多くの診断士が直面している現実は、資格を取得する前の年収とほとんど変わらない、あるいは場合によってはそれを下回る収入しか得られないという状況です。特に独立開業した診断士の中には、会社員時代の年収を大幅に下回る収入で苦しんでいる人も少なくありません。
下記記事で、中小企業診断士の年収については詳しく解説しています。


企業内診断士のキャリアアップ幻想
「企業内で中小企業診断士の資格を活かしてキャリアアップ」という謳い文句も、多くの場合は幻想に過ぎません。実際のところ、多くの企業では中小企業診断士の資格は、昇進や昇格の決定要因としてそれほど重視されていないのが現状です。
確かに、一部の企業では資格手当が支給されることもありますが、その金額は月額数千円から数万円程度がほとんどです。年間で考えても、資格取得にかかった費用や時間、そして毎年の維持費を考慮すると、経済的なメリットは非常に限定的と言わざるを得ません。
さらに深刻な問題は、企業内での実務において、中小企業診断士の知識がそれほど直接的に活用される機会が少ないということです。多くの企業では、より専門的で実務的なスキルが重視される傾向があり、中小企業診断士の幅広い知識よりも、特定分野の深い専門知識や実践的なスキルの方が評価される場合が多いのです。



例外的に、多くの信用金庫や一部地銀では、診断士の取得が奨励されてますし、キャリアップとして有用です。ただ、これはあくまで例外で、ほとんどの業界にとっては、大して意味のない資格ということになります。
独立開業の厳しい現実



診断士に限った話ではないのですが、診断士として独立しても廃業や事実上廃業している人も多いです。
コンサルタントとして成功するのは至難の業
中小企業診断士として独立開業を考えている方にとって、最も知っておくべき現実があります。それは、コンサルタントとして安定した収入を得ることが、想像以上に困難だということです。
まず、クライアントを獲得すること自体が大きな壁となります。中小企業の多くは、外部のコンサルタントに高額な報酬を支払う余裕がありません。また、コンサルタントを雇う場合でも、実績のある大手コンサルティング会社や、特定分野での豊富な実務経験を持つ専門家を選ぶ傾向があります。
新米の中小企業診断士が、このような競争の激しい市場で生き残ることは、容易なことではありません。多くの独立診断士が、クライアント獲得に苦労し、思うような収入を得られずに、結局は別の仕事で生計を立てざるを得ない状況に陥っています。



多くの企業にとって「中小企業診断士です!」といったところで、「何の資格ですか、それ?」「何ができるんですか?」状態ですからね。士業なので、無いよりマシな程度の資格というのが現実的なところです。
営業力こそが成功の鍵
独立開業で成功している中小企業診断士に共通している特徴があります。それは、優れた営業力と人脈形成能力を持っているということです。



逆に言えば、どれだけ診断士としての知識が豊富であっても、営業力やマーケティング力がなければ成功することは困難なのです。
この現実は、多くの資格取得者にとって衝撃的なものです。なぜなら、彼らの多くは「資格を取得すれば仕事が舞い込んでくる」と期待していたからです。しかし、実際には資格取得はスタートラインに立ったに過ぎず、そこから先は厳しい営業活動と継続的な努力が必要になるのです。



医者、弁護士、税理士など独占資格であれば、まだ「資格を取得すれば仕事がある」ことが期待できますが、診断士に限っては、それはほぼ無いです。
さらに、営業活動に時間を取られることで、本来の診断士業務に集中できない時間が増えることも問題となります。結果として、専門性を高めることよりも、営業活動に多くの時間を費やさざるを得ない状況に陥る診断士も少なくありません。
資格維持にかかる見えないコスト



特に会社員にとっては、中小企業診断士は資格維持にはとてもコストがかかる資格です。
継続的な金銭負担の重さ
中小企業診断士の資格を維持するためには、継続的な費用負担が必要です。この維持費については、資格取得を検討している段階では軽視されがちですが、実際には長期的に見ると相当な負担となります。
まず、5年ごとの更新に必要な研修費用があります。これは2つあり「実務従事ポイント」と「理論更新研修」の2つに分けられます。「実務従事ポイント」は中小企業のコンサル実施日数が30日分、「理論更新研修」は5年で5回受講する必要があります。さらに、各地の診断士協会に入る場合は、年会費で5万円ほどかかります。



実務従事ポイントは、もし中小企業のコンサル実施日数が30日分に満たなければ、ポイントを購入することになります。ざっくり1ポイントにつき1万円くらいです。
これらの費用は、資格を活用して十分な収入を得ている場合には問題となりませんが、期待していたほどの収入アップが実現できない場合には、大きな負担となります。実際に、資格の維持費用が家計を圧迫しているという診断士も存在するのです。
時間的コストの問題
金銭的な負担だけではありません。資格維持のためには、相当な時間的投資も必要です。継続研修の受講、関連知識のアップデート、業界動向の把握など、診断士として必要な学習は継続的に行わなければなりません。



特に実務従事ポイントを会社員で達成するのは至難なので、その場合は協会からポイントを買うことになります。これもただポイントを買うだけでなく、「実務補習」として、実際の中小企業の診断をしなければなりません。また、これは平日も跨いで行われるので、皆さんの貴重な有給休暇を使うことになります。
この時間的投資が、本業や家庭生活に与える影響は決して小さくありません。特に、資格を取得したものの期待していたほどの成果が得られない場合、この時間投資の価値について疑問を感じる人も多いのです。
さらに問題なのは、この継続的な学習が、実際の業務や収入向上に直結しない場合が多いということです。形式的な研修受講に時間を取られることで、より実践的なスキル向上や営業活動に充てるべき時間が削られてしまうという矛盾も生じています。
市場の飽和状態と競争の激化



市場のパイが減っているのに、診断士の数はどんどん増えており、公的業務など、簡単に仕事が獲得できる業務ほど過当競争になっています。
診断士の数が多すぎる現実
中小企業診断士の資格保有者数は、年々増加の一途をたどっています。この増加傾向は、一見すると資格の人気や価値の高さを示しているように見えますが、実際には市場の飽和状態を招いています。
需要に対して供給が過多となっている状況では、当然ながら競争が激化します。同じような知識とスキルを持つ診断士が大勢いる中で、クライアントから選ばれるためには、何らかの差別化要素が必要になります。しかし、この差別化こそが多くの診断士にとって大きな課題となっているのです。
特に独立開業を目指す診断士にとって、この競争の激化は深刻な問題です。限られた案件を多数の診断士が奪い合う状況では、報酬単価の下落も避けられません。結果として、案件を獲得できたとしても、十分な収入を得ることが困難になっているのです。
他資格との競合関係
中小企業診断士が直面している競争は、同じ診断士同士だけではありません。税理士、社会保険労務士、行政書士など、他の士業との競合も激しくなっています。
これらの他士業は、それぞれ独占業務を持っているため、中小企業診断士よりも安定した収入基盤を持っています。一方、中小企業診断士には独占業務がないため、常に他の専門家との競争にさらされる状況にあります。
さらに、近年では大手コンサルティング会社が中小企業向けのサービスを強化していることも、個人の診断士にとっては脅威となっています。豊富な人材とリソースを持つ大手企業との競争では、個人の診断士が不利になることは避けられません。
実務経験の不足という根本的問題



個人的に普段いろんな診断士と接していて思うのは、自分の専門分野を持ってない診断士があまりに多いという点です。例えば僕の専門はマーケティングですが、僕ほどの知識や経験を持っている診断士は見たことがありません。
資格だけでは通用しない現実
中小企業診断士の資格取得者の多くが直面する問題の一つが、実務経験の不足です。試験に合格し、資格を取得したからといって、すぐに企業経営に関する実践的なアドバイスができるわけではありません。
企業の経営者や管理者は、理論的な知識よりも、実際の経営現場での経験に基づいたアドバイスを求めています。しかし、多くの新人診断士は、このような実践的な経験が不足しているため、クライアントから信頼を得ることが困難なのです。
この問題は、資格取得前には十分に認識されていないことが多く、実際に診断士として活動を始めてから深刻な壁として立ちはだかります。理論的な知識は豊富でも、それを実際の経営改善に活かす能力が不足しているため、期待していたような成果を上げることができないのです。
経験を積む機会の限られた状況
実務経験を積むためには、実際のコンサルティング案件に携わる必要がありますが、経験の浅い診断士がそのような機会を得ることは容易ではありません。多くのクライアントは、実績のあるコンサルタントを求めているため、新人診断士には案件を任せたがらないのです。
この悪循環から抜け出すために、多くの診断士が無料や低価格でのコンサルティングサービスを提供することになります。しかし、このような方法では、経験は積めても十分な収入を得ることはできません。結果として、経験を積むために時間と労力を投入しても、経済的なメリットを得られない状況が続くことになります。
さらに問題なのは、このような低価格での案件ばかりを手がけることで、診断士全体のサービス価値が下がってしまうことです。これは個人の問題にとどまらず、業界全体の問題として深刻化しています。



中小企業診断士に限った話ではないですが、中小企業支援の業界は「自称専門家」の素人が多く、辟易とします。逆にいうと、ある程度専門性を高めて参入すれば、それなりに勝ち目があるとも言えますが。
中小企業の実情とのギャップ
理想と現実の大きな隔たり
中小企業診断士の教科書や試験では、理想的な経営環境や経営手法について学びます。しかし、実際の中小企業の現場は、教科書通りにはいかない複雑で困難な状況に満ちています。
多くの中小企業は、資金不足、人材不足、時間不足という三重苦に悩まされています。このような状況下では、理論的に正しい経営改善提案をしても、実際に実行することが困難な場合が多いのです。診断士が提案する改善策と、企業が実際に取り組める範囲との間には、大きなギャップが存在しているのです。
このギャップを理解せずに、教科書通りの提案を続ける診断士は、クライアントから敬遠されることになります。実際の経営現場では、理想的な解決策よりも、限られた条件の中で実現可能な現実的な改善策が求められているのです。



例えば診断士業界ではSWOT、つまりStrengths(強み)、Weaknesses(弱み)、Opportunities(機会)、Threats(脅威)のフレームワークを使うのが大好きですが、中小企業の経営者にこんな話しても「何のこっちゃ」ですからね。フレームワークに当てはめて企業分析した気になっているのも困りもんだと思います。
中小企業が求めるものと診断士が提供できるもののズレ
中小企業が外部のコンサルタントに求めているのは、多くの場合、即効性のある具体的な解決策です。売上を短期間で向上させる方法、コストを削減する具体的な手法、人材の問題を解決する実践的なアプローチなどが求められています。
しかし、中小企業診断士の知識は、どちらかというと総合的で理論的なものが中心となっています。個別の専門分野における深い知識や、即効性のある実践的な手法については、他の専門家に劣る場合が多いのです。
この需要と供給のミスマッチが、多くの診断士がクライアント獲得に苦労する根本的な原因となっています。中小企業が真に必要としているサービスと、診断士が提供できるサービスとの間に大きなズレがあるのです。



要するに、マーケティングであればいかにお問い合わせを効率良く増やすか、人材採用だったらいかに優秀な人材に来てもらえるかという具体的な部分が必要です。ただそういう具体的な実務ができる診断士は思ったより少ないという印象です。
デジタル化による業界の変化
従来のコンサルティングモデルの限界
近年のデジタル化の進展により、従来のコンサルティングモデルが大きな変革を迫られています。AIや各種デジタルツールの発達により、従来であれば専門家でなければできなかった分析や提案が、誰でも簡単にできるようになってきています。



はっきり言って、ホワイトカラーの9割の仕事はいずれAI代替されます。そう考えると、コンサルティング業界自体が近い将来消滅する可能性はそれなりに高いと考えます。
特に、財務分析や市場分析といった分野では、AIを活用したツールが高い精度で結果を出すことができるようになっています。このような状況では、単純な分析業務や定型的なコンサルティング業務では、人間のコンサルタントの価値が相対的に下がってしまいます。
この変化に対応できない診断士は、今後ますます厳しい状況に置かれることになるでしょう。デジタル化の波に乗り遅れた診断士は、市場から淘汰される可能性が高いのです。
新しいスキルセットの必要性
デジタル化時代において価値を提供し続けるためには、従来の診断士の知識だけでは不十分です。デジタルマーケティング、データ分析、AIツールの活用方法など、新しいスキルセットが必要になっています。
しかし、これらの新しいスキルを習得するためには、相当な時間と労力が必要です。すでに診断士として活動している人にとって、これらの追加学習は大きな負担となります。一方で、これらのスキルを習得しなければ、競争力を維持することが困難になっているのです。
さらに問題なのは、これらの新しいスキルの多くは、中小企業診断士の試験範囲には含まれていないということです。つまり、資格を取得した後も、継続的に新しい知識とスキルを身につけ続けなければならないのです。
まとめ:それでも中小企業診断士を目指すべきか
冷静な判断が必要な時代
ここまで、中小企業診断士の厳しい現実について詳しく説明してきました。これらの現実を踏まえた上で、それでもあなたは中小企業診断士を目指すべきでしょうか。
答えは、あなたの目的と覚悟次第です。もし、資格を取得すれば簡単に成功できると考えているのであれば、その考えを改める必要があります。中小企業診断士として成功するためには、資格取得は最初のステップに過ぎず、その後の努力と工夫が何より重要になります。
一方で、明確な目的意識と十分な覚悟を持っている人にとっては、中小企業診断士という資格が有効な手段となる可能性もあります。ただし、その場合でも、現実を正しく理解した上で、戦略的にアプローチすることが不可欠です。
成功するための条件
もし、それでも中小企業診断士を目指すのであれば、以下の条件を満たしている必要があります。
まず、優れた営業力と人脈形成能力を持っているか、それらを身につける強い意志があることです。資格だけでは仕事は舞い込んできません。自分でクライアントを開拓し、継続的な関係を築く能力が必要です。
次に、特定分野における深い専門知識や実務経験を持っていることです。幅広い知識だけでは差別化が困難です。何らかの専門分野で他の診断士に負けない強みを持つことが重要です。
そして、継続的な学習と成長への強いコミットメントがあることです。デジタル化をはじめとする環境変化に対応し続けるためには、常に新しい知識とスキルを身につけ続ける必要があります。
最後に、長期的な視点で取り組む覚悟があることです。短期間で大きな成果を期待するのではなく、長期的な努力の積み重ねによって徐々に成果を上げていく覚悟が必要です。



あとは表面的な知識でなく、根本的でユニバーサルな知識の習得ですかね。今なら、確率・統計数学と、プログラミングを勉強するのが良いかと思います。
最終的な判断はあなた次第
中小企業診断士という資格には、確かに魅力的な側面もあります。幅広い経営知識を体系的に学べること、様々な業界の企業と関わる機会があること、社会貢献できる可能性があることなどです。
しかし、これらの魅力的な側面だけに惑わされてはいけません。現実には、多くの診断士が期待していたような成果を上げられずに苦労しているのです。
予備校の甘い言葉に惑わされることなく、この記事で紹介したような厳しい現実を十分に理解した上で、冷静に判断することが重要です。もし、これらの現実を受け入れた上で、それでも挑戦したいという強い意志があるのであれば、全力でサポートします。
しかし、もし少しでも迷いがあるのであれば、他の選択肢も含めて慎重に検討することをお勧めします。あなたの貴重な時間と労力、そして経済的な資源を有効に活用するためにも、正しい判断を下すことが何より重要なのです。
中小企業診断士の資格取得を検討している多くの方が、この記事を読んで現実を正しく理解し、後悔のない選択をされることを心から願っています。