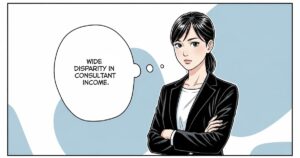中小企業診断士の資格が意味ないと言われる5つの決定的理由|予備校が絶対に話さない年収の真実
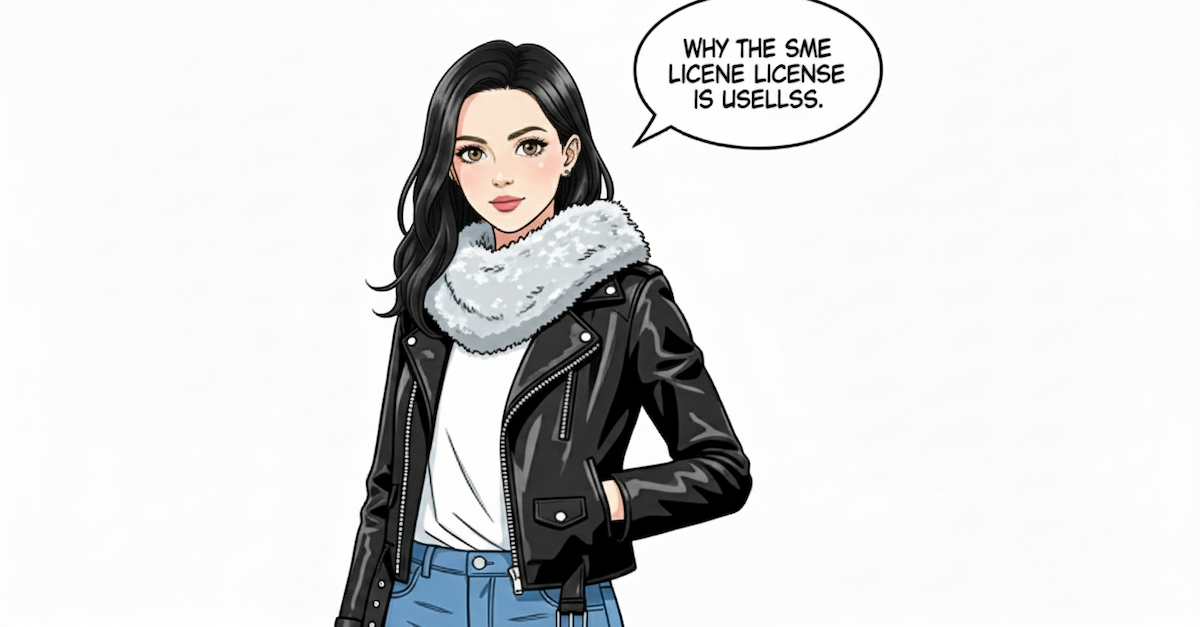
「中小企業診断士を取れば、コンサルタントとして独立できる」
「年収1000万円も夢じゃない」
「転職にも有利になる」
もしあなたが、予備校のパンフレットやネットの情報を見て、こんな期待を抱いているなら、ちょっと待ってください。
私は現役の中小企業診断士として活動していますが、診断士の世界の実態は、あなたが想像しているものとはまるで違います。
実は、診断士資格を取得しても、その7割以上が満足に稼げていないというのが現実なのです。年間の維持費だけで10万円以上かかり、仕事を獲得するには資格以外のスキルが必須。さらに、かつて診断士の主要な収入源だった補助金ビジネスは、もう完全に崩壊してしまいました。
この記事では、予備校や診断協会が決して語らない、中小企業診断士のリアルな実態を包み隠さずお伝えします。なぜ「診断士は意味ない」と言われるのか、その5つの決定的な理由を、現場の生の声とデータをもとに解説していきます。
この記事を読めば、中小企業診断士という資格の本当の価値と、それでもなお挑戦する価値があるのかどうかが、はっきりと分かるはずです。

結論から言えば、「資格を取れば安泰」という時代は、とっくに終わ離ました。
なぜ中小企業診断士は「意味ない」と言われるのか|資格取得者の7割が稼げていない衝撃の実態
中小企業診断士は「経営コンサルタントの国家資格」として知られ、ビジネスパーソンが取得したい資格ランキングでも常に上位に入る人気資格です。しかし、その華やかなイメージとは裏腹に、資格取得者の多くが「取っても意味がなかった」と感じているのが実情です。
なぜこのようなギャップが生まれるのでしょうか。その背景には、診断士業界の構造的な問題が潜んでいます。
企業内診断士が全体の7〜8割を占め、ほとんどが資格を活かせていない現実
中小企業診断士の資格保有者のうち、実に7〜8割が企業内診断士として、会社に勤めながら資格を保有しているのが実態です。独立して活動している診断士は、全体のわずか2〜3割に過ぎません。
この企業内診断士の多くは、以下のような状況に置かれています:
- 副業禁止の会社に勤めており、診断士としての活動が一切できない
- 資格手当もなく、昇進にも影響しない
- コンサルティングの実務経験を積む機会がない
- 診断士の知識を業務で活かす場面がほとんどない
つまり、せっかく難関試験を突破して資格を取得しても、その大半の人が「資格を持っているだけ」の状態になっているのです。年会費だけを払い続け、5年ごとの更新要件を満たすために苦労している、いわば「ペーパー診断士」が大量に存在しているのが現実なのです。
年収調査の罠|実は稼げていない人の大半がデータから除外されている
診断協会が発表する年収調査では、「年収1000万円以上が約30%」「500万円以上が約66%」という一見すると魅力的な数字が並んでいます。しかし、ここには巧妙なトリックが隠されています。
実は、この年収調査は「年間100日以上コンサルティング業務に従事した人」だけを対象にしているのです。アンケート全体の回答者1,892名のうち、年収に関する質問に答えたのはわずか579名。つまり、約7割の診断士がそもそも調査対象から除外されているのです。
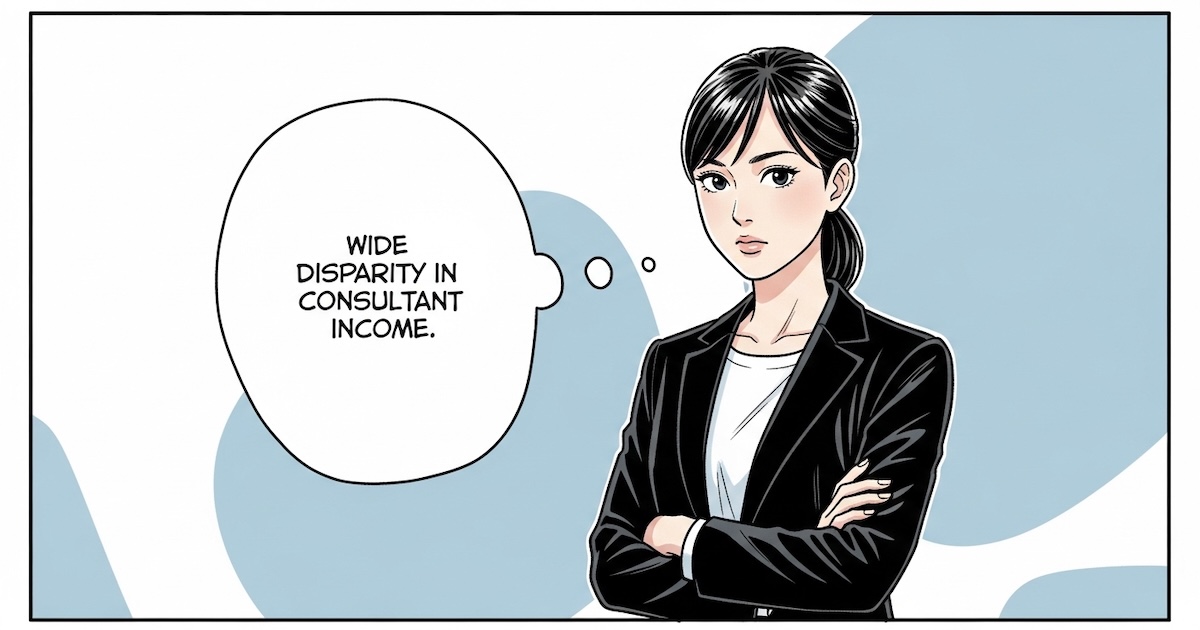
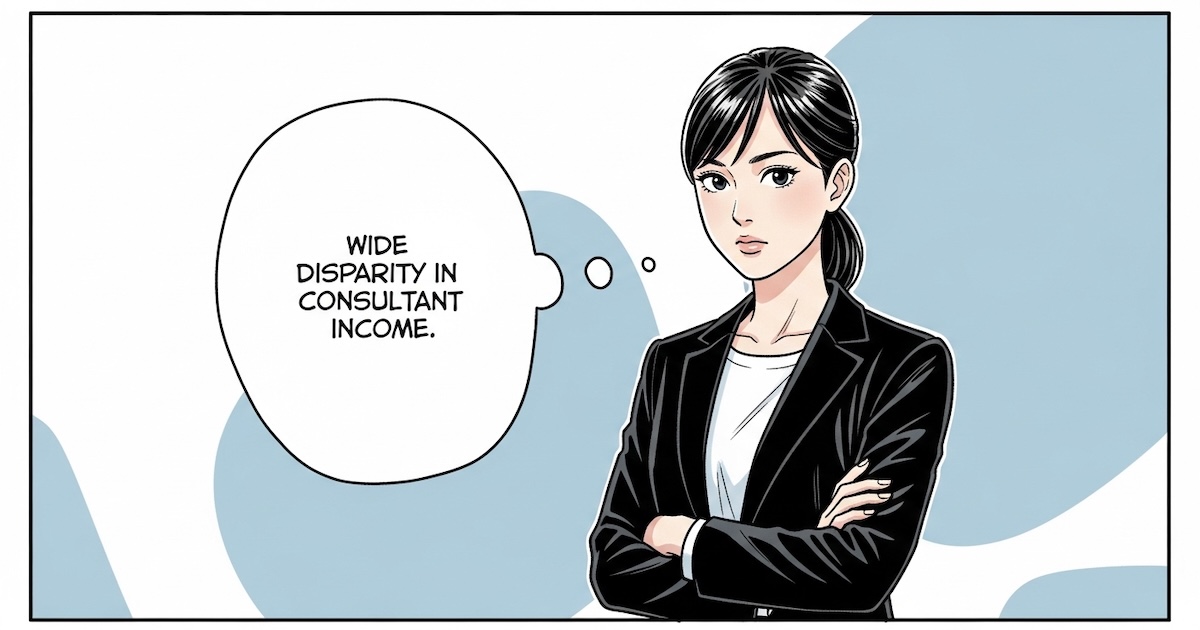
これは何を意味するのでしょうか:
- コンサル業務をほとんどしていない「稼げていない診断士」が最初から除外されている
- ある程度稼げている人だけのデータなので、数字が良く見えるのは当然
- 診断士全体の年収実態とは大きくかけ離れている
つまり、診断協会が公表している年収データは、診断士のリアルな実態を反映していないのです。本当の平均年収は、公表されている数字よりもはるかに低いと考えるべきでしょう。
診断協会の体験談や予備校の成功事例は「生存者バイアス」の塊
予備校のパンフレットや診断協会のホームページには、「独立して年収2000万円達成」「大手企業のコンサルタントとして活躍」といったキラキラした成功事例があふれています。
しかし、これらは典型的な「生存者バイアス」の例です。成功した一握りの人だけがクローズアップされ、その陰で苦労している大多数の診断士の声は表に出てこないのです。


実際の診断士の多くは:
- 仕事が全く取れずに廃業する
- 補助金申請の下請けで年収200〜300万円程度
- 企業内で資格を活かせず、ただ維持費を払い続ける
このような「語られない失敗談」の方が圧倒的に多いのが実情です。しかし、こうした情報は予備校の営業に都合が悪いため、決して表に出ることはありません。



「中小企業診断士を取ってもどうやって稼ぐかイメージが湧かない」という話を良く聞きますが、単純に稼いでいる人がいないので、情報が出回ってないという側面もあると思います。
理由1:独占業務がないため、資格だけでは仕事が獲得できない
中小企業診断士が「意味ない」と言われる最大の理由は、独占業務が存在しないことです。これは、他の士業と比較すると、致命的な弱点となっています。
弁護士や税理士と違い、診断士にしかできない仕事が存在しない
士業の世界では、独占業務の有無が資格の価値を大きく左右します:
- 弁護士:訴訟代理、法律相談(独占業務)
- 税理士:税務申告、税務相談(独占業務)
- 社会保険労務士:社会保険手続き、労務管理(独占業務)
- 中小企業診断士:独占業務なし
診断士が行う経営コンサルティングは、誰でもできる仕事です。資格がなくても「経営コンサルタント」を名乗ることは可能ですし、実際に無資格で活躍しているコンサルタントも多数存在します。
つまり、診断士資格は「できること」を増やすのではなく、「信頼性」を少し高めるだけの資格なのです。しかし、その信頼性すら、次に述べる認知度の低さによって、ほとんど機能していないのが現実です。
「中小企業診断士です」と名乗っても、世間の認知度は驚くほど低い
実際にコンサルティングの現場で「中小企業診断士です」と名乗っても、相手の反応は「ふーん」程度がほとんどです。
一般的な中小企業の社長の反応:
- 「それって何をする資格なの?」
- 「税理士さんとは違うの?」
- 「へぇ、そんな資格があるんだ」
資格の名前すら知らない人が大半で、知っていても「何ができる人なのか」を理解している人はほとんどいません。これでは、資格が営業ツールとして機能するはずがありません。
実際、診断士として独立している人の多くは、資格よりも「元○○会社の営業部長」「マーケティング歴20年」といった実務経験の方をアピールポイントにしています。資格は添え物程度の扱いなのです。



僕も中小企業診断士で独立して15年ほど経ちますが、中小企業診断士であることが仕事に有利になったことはほぼありません。補助金の仕事をやる時に、有資格者なのでやややり易いといった程度です。
資格を取っても、営業力とマーケティング力がなければ1円も稼げない
独占業務がなく、認知度も低い診断士資格。では、どうやって仕事を獲得するのでしょうか。答えは明確です。営業力とマーケティング力がすべてです。
診断士として稼ぐために必要なスキル:
- 営業力:自分を売り込み、信頼関係を構築する力
- マーケティング力:見込み客を見つけ、価値を伝える力
- 実務能力:実際に成果を出せる専門知識とスキル
皮肉なことに、これらのスキルは診断士試験では一切問われません。試験で学ぶのは経営理論やマーケティングの知識だけで、実際にクライアントを獲得する方法は教えてくれないのです。
その結果、多くの診断士が「資格は取ったけど、どうやって仕事を取ればいいか分からない」という状況に陥っています。資格を取っただけでは、1円も稼げない。これが、診断士の残酷な現実なのです。
理由2:補助金バブル崩壊で、簡単に稼げる時代は完全に終わった
2021年から2023年にかけて、診断士業界には「補助金バブル」と呼ばれる異常な好景気が訪れていました。しかし、そのバブルは完全に崩壊し、多くの診断士が収入源を失っているのが現状です。
2021年〜2023年の補助金バブルで下請けでも年収1000万円が可能だった異常事態
コロナ禍で傷んだ企業を支援するため、政府は前例のない規模の補助金を投入しました:
- 事業再構築補助金:総額1兆1,485億円
- IT導入補助金:毎月のように募集、採択率も高い
- ゼロゼロ融資:無利息・無担保で借りられる特別融資
特に事業再構築補助金は、補助額が最大1億円という破格の規模でした。診断士の報酬は採択額の10〜15%が相場だったため、2,000万円の案件が通れば、それだけで200〜300万円の報酬が得られたのです。
この時代の診断士の収入例:
- 年間10件の申請支援で1,200万円以上
- 下請けでも月100万円超えが珍しくない
- IT導入補助金の量産で安定収入を確保
まさに、「誰でも簡単に稼げる」夢のような時代でした。しかし、この異常事態は長くは続きませんでした。
不正の横行と予算縮小により、IT導入補助金も事業再構築補助金も稼げなくなった
補助金バブルの崩壊には、複数の要因が重なりました:
1. 不正の大量発覚
- 事業再構築補助金:コンサルタントによる計画書の完全代行が横行
- IT導入補助金:ランダム検査で8%に不正が発覚
- 実質無料スキームなどの悪質な手法が蔓延
2. 審査の厳格化
- 採択率が50%から20%~30%程度に激減
- 審査基準が大幅に厳しくなり、簡単には通らない
- 不正に対する監視体制の強化
3. 予算の大幅縮小
- 補助金の全体予算が激減
- 募集回数の減少
- 補助上限額の引き下げ
その結果、かつてのように簡単に稼げる状況は完全に終わりました。もはや、補助金だけで食べていくことはかなり難しくなりました。



体感的には補助金バブル前とバブル後だと、案件数自体は1/3くらいに減っていると感じています。一方、競合する診断士は増えているので、安定顧客を持ってない場合は、補助金だけで食っていくのは、今後相当厳しと思います。
補助金に依存していた診断士の倒産・廃業が相次いでいる現実
補助金バブルの崩壊は、多くの診断士に深刻な影響を与えています:
実際に起きている事例:
- 大阪の「北浜グローバル経営」の倒産がニュースに
- 月収100万円から20万円以下に激減した診断士が続出
- 廃業や会社員への転職を余儀なくされる独立診断士


私の周りでも、以下のような悲惨な状況が見られます:
- 補助金収入がゼロになり、生活費も稼げない
- 借入金の返済ができず、自己破産寸前
- 独立を諦めて、再就職活動をする40代・50代



「経営コンサル」ができる診断士が廃業・破産するとは妙なものですが、例えば補助金コンサルタントは補助金の申請書を書くことはできますが(それすら怪しいのも多いのが実態ですが)、営業・マーケ・経営のプロではないので、新たな顧客を見つけてきたり、新しいビジネスを創造する力は相当弱いです。
「事業再構築補助金は、誰も幸せにならない最低の補助金だった」と、心ある診断士の間では言われています。補助金で一時的に潤った企業も、見通しの甘い事業で赤字を垂れ流し、最終的に倒産するケースが相次いでいるのです。
補助金バブルは終わりました。これからの診断士は、補助金に頼らない新たなビジネスモデルを構築しなければ生き残れません。しかし、多くの診断士にはその準備ができていないのが現実なのです。
理由3:維持費が高額で、資格を持っているだけで年間10万円以上が消える
中小企業診断士の資格は、取得するのも大変ですが、維持するのも大変です。資格を持っているだけで、毎年10万円以上の出費が発生するという事実を、予備校は決して教えてくれません。
診断協会の年会費だけで5万円、支部会費を含めると7〜8万円の負担
診断士資格を維持するための基本的な費用:
- 中小企業診断協会の年会費:50,000円
- 診断実務従事ポイントの購入 : 50,000円(1ポイント1万円)
- 理論政策更新研修 : 5000円
- 合計:年間約10万円
これは最低限の費用です。さらに、協会内の研究会やマスターコースに参加すれば、追加で年間数万円から10万円以上かかることも珍しくありません。


診断士には独占業務がなく、資格さえあれば自動的に案件が来るわけではないことを考えると、この金額は割に合わないと言わざるを得ません。
5年ごとの更新に必要な理論政策更新研修は1回5,000円×5回=2.5万円
診断士資格は5年ごとに更新が必要で、そのためには以下の要件を満たす必要があります:
理論政策更新研修
この研修は、診断士としての知識をアップデートするためのものですが、内容については賛否両論があります:
- 「毎回同じような内容で、新しい学びが少ない」
- 「講師のレベルにばらつきがある」
- 「ただの既得権益の温床になっている」
それでも、受講しなければ資格を失うため、半ば強制的に支払わされるのが実情です。



とはいえ、大塚商会などのやっている民間の理論政策更新研修であれば、かなりマシなので、そういう民間の研修を受けるのが良いと思います。診断協会主催の研修はつまらなく、何の役にも立たないので、やめておいた方が良いでしょう。
実務ポイントを稼ぐための研修は有給を使って年間5〜6万円を自腹で支払う必要がある



更新要件の中で最も負担が大きいのが、「実務ポイント」です。これは、5年間で30日以上の中小企業のコンサルティング業務を実施し、その照明を更新時に提出する必要があります。
実務従事ポイントの要件
- 5年間で30ポイント(30日分)の実務従事が必要
- 企業内診断士の多くは実務機会がない
- 協会主催の実務補習を受けるしかない
実務補習の実態:
- 5日間コース:50,000〜60,000円
- 15日間コース:150,000円以上
- しかも平日開催が多く、有給休暇を使う必要がある
つまり、企業内診断士は以下の三重苦を強いられます:
- お金を払って(5〜6万円)
- 有給を使って(5日間)
- 無報酬で企業のコンサルティングをする
「お金を払ってタダ働きをする」という、普通に考えればあり得ない状況が、診断士の世界では当たり前になっているのです。
さらに悪いことに、この実務補習には「講師ガチャ」が存在します。協会にコネがある講師が担当することが多く、能力や指導力にばらつきがあるため、ひどい講師に当たると、お金も時間も精神力も削られる最悪の体験になります。
これだけのコストをかけて維持する価値が、独占業務もない診断士資格にあるのでしょうか。多くの診断士が「割に合わない」と感じているのも、無理はありません。
理由4:AIの進化により、知識提供型の診断士業務の7割が代替可能になった
テクノロジーの進化、特にAI(人工知能)の急速な発展は、診断士の仕事に革命的な変化をもたらしています。もはや「知識を持っている」だけでは、価値を提供できない時代が到来したのです。
高卒の素人でもAIを使えば事業計画書の8割が作成できる衝撃の事実
私は実際に、以下のような実験を行いました:
実験内容:
- 高校卒業の経営知識ゼロの人材を採用
- AIツール(ChatGPT等)の使い方を教える
- 事業再構築補助金の事業計画書を作成させる
驚愕の結果:
- ベテランコンサルタント2名が評価
- 「これは8割完成している」という評価
- プロの診断士が書くものと遜色ないレベル
つまり、まったくの素人でも、AIを使えばプロ並みの成果物が作れる時代になったのです。これは、診断士の存在価値を根本から揺るがす事実です。



ちなみに、その直後、「補助金コンサル養成セミナーの講師をしている」という診断士の補助金の事業計画書をレビューする機会がありましたが、内容が全くはちゃめちゃで、下手な自称プロよりはAIの方が遥かに賢いです(笑)
補助金申請書作成、財務分析、市場調査などの業務がAIに置き換わっている
現在、AIによって代替されている診断士業務:
1. 補助金申請書の作成
- 事業計画のテンプレート生成
- SWOT分析の自動作成
- 市場分析データの収集と整理
2. 財務分析
- 財務諸表の自動分析
- キャッシュフロー予測
- 経営指標の算出と評価
3. マーケティング支援
- 市場調査レポートの作成
- 競合分析
- マーケティング戦略の立案
私自身の実感として、1年前は仕事の2〜3割がAIに置き換わると思っていましたが、現時点ですでに7割がAIで代替可能になっています。この変化のスピードは、想像をはるかに超えていますし、この大きな津波は逃れることができないと思います。
10年後にはコンサルタントという職業自体が消滅する可能性
このままAIの進化が続けば、どうなるでしょうか:
5年後の予測:
- 定型的なコンサルティング業務の9割がAI化
- 人間のコンサルタントは「翻訳者」的な役割に
- 診断士資格の価値がさらに低下
10年後の可能性:
- AIが経営者と直接対話して課題解決
- コンサルタントという職業自体が不要に
- 診断士資格が完全に形骸化



すでに、戦略系コンサルのように、AIに代替可能なコンサルティングファームからどんどん人材の削減が進んでいます。市場のパイは定まっているため、ここから減少の一途を辿り、増加することはないでしょう。
診断士が生き残るために必要な要素:
- ビジョンと戦略立案能力:AIには描けない未来を構想する力
- 人間関係構築力:経営者の心理的サポート
- 現場での実行支援:理論を実践に落とし込む力
しかし、これらの能力は診断士試験では測れません。つまり、資格の有無と、AI時代に必要な能力は、まったく関係がないのです。
「知識」で勝負する時代は終わりました。診断士資格が提供する「知識の証明」という価値は、AIの前ではほとんど意味を持たないのが現実なのです。



特に士業は「アイデアが乏しい」「コミュニケーションが苦手」なバックオフィス型の人材が多いので、これからどんどん仕事を失っていくと思います。
理由5:転職市場での評価はほぼゼロ|資格より実務経験が圧倒的に重視される
「診断士資格があれば転職に有利」という言葉を信じて資格取得を目指す人は多いですが、これは真っ赤な嘘です。転職市場における診断士資格の評価は、驚くほど低いのが実態です。



特に診断士については、資格により転職が有利になることはほぼゼロです。
診断士資格があっても転職で有利になることはほとんどない
私自身、診断士資格取得後に2回転職を経験しましたが、資格が有利に働いたことは一度もありませんでした。
転職活動での現実:
- 面接で診断士資格について聞かれたことはゼロ
- そもそも中小企業診断士の資格名を知っている程度
- 給与交渉で資格が評価されることもない
なぜ診断士資格が評価されないのか:
- 独占業務がないため、資格の必要性がない
- 認知度が低く、何ができる資格か理解されていない
- 実務能力との相関が低いと認識されている
信用金庫など一部の金融機関を除き、企業は資格より経験を評価する
診断士資格が評価される例外的なケース:
1. 信用金庫・地方銀行
- 中小企業支援の専門部署で需要あり
- 資格手当が出るケースも(月1〜3万円程度)
- 昇進で有利になる可能性
2. 一部の大手企業
- 経営企画部門で若干の評価
- ただし、MBAの方が評価は高い(特に外資系)
3. 公的支援機関
- 商工会議所、中小企業支援センターなど
- ただし、給与水準は低い
しかし、これらは全体から見ればごく一部の例外です。一般的な企業では、診断士資格はほとんど評価されません。
「診断士資格で転職に有利」という予備校の宣伝文句は真っ赤な嘘
予備校のパンフレットには、必ずと言っていいほど「転職に有利!」という文言が踊っています。しかし、これは明らかな誇大広告です。
企業が本当に求めているもの:
実務経験の例:
/
- 「営業で3年連続目標達成、売上2億円を管理」
- 「子会社社長として黒字化を達成」
- 「マーケティング部門で新規事業を立ち上げ」
これらの具体的な実績の方が、診断士資格の100倍価値があります。
転職市場の現実:
- 35歳以上の転職では、マネジメント経験が最重要
- 専門分野での実績と人脈が評価される
- 資格は「おまけ」程度の扱い
もし転職のために診断士資格を取ろうと考えているなら、その時間と労力を実務経験を積むことに使った方が、はるかに有益です。
診断士資格は、転職市場においては「ないよりはマシ」程度の価値しかありません。年間10万円以上の維持費と、取得に要する1000時間以上の勉強時間を考えれば、コストパフォーマンスは最悪と言わざるを得ません。



診断士の試験の内容自体は悪くないので、自己啓発的に、自習で試験勉強するくらいならいいと思います。ただ、例えば2次試験免除の養成課程に200万円~300万円も払って取得する価値のある資格ではありません。
それでも診断士資格を取る意味はあるのか?|残された3つの活用法
ここまで、診断士資格の厳しい現実を述べてきました。しかし、完全に無価値というわけではありません。正しい戦略と覚悟があれば、まだ活用できる道は残されています。
認定支援機関の取得が容易になり、補助金コンサルの入口は作れる
診断士資格の最大のメリットの一つが、「認定支援機関」になりやすいことです。
認定支援機関とは:
- 国が認定する中小企業支援の専門機関
- 特定の補助金申請で必須要件となる
- 一般的には取得が困難
診断士が認定支援機関になるメリット:
- 早期経営改善計画の支援が可能
- 補助金申請での信頼性向上
- 認定支援機関の確認書が必要な補助金多数
- 事務局への問い合わせ権限
- 独立3年で比較的簡単に取得可能
ただし、注意点もあります。認定支援機関は研修を受ければ診断士資格がなくても取得可能です。それでも、診断士の方が取得しやすいのは事実であり、これは明確なメリットと言えるでしょう。
金融機関からの信頼は厚く、融資支援では大きな武器になる
診断士資格が最も威力を発揮するのは、金融機関との連携です。
銀行員の診断士に対する評価:
- 「診断士さんが関わっているなら安心」
- 「稟議が通りやすくなる」
- 「ぜひ一緒に支援したい」
融資支援での活用方法:
- 融資申込みの同行支援
- リスケジュール交渉の支援
- 返済計画の見直し提案
- 改善計画の策定
- 銀行との信頼関係構築
- 制度融資の活用提案
注意点: 報酬をもらって金融機関と「交渉」することは弁護士法違反になる可能性があります。あくまで「支援」「アドバイス」に留める必要があります。
定期コンサルを狙い、営業力とマーケティング力があれば独立も可能
最後に、診断士として本当に稼ぎたいなら、狙うべきは「定期コンサル」一択です。
定期コンサルの魅力:
- 月額10〜30万円の安定収入
- 5社獲得で月収50〜150万円
- 長期的な関係構築が可能
成功のために必要な要素:
- 専門分野の確立
- 営業力とマーケティング力
- クライアント獲得コスト:1社10万円以上
- 初期投資として300〜400万円は必要
- できれば1000万円の資金があれば安心
- 実績の積み上げ
現実的な成功パターン:
- 未経験でも定期コンサルを獲得している人は存在する
- ただし、100人中5人程度の狭き門
- 成功者の共通点は「営業力」と「行動力」
診断士資格は、あくまでも信頼性を少し高めるツールに過ぎません。本当に必要なのは、ビジネススキルと覚悟です。
まとめ:中小企業診断士は「資格を取れば安泰」ではない|覚悟を持って挑戦すべき理由
資格だけで稼げる時代は終わり、ビジネススキルが必須の時代へ
ここまで読んでいただいて、中小企業診断士の厳しい現実がお分かりいただけたと思います。
診断士資格の現実:
- 独占業務がなく、資格だけでは仕事が取れない
- 年間10万円以上の維持費がかかる
- 補助金バブルは崩壊し、簡単に稼げる時代は終わった
- AIによって知識の価値は急速に低下している
- 転職市場での評価はほぼゼロ
もはや「資格を取れば安泰」という時代は完全に終わりました。これからの診断士に求められるのは、資格の知識ではなく、実践的なビジネススキルです。
新時代の診断士に必要な3つの力:
- 営業力・マーケティング力
- 専門性と実務能力
- 特定分野での圧倒的な強み
- 机上の空論ではない実践力
- 成果を出せる問題解決力
- ビジョンと人間力
AIと共存し、営業力・マーケティング力・ビジョンを持つ診断士だけが生き残る
AIの進化は止まりません。今後、診断士の仕事の多くがAIに代替されることは避けられない現実です。しかし、AIを敵視するのではなく、共存する道を選ぶべきです。
AI時代の診断士の生存戦略:
- AIを使いこなす側になる
- AIにできないことに特化
- 経営者の心理的サポート
- 現場での実行支援
- ビジョンの構築と戦略立案
- 常に学び続ける姿勢
生き残れる診断士は、おそらく全体の1〜2割でしょう。しかし、その1〜2割に入ることができれば、生き残れる可能性があります。



とはいえ、そもそもAIの進展によってコンサルティング業界自体が無くなる可能性もあるので、既存のコンサルティングにこだわらない新たなサービスも考えていく必要があるかと思います。
それでも挑戦する価値|本気で中小企業を支援したい人への最後のメッセージ
ここまで厳しい現実を述べてきましたが、私は診断士という仕事自体を否定しているわけではありません。
診断士の仕事の本質的な価値:
- 困っている中小企業を助けることができる
- 経営者の孤独に寄り添える
- 日本経済の基盤を支える仕事
もしあなたが、以下のような思いを持っているなら、診断士への挑戦は価値があるかもしれません:
✓ 本気で中小企業を支援したいという情熱がある ✓ 厳しい現実を受け入れる覚悟がある ✓ 営業力とマーケティング力を身につける意欲がある ✓ AIと共存しながら進化し続ける柔軟性がある ✓ 資格に頼らず、実力で勝負する決意がある
まとめ
診断士資格は、「ゴール」ではなく「スタートライン」です。資格を取ったからといって、自動的に仕事が来るわけではありません。成功への道のりは険しく、多くの人が途中で挫折します。
しかし、本当の実力を身につけ、正しい戦略で行動すれば、まだチャンスは残されています。定期コンサルで月収100万円を超える診断士も、少数ですが確実に存在します。
大切なのは、幻想を捨てて現実を直視すること。そして、その上で「それでもやる」という覚悟を持つことです。
この記事が、あなたの人生の選択に少しでも役立てば幸いです。予備校や診断協会が決して語らない「本当の話」を知った上で、あなたがどんな選択をするのか。
その決断を、心から応援しています。