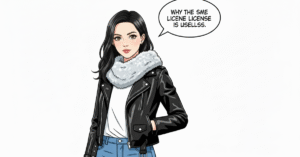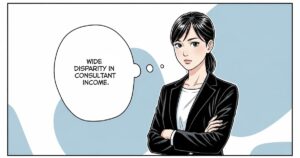【2025年最新】中小企業診断士の年収の真実|年収1000万円超は可能なのか検証

「中小企業診断士になれば年収1000万円も夢じゃない!」
「資格を取れば安定して稼げるようになる!」
「独立すれば高収入が約束される!」
ちょっと待ってください。
あなたが今見ている情報は、本当に「リアル」な数字でしょうか?
この記事では、診断協会の公式データから読み取れる年収の実態、そして予備校や成功者の体験談では決して語られない「稼げない診断士」の現実まで、データと経験に基づいて徹底的に解説します。
読み終わる頃には、中小企業診断士の年収について、誰よりも正確な知識を持っているはずです。そして、それでもなおこの資格を目指すのか、冷静に判断できるようになるでしょう。

データについては、基本的には、下記の診断士協会のアンケートに基づいています。
衝撃のデータ!中小企業診断士の年収分布の真実
まず、中小企業診断協会が実施した最新の調査データから、診断士の年収分布を見ていきましょう。このデータは1,207名の診断士から得られた情報です。
総人数: 1,207人のデータを可視化
驚愕!年収500万円以下が全体の40.58%
データを分析すると、平均年収はそこそこだが、一方で年収500万円以下の診断士が全体の40.58%を占めているという事実が明らかになりました。
具体的な内訳を見てみましょう。年収100万円以下が9.36%、101万円~200万円が7.54%、201万円~300万円が8.12%、301万円~400万円が7.46%、401万円~500万円が8.29%となっています。
つまり、10人中4人は一般的なサラリーマンの平均年収にも満たないというのが現実なのです。
この数字を見て、「え?中小企業診断士って難関資格じゃないの?」と思われた方も多いでしょう。確かに、中小企業診断士試験の合格率は一次試験で約30%、二次試験で約20%という狭き門です。それなのに、なぜこれほどまでに低収入の診断士が多いのでしょうか。
最も多い年収帯は「501万円~800万円」
一方で、最も構成比が高いのは「501万円~800万円」の層で、全体の19.55%を占めています。これは独立して活動する診断士の標準的な収入水準と考えられます。
続いて「801万円~1,000万円」が13.34%、「1,001万円~1,500万円」が14.66%となっており、年収1,000万円を超える層も確実に存在しています。実際、年収1,001万円以上の診断士は全体の26.34%、つまり4人に1人以上が1,000万円プレーヤーという計算になります。
しかし、ここで注意すべき点があります。このデータには大きなカラクリが隠されているのです。
隠されたデータのトリック
実は、この年収調査には重要な前提条件があります。それは「1年間にコンサルティング業務に従事した日数が100日以上」の診断士のみを対象としていという点です。
つまり、コンサルティング業務をほとんど行っていない診断士、例えば企業内診断士で副業をしていない人や、資格は持っているが実務をしていない「ペーパー診断士」は、このデータから除外されているのです。
また、このアンケートの回答数は4,649名ですが、年収に回答した人は1,207名と1/4程度です。
もし、すべての診断士を対象にした調査を行えば、年収分布はさらに低い方にシフトすることは間違いありません。予備校や資格学校が宣伝で使う「診断士の平均年収」という数字が、いかに実態とかけ離れているかがお分かりいただけるでしょう。
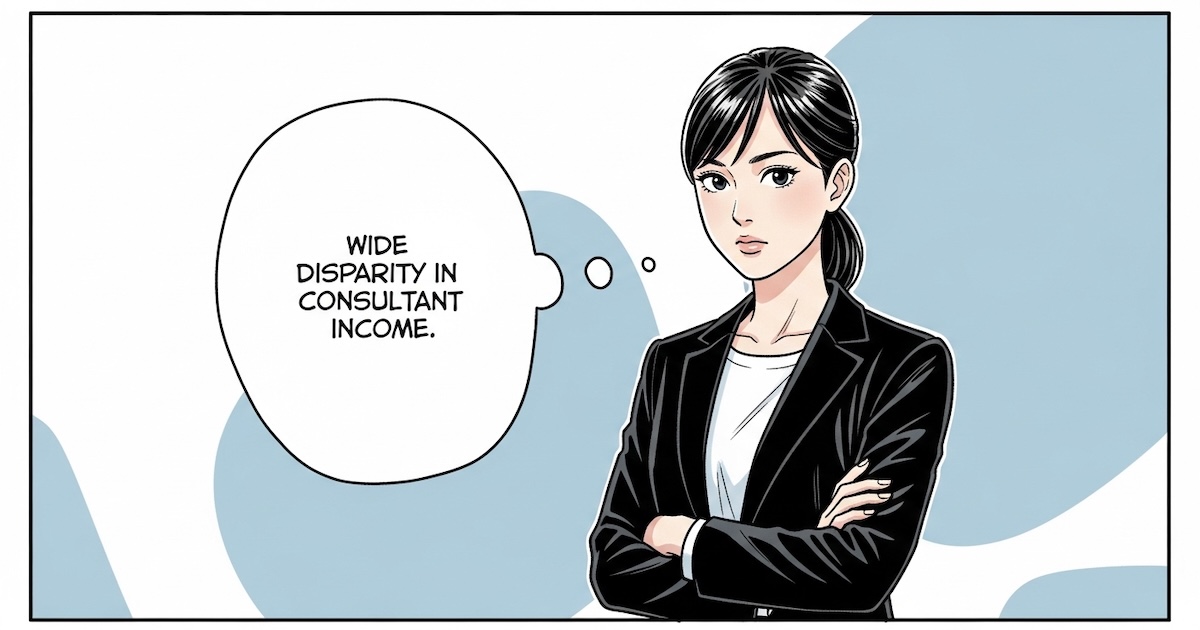
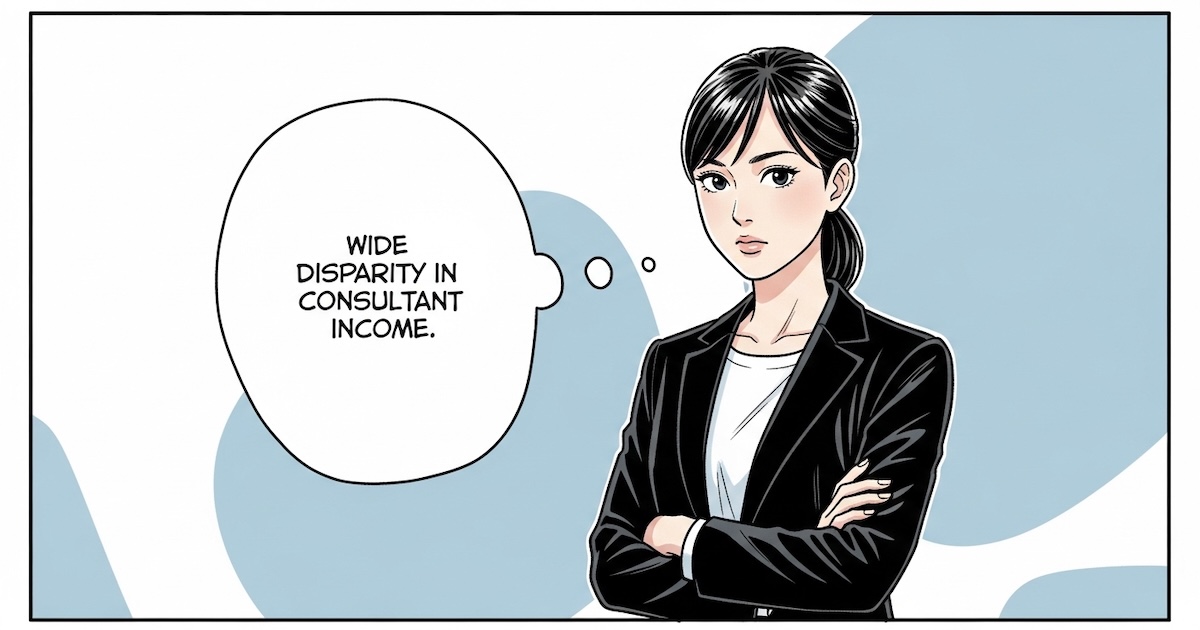
なぜ年収格差が生まれるのか?3つの活動形態を徹底解説
なぜこれほどまでに年収格差が生まれるのでしょうか?その答えは、診断士の「活動形態」にあります。中小企業診断士と一口に言っても、その働き方は大きく3つに分かれており、それぞれで収入構造が全く異なるのです。
活動形態① 企業内診断士(全体の約70%)
実は、診断士の約7割は企業に勤めながら資格を保有する「企業内診断士」です。彼らの診断士としての直接的な収入は、ほぼゼロか、副業として認められている場合でも限定的です。
私が知る企業内診断士の多くは、「いつかは独立したい」という夢を抱きながら、日々の業務に追われています。診断士資格を取得した当初は意気込んでいても、会社の仕事が忙しく、診断士としての活動はほとんどできていないのが実情です。
企業によっては資格手当が支給されることもありますが、その額は月額5,000円~30,000円程度が相場です。年間で考えても6万円~36万円。これを「診断士としての収入」と呼べるかは疑問です。
さらに深刻なのは、多くの企業で副業が禁止されているという現実です。せっかく診断士資格を取得しても、それを活かして収入を得ることができません。土日に無料で知人の相談に乗る程度が精一杯という診断士も少なくありません。
企業内診断士のジレンマは、「資格は持っているが使えない」という点にあります。診断士としての実務経験を積むことができず、いざ独立しようと思っても、実績がないため顧客獲得に苦労することになります。
活動形態② 副業診断士(全体の約10%)
本業を持ちながら、週末や夜間に診断士として活動する層です。最近は副業を解禁する企業も増えてきており、この層は今後増加していくと予想されます。
副業診断士の主な収入源は以下のようなものです:
補助金申請の支援は最も一般的な副業です。事業再構築補助金やものづくり補助金などの申請支援を行い、採択された場合に成功報酬として補助金額の10~15%を受け取ります。1件あたり20万円~50万円の報酬が相場ですが、申請書の作成には相当な時間がかかります。土日をフルに使っても1ヶ月に1~2件が限界でしょう。



かつて補助金バブルの時代は、企業内診断士でも副業で年間で数百万円稼げたこともありましたが、今はそんなに案件がないので、年間、百万円単位で稼いでいる企業内診断士はほぼいないかと思います。
セミナー講師も人気の副業です。商工会議所や金融機関主催のセミナーで講師を務めると、1回あたり3万円~10万円の謝礼が得られます。ただし、準備時間を考えると時給換算では決して高くありません。また、平日昼間の開催が多いため、有給休暇を使う必要があることも多いです。
執筆活動は在宅でできる点が魅力です。専門誌への寄稿や書籍の執筆など、原稿料は1文字1円~5円が相場です。1万文字の記事で1万円~5万円という計算になりますが、執筆には相当な時間と労力が必要です。
副業診断士の年間収入は数万円程度というのが一般的です。本業があるので生活には困りませんが、「診断士として稼いでいる」という実感は薄いかもしれません。
活動形態③ 独立診断士(全体の約20%)



フルタイムで診断士として活動する層ですが、その中でも大きな格差があります。
独立診断士と聞くと、自由に仕事を選び、高収入を得ているイメージがあるかもしれません。しかし、現実はそう甘くありません。
独立診断士の中でも、自分で直接クライアントから仕事を取ってくる『元請け』になれているのは、全体の2割程度で、残りの8割は下請けとして、仕事をもらって食い繋いでいるのが実態です。
この「元請け」と「下請け」の違いは、収入に直結します。元請けは顧客から直接受注するため、利益率が高く、年収1,000万円以上も十分可能です。一方、下請けは元請けから仕事を回してもらう立場で、報酬の約70%を元請けに中抜きされるのが業界の相場です。
例えば、補助金申請の着手金が20万円だった場合、元請けが14万円を取り、下請けには6万円しか回ってきません。これでは、いくら頑張っても年収は上がりません。
補助金バブル崩壊で激変した収入構造
2021年から2023年にかけて、診断士業界には「補助金バブル」と呼ばれる特需がありました。しかし、2024年以降、この構造は完全に崩壊しています。この変化は、診断士の収入構造に決定的な影響を与えました。
かつての「黄金時代」の実態
コロナ禍で導入された事業再構築補助金は、総額1兆1,485億円という戦後最大規模の予算でした。この補助金は、コロナで打撃を受けた企業が新しい事業に挑戦することを支援するもので、最大で1億円もの補助金が支給されました。
当時の状況を振り返ると、まさに「誰もが稼げる夢のような時代」でした。補助金の採択率は初期には50%以上あり、2回に1回は通るような状況でした。成功報酬は採択額の10~15%が相場で、2,000万円の補助金が通れば、それだけで200万円~300万円の報酬が得られました。
この時代は、下請けの診断士でも年収1,000万円を超えることが可能でした。年間10本の案件をこなせば、それだけで2,000万円以上の売上も夢ではありませんでした。
IT導入補助金も同様に「美味しい」仕事でした。補助額は150万円程度と小さいものの、申請の手間が少なく、量産が可能でした。採択率も高く、毎月のように募集があったため、安定的な収入源となっていました。
この時期に診断士として独立した人の多くは、「診断士は稼げる資格だ」と確信していたでしょう。実際、私の知り合いでも、この時期に独立して初年度から年収1,000万円を超えた診断士が何人もいました。
そして訪れた「冬の時代」
しかし、2024年以降、状況は一変します。補助金バブルの崩壊は、いくつかの要因が重なって起こりました。
予算の大幅削減が最初の打撃でした。事業再構築補助金の予算は、ピーク時の3分の1以下に削減されました。さらに、採択率も大幅に低下し、50%あった採択率は20%以下まで落ち込みました。つまり、5回申請して1回通るかどうかという厳しい状況になったのです。
不正の横行も問題となりました。本来は企業自身が作成すべき事業計画書を、コンサルタントが丸ごと代行する不正が横行しました。中には、実現不可能な計画で補助金を獲得し、結果的に企業を倒産に追い込むケースも出てきました。
IT導入補助金でも不正は深刻でした。ランダム検査で8%もの不正が発覚し、「実質無料でシステムを導入できる」といった誇大広告でクライアントを騙すコンサルタントも現れました。
こうした状況を受けて、審査は格段に厳格化されました。以前のような「とりあえず出せば通る」という甘い審査ではなくなり、本当に実現可能で、企業の成長に寄与する計画でなければ採択されなくなりました。



私も補助金の案件は多少やってますが、審査が厳格化され過ぎて、実務を知らない診断士が、代書屋的に書けるレベルのものではなくなってきています。
補助金バブルは完全に終わりました。これまで補助金で稼いできた診断士の中には、廃業や倒産に追い込まれる人も出ています。大阪の有名コンサル会社『北浜グローバル経営』の倒産は、その象徴的な出来事でした。


私の周りの心ある診断士は、こんな風に良く言ってます。
事業再構築補助金は、誰も幸せにならない最低の補助金だった。診断士を稼がせただけの補助金だったと言われても仕方ない。多くの企業が、実現不可能な事業に手を出し、毎月何百万円もの赤字を垂れ流している。でも、事業をやめれば補助金を返還しなければならない。結果、倒産するまで続けるしかない地獄に陥っている。
独立診断士のリアルな収入モデル
では、現在の独立診断士はどのように収入を得ているのでしょうか?補助金バブルが崩壊した今、診断士たちは新たなビジネスモデルを模索しています。データから見えてきた典型的なビジネスモデルを詳しく解説します。
収入源の多角化が成功の鍵
年収1,000万円を超える診断士は、単一の収入源に依存していません。彼らは複数の収入源を組み合わせることで、リスクを分散し、安定的な高収入を実現しています。
診断協会の調査データによると、各活動の平均年間売上は次のようになっています。
経営診断・助言は平均141万円(中央値97万円)、講演・研修は平均191万円(中央値130万円)、執筆・出版は平均207万円(中央値108万円)となっています。
ここで注目すべきは、すべての活動において平均値が中央値を大きく上回っている点です。これは、一部の非常に高い売上を上げる診断士が平均値を引き上げていることを示しています。つまり、成功している診断士とそうでない診断士の格差が、ここでも表れているのです。
成功している診断士の収益モデルを具体的に見てみましょう。年収1,500万円を実現している診断士の場合、例えば中核業務である経営コンサルティングで800万円、補助金業務で500万円、研修・講演でで200万円みたいな感じです。
このように複数の収入源を持つことで、一つの収入源が減少しても他でカバーできる体制を作っています。これは「ポートフォリオ経営」と呼ばれる考え方で、リスク管理の観点からも重要です。



特に毎月定期的に入ってくる収入を確保するのが、安定して稼ぐコツだと感じています。
プロジェクト型からストック型へのシフト
従来の診断士ビジネスは、補助金申請のような「プロジェクト型」が中心でした。一つの案件が終われば、また新しい案件を探す必要があり、常に営業活動に追われていました。
しかし、最近では「ストック型」のビジネスモデルにシフトする診断士が増えています。これは、顧問契約のような継続的な収入を確保するモデルです。
月額10万円の顧問契約を5社と結べば、それだけで月50万円、年間600万円の安定収入となります。月額15万円なら5社で750万円の収入が得られます。
ストック型ビジネスの利点は、収入の安定性だけではありません。長期的な関係を築くことで、クライアント企業の深い部分まで理解し、より本質的な支援ができるようになります。これは診断士としてのやりがいにもつながります。
企業内診断士という選択肢の現実
「独立はリスクが高い」と考える人にとって、企業内診断士は魅力的な選択肢に見えるかもしれません。確かに、安定した給与を得ながら診断士の知識を活用できるという点では、理想的に思えます。しかし、その実態はどうでしょうか?
メリット:安定した収入基盤と低リスク
企業内診断士の最大のメリットは、安定した収入基盤があることです。本業の給与は平均で年収500万円~800万円程度。これに加えて、企業によっては資格手当が支給されます。月額5,000円~30,000円程度ですが、ないよりはマシでしょう。
また、診断士の知識を本業に活かせる点も魅力です。経営戦略の立案、新規事業の企画、業務改善プロジェクトなど、診断士として学んだ知識が直接役立つ場面は多いです。
社内での評価向上につながることもあります。「中小企業診断士」という肩書きは、特に管理職や経営企画部門では一定の評価を得られます。昇進や異動の際に有利に働くこともあるでしょう。
リスクを取らずに診断士の知識を活用できる点も重要です。独立のリスクを負うことなく、安定した環境で診断士としてのスキルを磨くことができます。
デメリット:活用機会の限界と成長の停滞
しかし、企業内診断士には大きな制約があります。最も深刻なのは副業禁止の問題です。約60%の企業で副業が禁止されており、せっかくの診断士資格を収入に結びつけることができません。
診断士としての実務経験が積めないのも大きな問題です。企業内では、診断士として外部のクライアントを支援する機会はほとんどありません。資格は持っているが実務経験がない「ペーパー診断士」になってしまう危険性があります。
資格維持も意外と大変です。診断士資格は5年ごとに更新が必要で、そのためには実務ポイントを獲得する必要があります。企業内診断士は実務ポイントを稼ぐのが難しく、有料の実務補習を受ける必要が出てきます。
診断士ネットワークから疎外されやすいのも問題です。診断士の研究会や勉強会は平日夜や土日に開催されることが多く、仕事や家庭の都合で参加できないことが多いです。結果として、診断士コミュニティから孤立してしまいがちです。



あと最大のリスクは「AIの台頭」でしょう。
独立して仕事をすると、仕事の仕方は自分の自由に決められます。なので、AIの進化に対応するのも比較的容易です。
一方、会社勤めであれば、使えるAIやどの業務にどれだけAIを使うかの裁量が低くなります。もっと本質的な話をすると、独立した身であれば、AIを使って業務量を80%削減して、余った時間で遊んでいても誰にも怒れられませんが、会社員だとそうはいきません。AIを使って多少の残業程度の業務改善であれば歓迎されますが、AIを使って業務量の80%を削減するようなドラスティックなことを実現することが許される環境ではない企業がほとんどですし、そもそもAIを前提にした組織体制になってないません。
しかし、実態としては、私の業務の80%はAIに置き換わってしまったように、AIは将来的にはホワイトカラーの90%の業務を奪います。企業に所蔵していると、その社会革命の波にモロに飲み込まれてしまうので、そこが企業に所属していることの最大のリスクです。



よく「情報通信革命」なんて言い方をしますが、過去の農業革命、産業革命ともに、既得権を持っている社会階層は散々な目に遭ってきました。情報通信革命の本質は「知識階級という既得権が打破される」ことに他ならないので、知識を売りにしているビジネスは、軒並み苦境に陥るのは避けられません。
企業内から独立への道筋
それでも、企業内診断士から独立を果たし、成功している人もいます。彼らに共通しているのは、計画的な準備をしていることです。
まず、在職中に専門性を確立します。例えば、製造業に勤めているなら製造業コンサルティング、IT企業なら DXコンサルティングなど、本業での経験を活かせる分野を選びます。
次に、副業が可能な環境を作ります。転職して副業可能な企業に移る、社内で副業解禁を働きかける、あるいは有給休暇を使って少しずつ実績を作るなど、様々な方法があります。
人脈構築も重要です。診断士の研究会に参加し、先輩診断士とのつながりを作ります。また、本業での人脈も将来のクライアント候補となる可能性があります。
資金準備も忘れてはいけません。独立後、すぐに収入が安定するわけではありません。最低でも1年分の生活費は準備しておく必要があります。
こうした準備を3~5年かけて行い、十分な準備が整ってから独立する。これが、企業内診断士から独立を成功させる王道パターンです。
年収1000万円を実現する診断士の共通点
データ分析と実態調査から、高収入を実現している診断士には明確な共通点があることが分かりました。彼らはどのようにして成功を掴んだのでしょうか?その秘密を詳しく見ていきましょう。
共通点① 直接契約の獲得力
高収入診断士の最も重要な特徴は、下請けではなく、元請けとして仕事を獲得できることです。
下請けの場合、報酬の約70%を元請けに中抜きされます。20万円の仕事でも、手元に残るのは6万円。これでは年収1,000万円など夢のまた夢です。
では、どうやって直接契約を獲得するのでしょうか?成功している診断士たちは、様々な方法を組み合わせています。
セミナー営業は効果的な方法の一つです。月2回のセミナーを開催すれば、年間で約50社の経営者と直接会うことができます。セミナー後の個別相談から、顧問契約につながることも多いです。
紹介営業も重要です。既存顧客からの紹介率が30%を超える診断士は、安定的に新規顧客を獲得できています。良い仕事をすれば、自然と紹介が生まれる好循環が生まれます。
Web集客やSNS活用も増えています。LinkedInやX(旧Twitter)でのブランディングにより、専門家としての認知度を高め、直接問い合わせを獲得しています。
共通点② 専門領域の確立
「何でもできます」という診断士は、結局何もできないと見なされます。成功している診断士は、「この分野なら誰にも負けない」という専門性を持っています。
特に中小企業専門のコンサルタントや中小企業診断士は、実務能力が大してない人の方が大半です。逆にいうと、例えば創業支援であったり、M&Aであったり、マーケティングであったりといった、「この分野なら誰にも負けない」という領域がある人は、それなりに上手くいってます。
専門性を確立するには時間がかかります。最低でも3年、できれば5年以上、一つの分野に集中して取り組む必要があります。しかし、一度専門性が確立されれば、競合が少なくなり、高単価での受注が可能になります。
共通点③ 営業・マーケティング力
診断士としての知識だけでなく、自分を売り込む力が不可欠です。どんなに優秀な診断士でも、営業力がなければ仕事は取れません。
成功している診断士の営業スタイルを見ると、共通しているのは「価値提供型営業」です。いきなり契約を迫るのではなく、まず相手に価値を提供し、信頼関係を構築してから契約につなげています。
例えば、無料セミナーで有益な情報を提供し、その後の個別相談で具体的な提案を行う。ブログで専門知識を公開し、読者からの問い合わせを待つ。こうした「与える営業」が、結果的に大きなリターンをもたらしています。
また、マーケティングの観点では、「ポジショニング」が重要です。自分がどんな価値を提供できるのか、誰のどんな問題を解決できるのかを明確にし、それを分かりやすく伝える必要があります。
「中小企業の事業承継を成功に導く専門家」「製造業の生産性を2倍にする診断士」「売上を3倍にするWebマーケティングコンサルタント」など、具体的で分かりやすいポジショニングを持つ診断士ほど、成功しています。
AI時代に生き残る診断士の条件
2025年現在、AIの急速な発展により、診断士の仕事も大きく変わろうとしています。ChatGPTをはじめとする生成AIの登場は、診断士業界にも大きな影響を与えています。
AIに代替される業務の現実
すでにAIに代替され始めている業務があります。
財務分析は、AIが最も得意とする分野です。財務諸表を入力すれば、瞬時に財務指標を計算し、問題点を指摘してくれます。人間が1日かけて行っていた分析を、AIは数秒で完了させます。
市場調査もAIの得意分野です。ビッグデータを解析し、市場トレンドや競合分析を行うことができます。人間では処理しきれない膨大なデータも、AIなら簡単に分析できます。
事業計画書の作成も、AIで代替可能になりました。ChatGPTに企業の基本情報と事業アイデアを入力すれば、それらしい事業計画書が出来上がります。補助金申請書も同様で、専用のAIツールが続々と登場しています。
定型的な報告書作成も、AIの方が効率的です。調査結果をまとめ、グラフを作成し、レポートにまとめる作業は、AIの方が速く正確にできます。



診断士に限った話でなく、弁護士、税理士、会計士など知識を売りにしてきた職業のは軒並みAIに代替されるのは間違いないでしょう。すでに、スキルのない士業よりも、現段階でのAIの方が遥かに優秀です。
AIには代替できない価値はあるか?



結論から言うと、知識産業の90%は必要なくなる未来はすぐそこまで来ています。AIが超知性、つまり人間の知能を超えれば、知識の存在価値はほぼなくなります。
しかし、現段階では人間にしかできない価値提供は確実に存在します。私たちができることは、AIに抗うのではなく、AIが描く現実を淡々と受け入れていくしかないという点です。
例えば、ビジョン構築力は、現在のAIには真似できません。企業の未来像を描き、経営者と共に実現への道筋を作る。これは、創造性と共感力が必要な、極めて人間的な仕事です。
経営者の多くは、論理的な分析結果だけでなく、感情的な支えを求めています。「この方向で本当に良いのか」「従業員はついてきてくれるか」といった不安に寄り添い、勇気づけることができるのは人間だけです。
人間関係構築力も重要です。経営者の良き相談相手となり、時には精神的支柱となる。これはAIには不可能です。
実際、成功している診断士の多くは、「経営者の壁打ち相手」としての役割を果たしています。経営者は孤独です。社内では本音を言えないことも多く、利害関係のない第三者である診断士に、本音をぶつけることができます。



特に、ビジネス的に苦境に陥っている企業では、コンサルタントの活躍の機会が多いです。そういう企業では、何のしがらみもなく、ゼロベースで改善計画を建てられる外部の人間の助けが必要です。
実行支援力も人間ならではの価値です。計画を作るだけでなく、それを実行に移すための組織変革をリードする。従業員の抵抗を和らげ、変化を促進する。これには、人間の感情を理解し、動機づけする能力が必要です。
AI活用力が新たな差別化要因に
当面は、AIを使いこなす能力自体が、診断士の新たな差別化要因になっています。
AIツールを使いこなせる診断士は、従来の10倍の生産性を実現しています。例えば、財務分析にAIを活用し、浮いた時間を経営者との対話に充てる。事業計画書の下書きをAIに作らせ、そこに人間ならではの洞察を加える。
AIを恐れるのではなく、AIを優秀な部下として使いこなす。それができる診断士だけが、これからの時代を生き残れるでしょう。



当面は、プログラミングの知識と統計学の知識は、AI時代には差別化要因となります。なので、AI時代にスキルアップを目指すなら、まずはプログラミングと統計学の学習を始めるべきです。
プログラミングスキルを武器にPythonやRを使ってデータ分析を行い、独自の分析ツールを開発する。自分や顧客専用のマーケティングツールを開発する。業務のオートメーション化を推進するためにクラウドでアプリを開発する。これらにより、他の診断士にはできない価値提供が可能になります。
統計学の知識も重要になっています。AIの出力結果を正しく理解し、解釈するには、統計学の基礎知識が不可欠です。「統計検定2級」レベルの知識があれば、AIの分析結果を適切に活用できます。
それでも診断士を目指すあなたへ
ここまで、中小企業診断士の年収について、良い面も悪い面も包み隠さずお伝えしてきました。予備校のパンフレットや成功者の体験談とは、かなり違う印象を持たれたかもしれません。
厳しい現実のまとめ
改めて、厳しい現実をまとめてみましょう。
診断士の40%以上が年収500万円以下という事実。これは、難関資格と言われる中小企業診断士の実態として、衝撃的な数字です。
独立しても7割は下請けに甘んじるという現実。自由に仕事を選び、高収入を得るという独立の理想とは、かけ離れています。
補助金バブルは崩壊し、もう戻らないという事実。かつての「誰でも稼げる時代」は終わり、本当の実力が問われる時代になりました。
AIによって仕事の一部は確実に奪われるという未来。従来型の診断士業務の多くは、AIに代替される可能性があります。
企業内診断士の多くは、資格を活かせていないという実態。副業禁止の壁は厚く、せっかくの資格が宝の持ち腐れになっているケースが多いです。
それでも存在する可能性
しかし、だからといって中小企業診断士という資格に価値がないわけではありません。正しい戦略と努力があれば、年収1,000万円以上も決して不可能ではありません。
実際、全体の26%以上が年収1,000万円を超えているという事実があります。これは、4人に1人以上という決して少なくない割合です。
成功している診断士に共通しているのは、現実を直視し、それに対応する戦略を持っていることです。彼らは、補助金に依存せず、専門性を確立し、営業力を磨き、AIを活用しています。
ここに成功への道筋を示すフローチャートが入る(資格取得→専門性確立→営業力強化→独立成功までの流れ)
成功への現実的なロードマップ
では、これから診断士を目指す人、あるいはすでに診断士資格を持っている人は、どのような戦略を取るべきでしょうか?
第1段階:基礎固め期(1~3年)
まず、企業内診断士として経験を積むことから始めましょう。いきなり独立するのはリスクが高すぎます。
この期間に重要なのは、専門領域を見つけることです。自分の強みは何か、どんな分野で価値提供ができるのかを探ります。本業での経験を活かせる分野が理想的です。
同時に、診断士ネットワークを構築します。研究会に参加し、先輩診断士から学び、仲間を作ります。この人脈は、将来の財産となります。
実務経験も少しずつ積んでいきます。土日を使った副業が可能なら積極的に行い、難しければボランティアでも構いません。重要なのは、実際にクライアントと接する経験を積むことです。
第2段階:実力養成期(1~2年)
基礎が固まったら、本格的に実力を養成する段階に入ります。
副業として本格的に活動を開始します。月1~2件でも良いので、有料の仕事を受注し、実績を作ります。失敗を恐れず、様々な案件にチャレンジしてみましょう。
専門性をさらに深めます。選んだ分野の知識を深め、独自のメソッドやツールを開発します。他の診断士との差別化を図ります。
営業力も磨きます。セミナー開催、ブログ執筆、SNS発信など、自分に合った方法で情報発信を行います。少しずつでも、自分の名前を知ってもらう努力をします。
資金準備も忘れてはいけません。独立に向けて、最低1年分の生活費を貯めます。独立後すぐに収入が安定するわけではないので、余裕を持った資金計画が必要です。
第3段階:独立・成長期(3年~)
十分な準備が整ったら、いよいよ独立です。
最初の1年は苦しいかもしれません。思うように仕事が取れず、収入も不安定でしょう。しかし、ここで諦めてはいけません。
2年目から少しずつ軌道に乗り始めます。リピート客が増え、紹介も生まれ始めます。収入も安定してきます。
3年目以降、本格的な成長期に入ります。専門家としての認知度が高まり、高単価での受注が可能になります。年収1,000万円も現実的な目標となります。
診断士資格の本当の価値
最後に、中小企業診断士という資格の本当の価値について考えてみましょう。
確かに、「資格を取れば稼げる」という単純な話ではありません。しかし、診断士資格には、年収以上の価値があります。
経営を体系的に学べることは大きな価値です。戦略、マーケティング、財務、人事、生産管理など、経営に必要な知識を網羅的に学べる機会は、そう多くありません。
経営者の視点を持てるようになることも重要です。一従業員としてではなく、経営者の立場で物事を考える習慣が身につきます。これは、独立するしないに関わらず、ビジネスパーソンとして大きな武器となります。
人脈が広がることも見逃せません。診断士コミュニティには、様々な業界、職種の人が集まっています。この多様性は、新しい視点や機会をもたらしてくれます。
社会貢献の機会も得られます。中小企業の支援を通じて、日本経済の発展に貢献できる。これは、金銭的な報酬以上のやりがいをもたらしてくれます。
最後に伝えたいこと
中小企業診断士という資格は、「取れば稼げる魔法の資格」ではありません。しかし、正しく活用すれば、あなたのキャリアを大きく変える可能性を秘めています。
大切なのは、現実を直視した上で、それでもなお挑戦する価値があるかを、あなた自身が判断することです。
この記事で紹介したデータや事例は、あくまで現時点での状況です。診断士を取り巻く環境は急速に変化しています。補助金バブルが崩壊したように、新たな機会が生まれる可能性もあります。
もし、この記事を読んでもなお「挑戦したい」と思うなら、あなたには成功する素質があるかもしれません。なぜなら、厳しい現実を知った上で挑戦する人こそが、真の成功を掴むからです。
診断士として成功するかどうかは、資格の有無ではなく、あなたの戦略と努力次第です。正しい方向に努力を重ねれば、必ず道は開けます。
年収1,000万円は、決して不可能な目標ではありません。しかし、それは自動的に与えられるものでもありません。自ら掴み取るものです。
あなたが中小企業診断士として、どのような道を歩むのか。それは、あなた自身が決めることです。
この記事が、その判断の一助となれば幸いです。