「中小企業診断士はやめとけ」と現役診断士が断言する理由

「中小企業診断士になれば年収1000万円も夢じゃない」
「独立すれば自由に稼げる」
「企業から引っ張りだこの人気資格」
こんな甘い言葉に騙されていませんか?
私は2008年から中小企業診断士として活動している現役の診断士です。中小企業診断士のマスターコース事務局も務め、業界の裏側を知り尽くしています。そんな私だからこそ断言できます。
中小企業診断士という資格だけでは、もう稼げません。
予備校や資格学校は決して教えてくれない、診断士業界の残酷な現実。補助金バブルの崩壊、AIによる仕事の消滅、そして業界に蔓延る搾取構造。
この記事では、年収データや業界構造の分析を基に、なぜ今「中小企業診断士はやめとけ」と言わざるを得ないのか、その理由を徹底的に解説します。
それでも診断士を目指したい方のために、最後には生存戦略もお伝えしますが、まずは現実を直視してください。
中小企業診断士の9割は補助金バブル崩壊で年収が激減している
正直、私も、2023年度まではほぼ診断士と関わることがなかったので、そもそも普通の診断士がどうやって稼いでいるのか良く分かりませんでした。
診断士の業界に入って分かったのは、診断士の約9割が、何らかの形で補助金業務に関わっているという事実です。
これは私の肌感覚ですが、診断協会のマスターコース事務局として多くの診断士と接してきた経験から、ほぼ間違いないと確信しています。

逆に、私は2023年くらいから中小企業のサポートが増えてきてますが、補助金関連の業務は何だかんだ降って来るので、中小企業と関わると融資とか補助金の話は付きまとってきます。
なぜこれほどまでに補助金に依存しているのか。それは、補助金ビジネスが「手っ取り早く稼げる」仕組みだったからです。
補助金コンサルティングの収益モデルは単純明快です。着手金10万~15万円を受け取り、採択されれば補助額の10~15%を成功報酬として得る。事業再構築補助金なら平均2000万円の補助額に対して、成功報酬10%でも200万円。これを年5件やれば1000万円です。



あとは、補助金業務は「実務経験がなくてもできる」業務だからというのも大きいです。診断士2次試験の延長に近い内容なので、実務経験がなくても、ある程度財務分析ができれば、ぶっちゃけ補助金の事業計画書は作ることができます。
しかし、その夢のような時代は終わりました。
2021年〜2023年の補助金バブル時代は誰でも年収1000万円が可能だった
2021年から2023年にかけて、まさに「補助金バブル」と呼ばれる時代がありました。
コロナ禍で傷んだ企業を支援するため、政府は総額1兆1485億円という戦後最大規模の事業再構築補助金を投入。採択率は当初50%以上、診断士が書けば70%という驚異的な数字でした。
この時期の診断士の稼ぎ方は、まさに異常でした。
事業再構築補助金の平均補助額は2000万円。成功報酬10%で200万円。年間10件、20件とこなせば、下請けの診断士ですら簡単に年収1000万円を超えていました。
元請けに報酬の7割を抜かれても、です。
IT導入補助金も同様に「美味しい」仕事でした。補助額は150万円程度と小さいものの、労力が少ない上に、毎月のように募集があり採択率も高い。元請け会社によっては、主婦のパートさんにやらせていたくらい簡単な作業でした。
この時期、診断士業界は未曾有の好景気に沸いていました。誰もが「資格を取れば稼げる」と信じて疑いませんでした。



私の周りでは、コロナ期に独立した診断士のほとんどは、補助金関連で独立している人たちです。ちなみに、私は補助金バブルのビッグウェーブには乗り遅れたので、大して美味しい思いはしてません(笑)
事業再構築補助金の予算縮小で下請け診断士の年収は300万円台に転落
しかし、2024年以降、状況は一変しました。
コロナ終息とともに補助金予算は大幅縮小。事業再構築補助金やものづくり補助金、IT導入補助金などの、今まで診断士の稼ぎ頭だった補助金は問題視されました。結果、採択率は大幅に下がり、「診断士が書けば通る」補助金ではなくなりました。
毎年2%の賃上げ義務化、事業計画の実現可能性の厳密な審査、不正防止のためのチェック強化。もはや「やれば儲かる」時代ではありません。
特に深刻なのは、下請け診断士の状況です。
元請けに7割を中抜きされる構造は変わらないまま、案件数だけが激減。かつて年収1000万円を超えていた下請け診断士の多くが、今では年収300万円台、あるいはそれ以下に転落しています。
さらに悲惨なのは、補助金を受けたために倒産する企業が続出していることです。
見通しの甘い事業計画で補助金を受け、毎月数百万円の赤字を垂れ流す。しかし、事業をやめれば補助金を返還しなければならない。結果、倒産まで赤字に耐え続ける「補助金ゾンビ」企業が大量発生しました。
心ある診断士の間では「事業再構築補助金は、誰も幸せにしなかった最悪の補助金だった。診断士を稼がせただけの補助金だった」とまで言われています。
事業再構築補助金の後継として、「新規事業進出補助金」というのが出たりしてますが、事業再構築補助金に比べて膨大な量の申請書類を書く必要があり、補助金ビジネスの時間給は減る一方です。
IT導入補助金の不正発覚で審査が厳格化し案件が激減している
IT導入補助金でも不正が横行しました。
本来、企業がシステム導入費用の一部を自己負担するはずが、IT会社が補助金分をキックバック。企業は実質タダどころか、お小遣いまでもらえる。そんな悪質なスキームが蔓延したのです。
2024年の無作為検査では、なんと8%で不正が発覚。これは氷山の一角でしょう。


結果、IT導入補助金の審査も驚くほど厳しくなりました。2025年度からは、支援事業者登録も厳格化を辿っています。私のような補助金がメインでない診断士にも「登録が通らない」という悲鳴のような相談が多数寄せられています。
また、IT導入補助金の採択率も、50%を切るような状況が続き、簡単には採択されなくなりました。
もはやIT導入補助金も、簡単に稼げる仕事ではなくなりました。
補助金バブルの崩壊により、診断士の9割が頼っていた収入源が消滅。これが、診断士業界の現実なのです。



補助金バブルで補助金をやる診断士が増えすぎて、業界が過当競争になっているという現状もあります。
診断士の年収についての記事はこちら
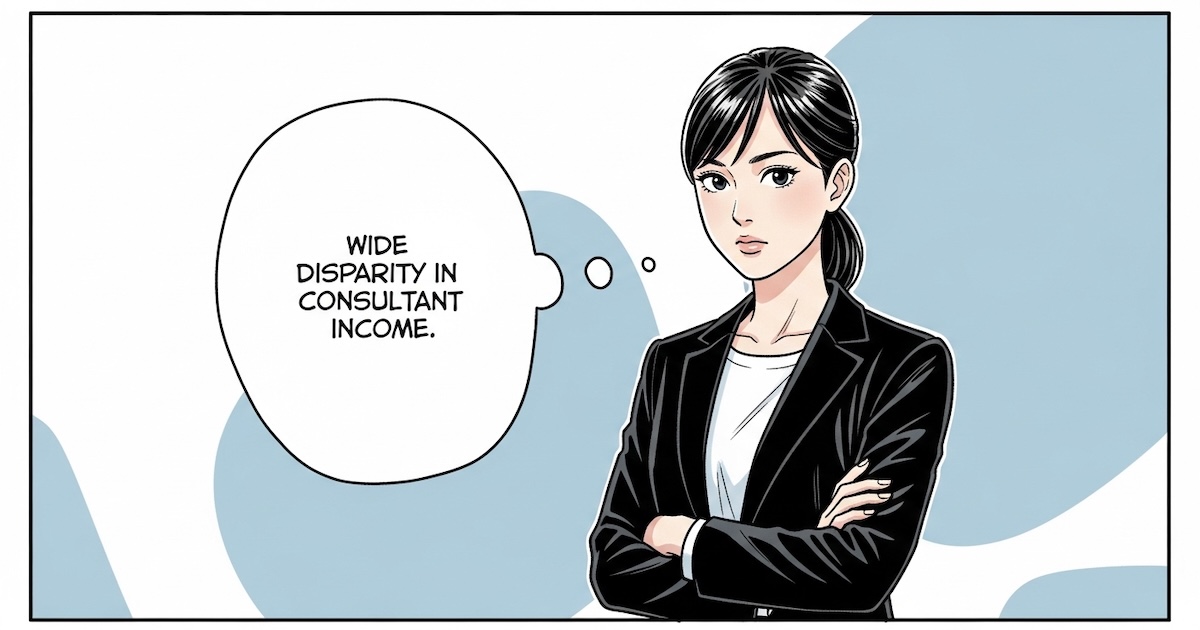
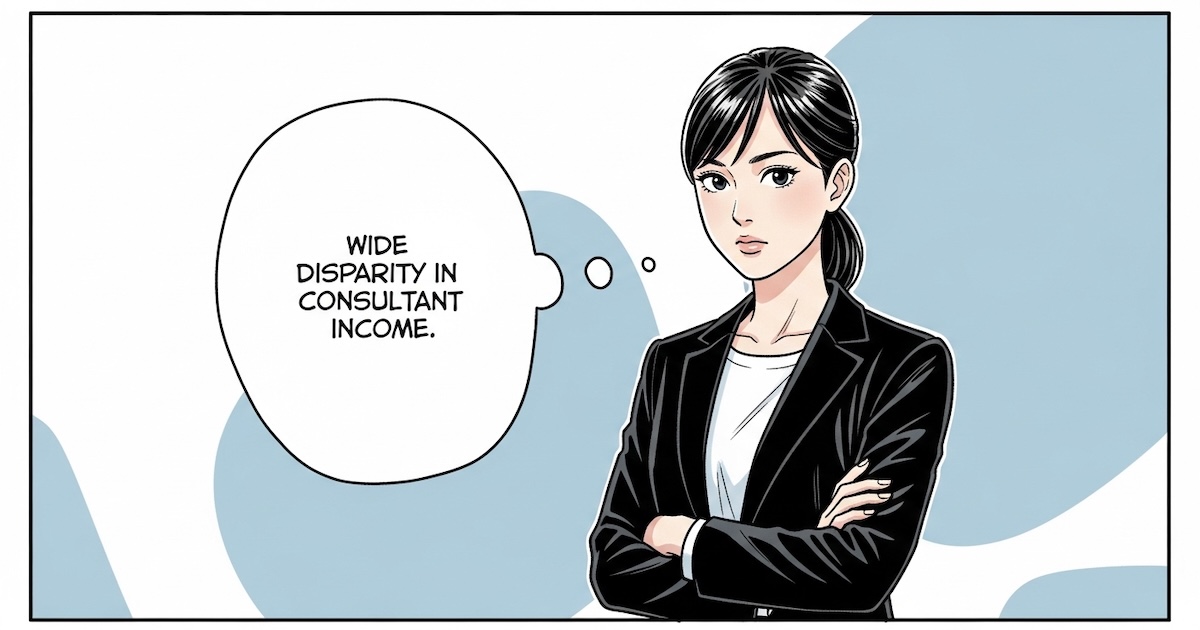
診断士資格の維持だけで年間10万円以上かかる「赤字資格」の実態
中小企業診断士の資格は、取得して終わりではありません。
5年ごとに更新が必要で、その維持コストは想像以上に高額です。
資格更新には、二つの要件を満たす必要があります。それぞれに、お金と時間という大きな犠牲を強いられます。
5年ごとの更新に必要な理論政策更新研修で毎年6万円が消える
まず必要なのが「理論政策更新研修」です。
半日の研修を5年間で5回受講する必要があり、1回あたり約6000円。つまり、5年で3万円、年間にならすと6000円の出費です。
以前は診断協会主催の研修しかなく、内容も驚くほどつまらないものでした。眠くなるような座学を、わざわざ会場まで出向いて受ける。それが義務だったのです。



大塚商会などの理論更新研修はかなりマシですかね。オンライン受講もできるので、期限ギリギリに慌てて更新研修を受ける診断士には大人気です(笑)
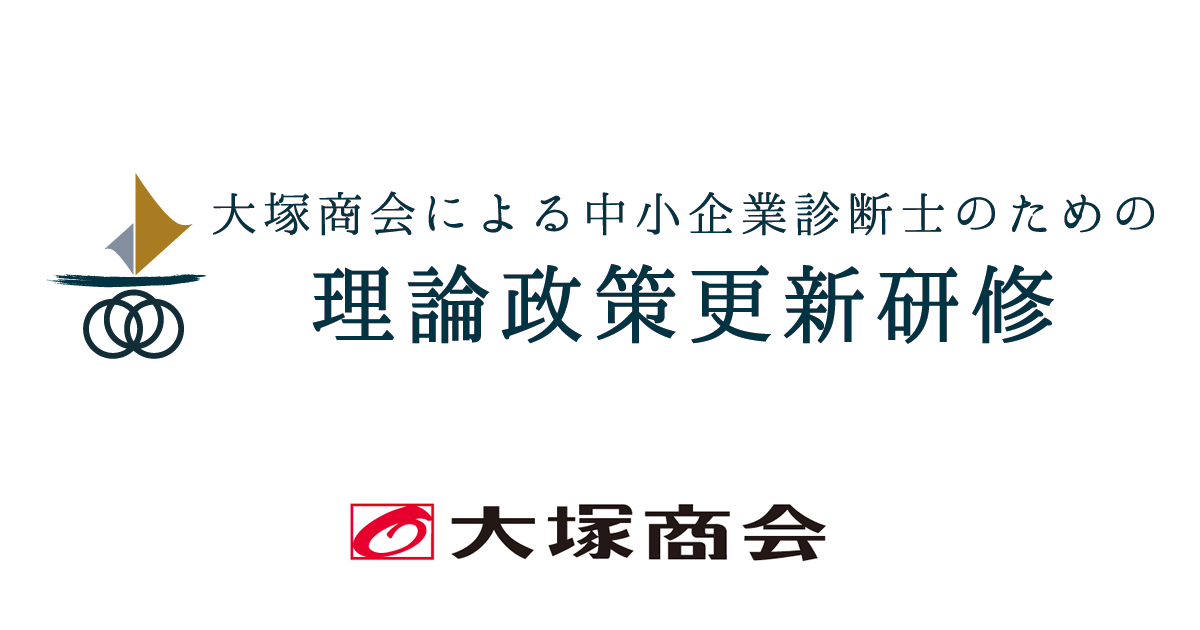
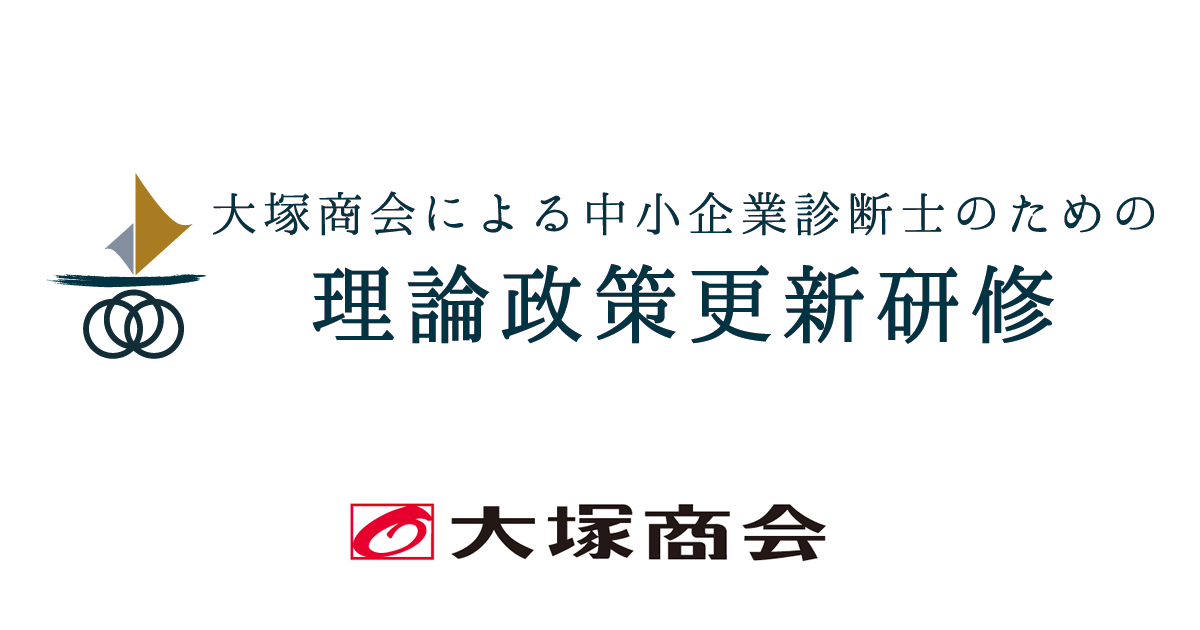
実務ポイント獲得のための研修に有給5日と5万円を費やす構造
更新要件の中で最も理不尽なのが、「実務ポイント」です。
5年間で30日分のコンサルティング実績が必要なのですが、企業内診断士にとって、これは非常に高いハードルです。
会社員として働きながら、30日分ものコンサル実績を作るのは、現実的にほぼ不可能です。
そこで多くの企業内診断士は、診断協会が主催する「実務補習」を受けることになります。
驚くべきことに、この実務補習はお金を払って、無料でコンサルティングをするという、本末転倒な仕組みなのです。
5日間コースで5~6万円。しかも平日開催が多いため、有給休暇を使って参加します。
つまり、自分の有給を潰し、5万円以上を払い、その上で中小企業に無料でコンサルティングを提供する。これが資格維持のために必要なのです。
さらに問題なのは「講師ガチャ」です。
補習の講師は、実力ではなくコネクションで選ばれることが多く、当たり外れが激しい。報告書の言葉遣いといった、どうでもいいことにネチネチと細かい指摘をされ、徹夜作業を強いられることもあります。
時間も有給もお金も取られる上に、精神まですり減らされる。まさに「三重苦」です。



協会の実務補習はとかく評判が悪いですね。中には実力のある診断士が後進の指導のために、利益など顧みないで担当しているケースもありますが、基本そういうのは少ないです。実力ある人は忙しいので、実務補習の講師などやってられないので。
診断協会の年会費と支部会費で毎年5万円が固定費になる
さらに、診断協会の会費も馬鹿になりません。
支部によって値段の前後はありますが、年間約5万円。これは診断士として活動する限り、永遠に払い続けなければなりません。
協会に入らなければ、研修情報も入ってこないし、実務ポイントを稼ぐ機会も限られます。事実上、強制加入のようなものです。
年間の維持費をまとめると:
- 理論政策更新研修:6000円
- 実務補習(5年で割る):6万円以上
- 診断協会会費:5万円
- 有給5日分の機会損失:10万円相当
合計で年間10万円以上、時間的コストも含めれば20万円以上の負担です。
これだけのコストをかけて維持する価値が、今の診断士資格にあるでしょうか?



もう結論から言ってしまうと、「会社員であればそこまでコストをかけるのはあまり意味ない」というのが正直な感想です。自分の企業が中小企業で、そこから実務ポイントを貰えるなどであれば、話は別ですが。
独立診断士の7割が下請け構造で報酬の70%を搾取されている
「独立すれば自由に稼げる」
これは予備校が振りまく、最大の幻想です。
確かに診断協会のアンケートでは、独立診断士が47.8%という数字が出ています。しかし、この数字には大きなカラクリがあります。
私の実感では、現役のビジネスパーソンとして独立している診断士は、全体の1割、多くても2割程度です。
残りの「独立診断士」の多くは、定年退職後に開業届を出しただけの「年金診断士」。年金をもらいながら、お小遣い稼ぎ程度に活動している人たちです。
そして、本当に独立している診断士の中でも、自分で直接クライアントから仕事を取ってくる「元請け」になれているのは、わずか2~3割。
つまり、独立診断士の約7割は、どこかの会社や先輩診断士から仕事をもらって食い繋いでいる下請けなのです。
元請け会社が200万円の案件から140万円を中抜きする業界構造
下請け診断士の現実は、想像以上に過酷です。
業界の相場として、下請け診断士は報酬の約7割を元請けに中抜きされます。
例えば、補助金申請業務で着手金20万円の仕事があったとします。元請けの会社や診断士が14万円を取り、実際に作業する下請け診断士には6万円しか残りません。
成功報酬200万円の案件でも、下請けの取り分は60万円。これが業界の「常識」なのです。
なぜこんな搾取的な構造がまかり通るのか。それは、多くの診断士が自分で仕事を見つけられないからです。
営業力がない、マーケティングができない、そもそもコネクションがない。だから、仕事を持っている人の下請けに甘んじるしかないのです。
さらに酷いのは、この業界には「勉強させてやる」という名目で、ただ働きをさせる風潮が蔓延していることです。
「うちの仕事を手伝えば、ノウハウを教えてあげるよ」
そんな甘い言葉で、実際はただで雑務をやらせる。そんな診断士が、本当に多いのです。



ホント、「勉強させてやるんだから、無料 / 無料に近い金額で診断士をこき使って構わない」という風潮はしょーもないですが、下請けにお金を払うほど稼げている診断士は極小なので、そういう構造になっているんだと思います。
診断協会が「やりがい搾取」を常態化させている驚きの実態
この搾取構造の根源にあるのが、診断協会です。
協会には、様々な研究会が存在しています。
これらの協会活動は、すべて無料奉仕です。
研究会の運営も、講師も、事務局も、すべてボランティアか微々たる謝金。この「無料で当たり前」という感覚が、業界全体に蔓延しています。



とはいえ、診断協会の偉い人は、けっこういい給料もらってるような話は聞きます。
マスターコースという独立支援講座も同様です。講師への謝金は雀の涙。OBには事務局作業を「自主ボランティア」として無料奉仕させているところもあると聞きます。
「勉強になるから」「仲間ができるから」「いずれ仕事につながるから」
そんな言葉で、診断士の善意とやりがいを搾取する。これが診断協会内部の実態です。
結果として、診断士業界全体に「ただ働きが当たり前」という異常な文化が根付いてしまいました。



結果的に、協会活動を一生懸命やっても、友達はできるけど、仕事にはつながらないというのがほとんどです。特に、補助金バブルが終了した今となっては、協会経由で美味しい仕事が貰えるというのは、相当厳しいのではないでしょうか。
公的業務の実質日給換算は2万円くらいの低水準
公的業務も、決して稼げる仕事ではありません。
商工会議所の相談員、中小機構の専門家派遣、自治体の経営相談…。これらの公的業務の日当は、半日で2万2000円程度が相場です。
一見、悪くない金額に見えますが、実態は違います。
往復の移動時間、事前準備、報告書作成。これらを含めれば、丸一日仕事です。時給換算すれば、アルバイト並みの水準です。
しかも、これらの仕事は競争が激しい。たった1人の枠に、何十人もの診断士が殺到します。
なぜなら、みんな仕事に飢えているからです。
採用されるのは、協会活動に熱心で、偉い人とコネクションを持っている人。実力ではなく、人脈で決まる世界です。
支部長とゴルフに行く、協会の無料奉仕活動に精を出す、飲み会には必ず参加する。そんな「政治活動」ができる人だけが、公的業務にありつけるのです。



私は、交流会などの目的のない飲み会とかは大嫌いなので、そういうの頑張っている人は偉いなぁと傍目に見ながら思ってます(笑)
診断士資格では転職も昇進も有利にならない残酷な現実
「中小企業診断士の資格があれば、転職に有利」
これも、よく聞く謳い文句です。しかし、現実は全く違います。
はっきり言って、転職市場において診断士資格の価値はほぼゼロです。
私自身、独立前に2回転職していますが、診断士資格が有利に働いたことは一度もありませんでした。
独占業務がないため弁護士や税理士のような市場価値はゼロ
なぜ診断士資格に価値がないのか。答えは簡単です。
独占業務がないからです。
弁護士には法廷での代理人業務、税理士には税務申告、社労士には労働保険の手続き代行。これらは有資格者にしかできない独占業務です。
しかし、中小企業診断士には、独占業務が一つもありません。
経営コンサルティング?誰でもできます。
補助金申請支援?無資格でも可能です。
経営診断?別に診断士じゃなくても…。
この致命的な弱点が、診断士の市場価値をゼロにしています。
認定支援機関になれる、というメリットはありますが、これも税理士や公認会計士なら同様に取得可能です。
結局、診断士は「あってもなくてもいい資格」なのです。
企業が求めるのは資格ではなく実務経験という転職市場の真実
転職市場で評価されるのは、資格ではなく実務経験です。
「中小企業診断士の資格を持っています」より、「子会社の社長として、売上を2倍にしました」「この分野の営業なら、誰にも負けません」という具体的な実績の方が、はるかに価値があります。
企業の採用担当者も、診断士が何をする資格なのか、よく分かっていません。
「診断士です」と言っても、「ふーん」という反応がほとんど。知名度が低すぎるのです。
実際、私がクライアント企業を訪問しても、「中小企業診断士って何ですか?」と聞かれることがよくあります。それくらい、世間の認知度は低いのです。
大手企業の99%は診断士資格を評価対象にしていない
大手企業の採用要件を見ても、診断士資格を評価している企業はほとんどありません。
MBAなら多少は評価されますが、診断士は「その他の資格」扱いです。
昇進においても同様です。診断士資格を取ったからといって、昇進が早くなることはありません。
むしろ、資格の勉強に時間を費やすより、目の前の仕事で成果を出す方が、よほど昇進につながります。
例外的に、信用金庫や地方銀行では診断士資格が評価されることがあります。これは、補助金申請や事業承継などの付加価値サービスを展開するために、診断士が必要だからです。
しかし、それも全体から見ればごく一部。一般企業において、診断士資格の価値はほぼないと言っていいでしょう。
AIが診断士の仕事の7割を奪い10年後には職業自体が消滅する
補助金バブルの崩壊、搾取構造、市場価値の低さ。
これだけでも十分に深刻ですが、さらに恐ろしい津波が押し寄せています。
それがAIです。
生成AIで事業計画書の8割が自動作成できる時代の到来
私自身、2024年の時点では、AIに置き換わる仕事は1~2割程度だと考えていました。
しかし、たった1年で状況は激変しました。
現在、私の仕事の約7割は、すでにAIに置き換わっています。
補助金の事業計画書作成を例に挙げましょう。
以前なら1週間かかっていた作業が、今では半日で完了します。AIにデータを読み込ませ、的確な指示を出すだけで、膨大な事業計画書がほぼ完成するのです。
マーケティング分析、財務計画、SWOT分析、競合調査…。かつて専門知識が必要だった業務が、AIによって誰でもできる作業になってしまいました。
ChatGPT、Gemini、Claude…。次々と登場する生成AIは、日々進化を続けています。
もはや、知識を武器にする時代は終わったのです。
素人でもAIを使えばプロ診断士と同等の成果物が作れる実例
これは誇張ではありません。実際に検証してみました。
私の事業所で「素人に事業計画書を書かせるプロジェクト」を実施したのです。
高校卒で、事業計画書など一度も書いたことがない人に、AIの使い方だけを教えて書いてもらいました。
結果は衝撃的でした。
手順通りにAIを使えば、素人でも事業計画書の80%は書けてしまったのです。
私だけでなく、他のベテラン診断士が見ても「これ、8割は書けていますね」と評価するレベルでした。
残りの2割は、業界の深い洞察やビジョンの提示など、まだ人間にしかできない部分です。しかし、それも時間の問題でしょう。
AIの進化スピードを考えれば、5年後には9割、10年後には10割がAIで代替可能になるはずです。
知識を売る士業ビジネスモデルの崩壊は避けられない
この現実が意味することは明白です。
知識だけを武器にしている診断士は、10年後には絶滅する。
いや、10年は長すぎるかもしれません。5年後には、多くの診断士が職を失っているでしょう。
すでに私は、弁護士を使う際も、まずAIに契約書のドラフトを作らせています。弁護士のアドバイスを聞いた後も、それをAIに読み込ませて最終回答を作らせます。
税務についても同じです。中途半端な知識しかない税理士より、AIの方がよほど正確で早い。
会計ソフトも進化し、決算や法人税申告も自動化が進んでいます。税理士の仕事の大部分が、近い将来AIに置き換わるでしょう。
診断士も例外ではありません。むしろ、独占業務がない分、真っ先にAIに仕事を奪われる職業です。
経営戦略、マーケティング、財務分析、人事管理…。診断士の試験で学ぶような知識は、すべてAIが人間を凌駕する領域になりつつあります。
知識の価値がゼロになる時代。それが、もうすぐそこまで来ているのです。
それでも診断士を目指すなら民間企業への直接営業で月100万円を狙え
ここまで、診断士の厳しい現実を包み隠さず話してきました。
それでも、あなたが診断士を目指すというなら、生き残るための戦略をお伝えしましょう。
公的業務のコネ競争から脱却し民間定期コンサルで稼ぐ方法
診断士として本気で稼ぎたいなら、狙うべきはたった一つ。
民間企業の定期コンサルティング契約です。
なぜか?答えは簡単。誰もやっていないからです。
私の体感では、純粋な民間コンサルで稼いでいる診断士は、全体の10%以下。もしかしたら5%もいないかもしれません。
多くの診断士は、公的業務に群がります。商工会の相談員、中小機構の専門家派遣…。しかし、これらは競争が激しく、日当も安い。半日で2万円という、時給換算したらアルバイト並みの仕事です。
一方、民間の定期コンサルなら、月額20万円、30万円という契約も可能です。年間契約なら、1社で240万円、360万円。5社獲得すれば、それだけで1000万円を超えます。
しかも、競合がほとんどいません。
なぜ誰もやらないのか?それは、営業が必要だからです。
自分で顧客を開拓し、提案し、信頼関係を築く。この当たり前のビジネス活動ができない診断士が、あまりにも多いのです。
だからこそ、チャンスなのです。
具体的な獲得方法は3つあります。
- 広告(Facebook広告、Google広告など) まず無料相談や無料セミナーで見込み客を集め、そこから有料契約につなげます。とはいえ、クライアント獲得コストはどんなに低くても10万円を切るのは難しいです。なので、ある程度の出費は覚悟する必要があります。
- 飛び込み営業・テレアポ 古典的ですが、効果的です。実際、DMを40件送って電話したら5件契約が取れた、という事例もあります。コンサルティングのような「今すぐ必要じゃない」サービスには、プッシュ型の営業が有効なのです。
- 銀行経由の紹介 銀行は融資先の経営改善を望んでいます。診断士が入ることで、融資の稟議も通りやすくなる。だから、銀行経由の紹介は成約率が高いのです。
1クライアント獲得に必要なコストは、最低でも10万円。通常は10万円から30万円以上です。



なので、「独立したい」「顧問契約が欲しい」という診断士には、私は「1000万円投下する勇気があれば大丈夫ですよ」とお伝えしてます。まぁ正しい方法でやれば、1人で食っていく分には300万円から400万円くらいの投下資金があれば、大丈夫と思いますが。
税理士など士業への不満を持つ中小企業はターゲット市場になる
中小企業の社長の多くは、税理士に強い不満を持っています。
「顧問料を払っているけど、何をしてくれているか分からない」
「前の税理士は良かったのに、代替わりしてから全然ダメ」
「経営のアドバイスなんて、全くしてくれない」
私の肌感覚では、中小企業の8~9割は、今の税理士に何らかの不満を持っています。
実際、多くの税理士は税務のことしか分からず、経営や財務のアドバイスなどできません。月給20万円程度で雇った補助者が実務を回し、税理士自身は判子を押すだけ。それで月額顧問料を取っているのです。
この不満こそが、診断士のチャンスです。
- 「税理士さんとは違う視点で、経営全体をサポートします」
- 「売上アップのための具体的な施策を一緒に考えます」
- 「補助金だけでなく、事業戦略から財務改善まで総合的に支援します」
こんな提案ができれば、税理士への不満を持つ社長は、必ず興味を示します。
ただし、注意点があります。
中小企業の社長にとって、診断士は優先順位の最下位です。税理士、社労士、弁護士の次。いや、そもそも選択肢にすら入っていないことが多い。
だからこそ、認知してもらうための営業活動が不可欠なのです。
診断士として生き残るための3つの必須スキル
最後に、AI時代に診断士として生き残るために、絶対に必要な3つのスキルをお伝えします。
ビジョンを語れない診断士の9割は淘汰される運命にある
1つ目は「ビジョン」です。
- 「今の業界の問題点は何か」
- 「5年後、10年後はどうなるか」
- 「それに対してどう対応すべきか」
このようなビジョンを自分の言葉で語れる診断士は、ほとんどいません。
しかし、これこそが、まだAIには真似できない仕事です。
私は初対面の人には必ずビジョンを語るようにしています。
「この業界に革命を起こしましょう」 「10年後も生き残れる会社にしましょう」 「AIを100%生かした効率的な経営をしましょう」
大げさに聞こえるかもしれませんが、ビジョンに共感してくれるクライアントとだけ仕事ができるようになります。
逆に言えば、自分と合わないクライアントと付き合う必要がないので、心理的にもラクです。
診断士の9割は、目の前の仕事に追われ、ビジョンを持っていません。だからこそ、ビジョンを語れるだけで圧倒的な差別化になるのです。
営業・マーケティング力がなければ仕事はゼロという現実
2つ目は「営業・マーケティング力」です。
現在のAIのテクノロジーでは、クライアントを見つけ、信頼関係を築き、契約を獲得する能力は、まだ人間の領域です。
しかし、診断士の多くは営業を毛嫌いします。
- 「資格があれば仕事が来る」
- 「知識があれば評価される」
- 「勉強もしているから自分は他より優れいている」
もちろん、表立ってそういうことを言う診断士は流石にいません。ただ、マインド的にはどこか「診断士という資格があれば、資格効果で案件が来るかもしれない」と思っている人は多いと感じます。
そんな甘い考えでは、一生稼げません。
飛び込み営業、テレアポ、広告運用、SNSマーケティング、紹介ネットワークの構築…。
泥臭い営業活動ができない診断士は、確実に淘汰されます。
逆に言えば、営業力さえあれば、知識はAIに任せても十分稼げるのです。
AIを使いこなせない診断士は3年以内に廃業に追い込まれる
3つ目は「AI活用スキル」です。
もはやAIを使いこなせない診断士に、未来はありません。



診断士というより、ホワイトカラー一般ですかね。AIの発達により、今まで「知識」とか「経験」とか言われてたものが、90%は意味がないことが明らかになりました。
先ほど「営業はまだAIに代替できない」「ビジョンもまだAIに代替できない」と言いました。
ただ、私は、「いずれ営業をAIに代替できないか?」「ビジョンもAIに代替できないか?」と考えて行動しています。
当然、そこまで視野に入れてる人間と、「AIなんて、、、」と心の奥底で考えている人では、どんどん業務効率化の差が広がる一方です。そして、診断士には「AIなんて、、、」と心の奥底で考えている人がほとんどで、大半の診断士のAI活用のレベルは「お粗末」の一言です。



診断士業界でAIの活用が全く進んでいないのは、診断士は年寄りが多いことも原因の1つかと思います。
AIのパワーを最大限に発揮するには、プログラミングの知識、線形代数の知識、確立統計の知識が必要になります。
なので、基礎的なもので良いので、プログラミングの基礎知識があれば、AIの活用の幅は格段に広がります。Pythonの基礎くらいは学んでおくことをお勧めします。
統計の知識も重要です。統計検定2級レベルの知識があれば、AIがどう動いているか理解でき、より効果的に活用できます。
AIを使いこなせる診断士と、そうでない診断士。その差は、すでに埋めがたいものになっています。



例えばプログラミングの世界だと、2~3年前は100人で開発してた案件が、AIを使いこなすことで5~6人で回せるようになっています。それと同じことが、診断士というか、ホワイトカラー全般に起こります。
まとめ:それでも診断士を目指すなら覚悟を決めよ
ここまで、中小企業診断士の厳しい現実を包み隠さずお伝えしてきました。
- 補助金バブルは崩壊し、9割の診断士が収入源を失った
- 資格維持に年間10万円以上かかる「赤字資格」
- 独立しても7割が下請けで、報酬の7割を搾取される
- 転職市場での価値はほぼゼロ
- AIが仕事の7割を奪い、10年後には職業自体が消滅する可能性
これが、予備校や診断協会が決して教えてくれない、診断士業界の真実です。
それでも、あなたが診断士を目指すというなら、覚悟を決めてください。
資格だけでは稼げません。 知識だけでは生き残れません。 既得権益にすがっても未来はありません。
必要なのは、営業力とビジョンとAI活用スキル。そして何より、行動力です。
診断協会のマスターコースを見ていても、独立できるのは年間10~15人中、せいぜい1~3人。その違いは、知識でも経験でもなく、「行動したかどうか」だけです。
厳しい現実ですが、逆に言えばチャンスでもあります。
9割の診断士が旧態依然とした考えに囚われている今だからこそ、新しい発想と行動力を持つ診断士には、大きなチャンスが広がっているのです。
民間企業への直接営業で月100万円を狙う。 AIを味方につけて生産性を10倍にする。 ビジョンを語り、共感するクライアントとだけ仕事をする。
これができれば、診断士として成功することは、決して不可能ではありません。
ただし、それは「中小企業診断士」という資格の力ではなく、あなた自身の力で勝ち取る成功です。
資格に頼らず、自分の力で道を切り開く覚悟があるなら、診断士という資格は、その第一歩になるかもしれません。
しかし、「資格を取れば安泰」という幻想を抱いているなら、今すぐその考えを捨ててください。
中小企業診断士はやめとけ。
これが、業界の裏側を知る現役診断士としての、私の正直な結論です。
それでもなお、この道を選ぶというなら…
覚悟を決めて、行動あるのみです。
健闘を祈ります。



