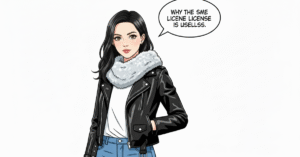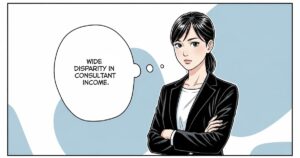中小企業診断士が「意味ない」と言われる本当の理由:予備校が絶対に教えない診断士の実態とは?
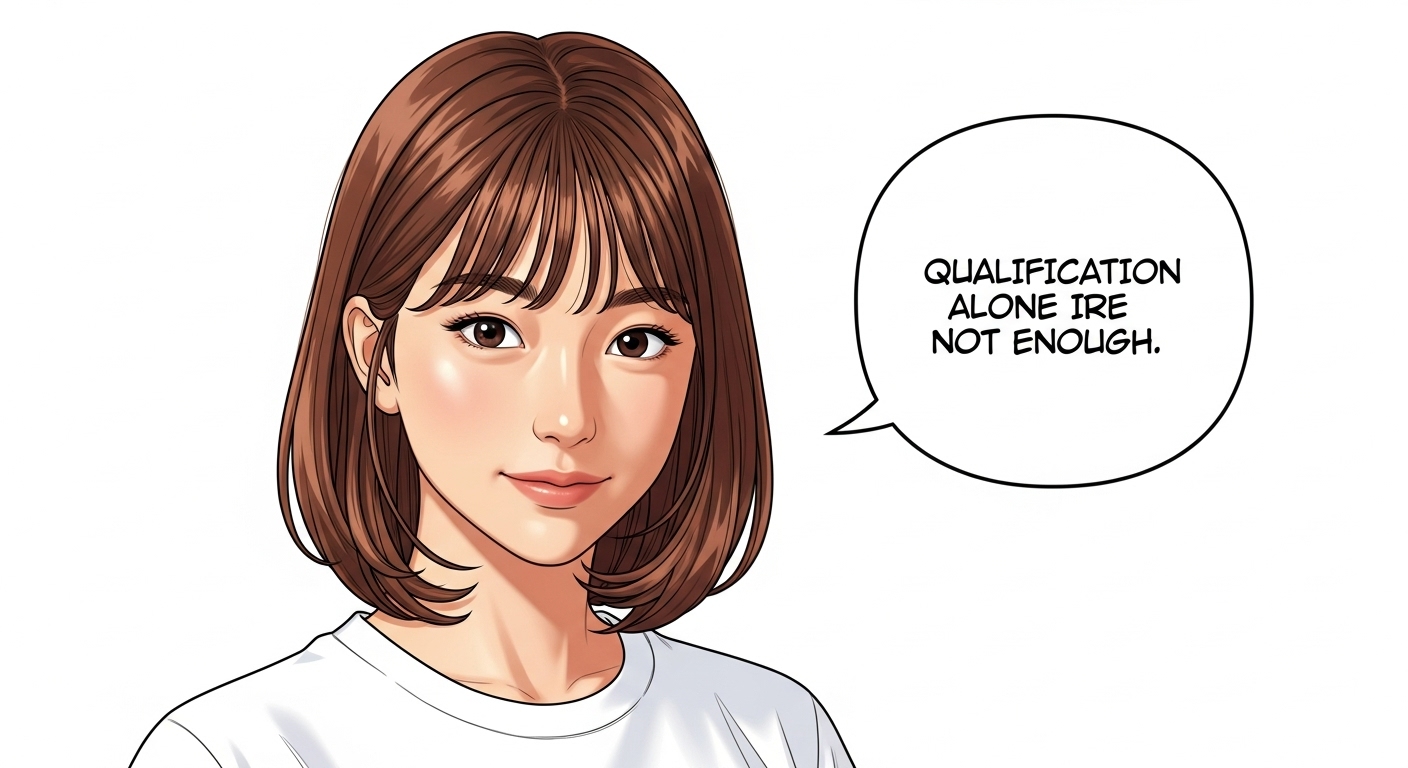
なぜ今、中小企業診断士は「やめとけ」と言われるのか?
あなたは今、中小企業診断士という資格に憧れを抱いているかもしれません。
「経営コンサルタントの唯一の国家資格」「年収1000万円も夢じゃない」「独立開業で自由な働き方を実現」「手に職をつけて安定した人生を」。
こんな甘美な言葉に魅力を感じて、この記事にたどり着いたのではないでしょうか?
しかし、これからお話しする内容は、あなたの期待を完全に裏切るものかもしれません。中小企業診断士の90%は、この資格だけでは食べていけない。これが、業界が隠し続けてきた残酷な現実です。

もともと、中小企業診断士は「食えない」資格の典型と言われてきましたが、この2年くらいで、本当に食えない資格へとなってしまいました。
この記事では、あなたが数百万円の学費と貴重な数年間を無駄にする前に知っておくべき、中小企業診断士の本当の実態を包み隠さずお伝えします。
予備校が仕掛ける「年収1000万円」という甘い罠
多くの予備校サイトを見ると、必ずと言っていいほど目にする文言があります。「中小企業診断士の平均年収は800万円から1200万円」「独立すれば年収2000万円も可能」「企業内でも昇進・昇格に有利」。
これらの数字を見て、あなたは何を感じるでしょうか?「今の年収と同じくらい稼げて独立できるのか!」「これなら勉強する価値がありそうだ」。そう思ったとしても、無理はありません。世の中に、診断士の実態に関する情報はほとんどでてないですからね。



私が診断士の実態について本を書いたときに、周りの診断士に言われたことは「こういう診断業界のホントの部分を書いた情報は全然分からなかった、診断士業界に入って初めて知った」という意見が大半でした。
しかし、年収のデータにはには巧妙なトリックが隠されています。実際の調査データを詳しく見てみましょう。
中小企業診断協会が実施した実態調査によると、診断士として年収500万円以上を得ている人は約28%、年収300万円から500万円が約22%、年収100万円から300万円が約35%、年収100万円未満または収入なしが約15%となっています。つまり、年収500万円以上を得ているのは全体の3割程度。残りの7割は年収500万円以下、そのうち半数は年収300万円以下という厳しい現実があります。
さらに衝撃的な事実があります。この調査で「診断士としての年収」と回答されているもののうち、実に8割以上が「診断士業務以外からの収入」を含んでいるのです。診断士の肩書きを使った講師業、診断士とは関係ない本業の収入、不動産収入や株式投資などの副収入が含まれているのです。



純粋に「中小企業診断士としてのコンサルティング業務」だけで年収500万円以上を得ている人は、私の周りでもほとんど見ませんね。全体として1割以下だと思います。
予備校のホームページには、必ず「合格者の声」や「成功事例」が掲載されています。「診断士資格取得後、年収が200万円アップしました!」「独立3年目で年収1500万円を達成!」「大手企業からヘッドハンティングされました!」
これらの事例は確かに事実でしょう。しかし、重要なのはその背景です。成功している診断士には共通点があります。診断士取得前から豊富な実務経験を持っている、大企業での管理職経験10年以上や特定業界での専門知識と人脈、起業・経営の実体験があることです。また、診断士以外の強力な武器を持っています。公認会計士、税理士などの他資格、ITやマーケティングなどの専門スキル、特定分野での著名度や影響力などです。さらに、資格取得前から収入基盤が確立されています。本業での十分な収入、既存ビジネスの成功、投資収入などの不労所得があるのです。
つまり、彼らが成功したのは診断士資格のおかげではなく、もともと持っていた能力や経験のおかげなのです。診断士資格は、あくまで「箔付け」や「営業ツール」として機能しただけ。資格そのものが成功の要因ではありません。



その箔付も個人的にはあまり意味がないと感じてます。私は、今まで、「中小企業診断士だから仕事を発注した」というのは、1件だけです(笑)。
予備校が発表する「平均年収800万円から1200万円」という数字は、統計学的に見ると非常に問題があります。調査に回答するのは、主に「成功している診断士」です。収入が少ない人や失敗した人は、そもそも調査に回答しません。また、「診断士としての年収」の定義が明確でなく、本業の収入や副業収入も含まれている可能性があります。全国の診断士約3万人のうち、実際に調査に回答しているのは数百人程度で、統計学的な信頼性に疑問があります。さらに、資格取得直後の収入と、10年後の収入を同列に扱っている場合があります。



「こういうアンケートは、大体みんな年収とか盛って書いてるよね」と、診断士業界でよく言われてますね。
下記記事で、中小企業診断士の年収については詳しく解説しています。


中小企業診断士が本当に「意味ない」理由を暴露する



他の国家資格と中小企業診断士の最大の違いは、独占業務の有無です。
弁護士には法廷での代理人業務や法律文書の作成、司法書士には不動産登記や商業登記、税理士には税務申告書の作成や税務代理、社会保険労務士には社会保険手続きや労務相談、建築士には建築設計や工事監理といった明確な独占業務があり、資格を持たない人が行うと法律違反になります。
一方、中小企業診断士の独占業務は一切ありません。経営コンサルティング業務は、診断士でなくても誰でも自由に行えます。実際、大手コンサルティング会社のコンサルタント、元大企業役員、成功した起業家、MBA取得者、公認会計士・税理士、IT専門家、マーケティング専門家などが診断士資格を持たずにコンサルティングを行っています。しかも、これらの人たちの方が診断士より高い報酬を得ているケースがほとんどです。
現在の経営コンサルティング市場で求められているのは、「幅広く浅い知識」ではなく「特定分野での深い専門性」です。ITやDXコンサルタントならプログラミングスキルやシステム設計・開発経験、最新テクノロジーの知識が求められます。財務やM&Aコンサルタントなら公認会計士資格や金融機関での実務経験、企業価値評価の専門知識が必要です。人事・組織コンサルタントなら人事制度設計の実績や組織心理学の知識、労働法の専門知識が要求されます。マーケティングコンサルタントならデジタルマーケティングのスキルや広告運用の実績、データ分析能力が不可欠です。業界特化コンサルタントなら特定業界での長年の経験や業界ネットワーク、規制・商慣習の詳細な知識が求められます。



私は専門がマーケティングなので、やはりマーケティングの案件がほとんどです。とはいえ、中小企業に関与している士業やコンサルタントはお話にならないくらいレベルが低い人の方が圧倒的に多いので(!)、なぜか財務の仕事や人事の仕事なども入ってきますが。
診断士試験で学ぶ内容は、これらの専門性とは程遠い「教科書的な一般論」がほとんどです。実際の企業経営者にとって、「財務分析の一般論を知っている人」よりも「うちの業界の財務改善を具体的に実行できる人」の方がはるかに価値があります。



とはいえ、マーケティングが専門の私の目から見ても、診断士試験の内容は、マーケティングの基本を広く勉強するにはとても良くできている、正直、どのマーケティングの教科書より良くできていると思います。もちろん、それだけでは実務上は使えないというだけで。
中小企業診断士の資格維持にかかる年間費用を詳しく計算してみると、更新研修受講料が年間約5000円、中小企業診断協会年会費が約5万円の必須費用があります。さらに実務補習費用が5年で30万円くらいです。



私は診断協会も辞めてしまったので、更新研修費用の年額5000円しかかかりません。実務補習は、中小企業のコンサル実績があるので、こちらも費用ゼロです。
これは診断士として活動するための「最低限の費用」です。実際に営業活動や能力向上を行うには、さらに多くの費用がかかります。



私は経営コンサルティングで独立したいという診断士には「1000万円くらいかければ独立できますよ」とは伝えています。これは広告や営業にかかる費用です。まぁ実際は300万円から400万円くらいで済むことが多いと思いますが。
経営コンサルティングは「信頼関係」が全てのビジネスです。経営者がコンサルタントに求めるのは、同じような課題を解決した経験、厳しいビジネス環境を生き抜いた実績、失敗と成功を重ねた人生経験です。しかし、多くの診断士受験生は会社員として与えられた仕事をこなしてきただけで、経営判断の責任を負ったことがなく、損益計算書に対する責任を持ったことがありません。



やはり、生なましい修羅場の経験がないと、話す内容も解像度が低いですからね。言われたことだけこなすタイプの人だとちょっと厳しいかな?と思います。
実際の経営者の声として「経営をしたことがない人に、なぜ経営の相談をしなければならないのか?」「理論は知っていても、実際にやったことがないアドバイスは信用できない」「同じお金を払うなら、成功している経営者や実績のあるコンサルタントに相談したい」という反応は当然です。
成功している診断士の多くは、資格取得前から大企業での事業部長・役員経験、起業・経営の成功体験、特定業界での専門的な実務経験10年以上、M&AやIPO、事業再生などの修羅場経験を持っています。診断士資格は、これらの経験に「箔をつける」役割しか果たしていません。



とはいえ、繰り返しになりますが、診断士なんてホント大した箔にはなりません。まぁ営業電話かけたときに電話に出てもらいやすいとか、銀行受けがいいとか、その程度のレベルかと思います。
ChatGPTに代表される生成AIの進歩により、従来の診断士業務の多くが代替可能になっています。経営分析レポートの作成、財務分析、SWOT分析、市場分析、競合分析から、事業計画書の作成支援、事業コンセプトの整理、収支計画の作成、リスク分析、補助金申請書類の作成、申請書の下書き作成、必要書類のチェックリスト、審査ポイントの整理、さらに経営課題の整理・分析、問題の構造化、解決策の提案、優先順位の設定まで、これらの作業はAIを使えば診断士でなくても短時間で高品質なアウトプットを作成できるようになりました。



実際に、僕も補助金の申請書とか、マーケティングのアイデア出しとか、自分ではほぼ書いてないですからね。基本、AIに書かせて微調整するくらいです。その方が正確で早いので。
診断士試験制度の根本的欠陥を見抜く



個人的には、大学校などの講座を受けると2次試験免除ができたことで、診断士の質はかなり下がっていると感じています。
2次試験の事例問題も、実際のコンサルティング業務とは大きく異なります。試験の事例問題では与えられた情報だけで解答し、模範解答が存在し、制限時間内での回答が求められ、一人で解決することが前提となっています。とはいえ、2次試験で書く内容は「コンサルティングのトレーニング」と考えれば、最高の試験内容ではないですが、そこまで批判されるような内容でもないことは事実です。どうしても試験の限界はある中では、ある程度はよく出来ている内容だと思います。
診断士というか、コンサルティング業務は多量のペーパーワークが必要です。しかし、大学の講座に通うことで、2次試験免除の制度ができてしまったおかげで、その基本的なペーパーワークすらこなせない診断士が世の中に大量に出現することになりました。まぁ大学のAO入試の功罪と同じことが起きているという認識で間違いないでしょう。



一応、フォローしておくと、AO入試で入学した人の中にも優秀な人がいるように、大学の講座組の中にも優秀な方はいます。ただ総体的には、2次試験組よりレベルが落ちると感じてます。
また、実際のコンサルティングでは、情報収集から始める必要があり、正解は複数存在する場合が多く、時間をかけて関係者と議論し、チームでの問題解決が基本となります。このため、「診断士にはなったものの、実務は全くできない」診断士が量産されているのです。
診断士試験の合格率約4%という数字は、一見すると「超難関資格」の印象を与えます。しかし、この数字には大きな疑問があります。合格率が低く見える理由として、記念受験者が多数含まれている、十分な準備をしていない受験者が多い、途中で諦めて受験しない人は統計に含まれないという受験者の質的問題があります。また、1次試験と2次試験の両方に合格する必要がある、科目合格制度により本気度の低い受験者も含まれる、実務補習まで完了して初めて登録可能という試験制度の複雑さもあります。さらに、他資格と比較して受験者の学歴・職歴が多様で、真剣に勉強している受験者の割合が不明という母集団の偏りもあります。



弁護士、税理士、会計士と違って、中小企業診断士は基本働きながら取得する人がほとんどな資格なので、真剣度もこれらの資格とはちょっと違うかな、と思います。
診断士試験合格に必要な勉強時間は、一般的に1000時間から1500時間と言われています。この時間を時給換算すると、平均的な会社員の時給2000円で計算して、1200時間×2000円=240万円となります。つまり、診断士試験の勉強には240万円相当の時間価値を投入することになります。



加えて、予備校に行った場合には20~30万円、2次試験免除の大学講座に通うと200万円~300万円くらいかかります。特に大学講座に関しては、中小企業診断士という資格取得のメリットに比べて、明らかにお金がかかりすぎです。
この240万円を他の投資に回した場合の効果を考えてみると、プログラミング学習ならフリーランスで月50万円の可能性があります。株式投資で年利7%なら10年後に470万円になり、不動産投資なら毎月の不労所得創出が期待でき、起業準備なら事業成功時のリターンは無限大です。これらの選択肢と比較して、診断士資格の投資効果は明らかに劣っています。
予備校が隠す診断士業界の「闇」を暴く
中小企業診断士の資格取得市場は、それなりに大きなビジネスです。なので、予備校は手を変え品を変え、皆さんに診断士取得の素晴らしさを吹き込みます。



例えば下記のTACのYoutubeなんかもそうですよね。まぁこの著者の方は、動画内で公的業務や補助金業務はムリゲーと言っており、その通りではありますが(笑)
予備校のマーケティング戦略を分析すると、巧妙な心理テクニックが使われています。まず現状への不満を増幅させるテクニックとして「今の仕事に満足していますか?」「一生平社員でいいのですか?」「AIに仕事を奪われる不安はありませんか?」と問いかけます。次に理想的な未来を提示するテクニックとして「経営者から頼られる存在になれます」「自分のペースで働けます」「やりがいのある仕事に出会えます」と訴えかけます。さらに緊急性を演出するテクニックとして「今始めないと手遅れになります」「来年から試験制度が変わります」「早期申込割引は今月まで」と急かします。
これらのテクニックにより、受講生は冷静な判断ができない状態で契約してしまいます。



そりゃ、独立できます、自由な仕事ができます、年収1000万円可能です、経営コンサルみたいな上から目線の仕事できますとか言われれば、今のキャリアに不安持ってる人なら、業界のホントの情報もあまり落ちてないので、コロっといっちゃいますよね。
診断士資格を取得した後も、継続的にお金を搾取する仕組みが存在します。更新研修ビジネスでは、5年に1度の更新研修が必須、年間の継続研修が事実上必須、専門分野別の特別研修が推奨されています。これらの研修内容は、実用性よりも「時間を埋める」ことが優先されています。本当に価値のある内容であれば、もっと短時間で効率的に学習できるはずです。



理論更新研修も昔はホントに酷かったです。診断士協会しか主催できず、内容がクソつまらく、何の役にも立たないただ眠いだけの研修に1年に半日拘束されるというバツゲームでした。今は民間の更新研修が認められて民間は研修内容を工夫しているのと、オンライン受講が認められるようになったので、大分ラクになりました。
診断士向け情報商材ビジネスも盛んで、診断士になった途端、様々な「スキルアップ商材」の営業を受けるようになります。診断士協会が主催する「中小企業診断士マスターコース」が15万円から20万円ほど、そのほかにもいろいろなスキルアップ系の講座の売り込みを受けるようになります。



とはいえ、協会のマスターコースは良心的な価格設定のところが多いのは事実なので、興味があれば受講しても良いのでは。問題は、「スキルアップ」にかこつけて、受講生にタダ、もしくは薄給で自分の仕事をやらせるとんでもないマスターコースもあるので、見極めが必要です。
登録診断士約2万6000人のうち、実際に診断士として活動している人は1万人程度。さらに、診断士業務で生計を立てている人は3000人程度と推定されます。残りの2万3000人は、資格コレクターとして資格を取ることが目的で活用する気がない人、名刺の箔付けとして本業の営業ツールとして資格名を利用する人、自己満足として「国家資格を持っている」という満足感を得るための人、将来への保険としていつか独立するかもしれないという漠然とした期待を持つ人です。これらの人たちも資格維持費は払い続けているため、診断士協会にとっては「優良顧客」です。



診断協会のお偉いさんの中には、ただいるだけで高給を得ているみたいな人もいると聞きます。まぁ一種の利権になってますね。
多くの診断士が収入源としている「補助金申請支援」にも大きな問題があります。実際の事業改善よりも「補助金が通る申請書」の作成に重点が置かれ、近年大問題となっています。また、申請が通った後の実際の事業実行支援は行わず書類作成のみで終了し、企業が補助金なしでは事業改善できない体質になってしまうという問題もあります。本来の経営改善支援ではなく、単なる「補助金申請代行業」になっているのが実態です。



2020年以降に独立した診断士の大半は補助金業務で独立しています。補助金業務をステップアップに、実際のコンサルティングなどの業務に移行できれば良いのですが、そんな人は見たことないので、「そもそも補助金業務は代行ビジネス専業への地獄の始まりなのでは?」とも最近は思います。
診断士の中には序列があり、補助金業務しかやってない診断士(まぁそれが大半なのですが)は業界内では軽く見られます。僕個人はそういう風潮はおかしいとは思いつつも、補助金コンサルの「補助金さえ通れば良い」という金儲け主義のモラルもへったくれもないマインドもどうかと思うところはあるので、補助金コンサル自体が招いた結果であるとも言えなくもないです。あと、補助金バブルが弾けて、もう新規参入で補助金業務で稼ぐのはほぼ無理です。補助金が結構稼げることが分かったので、診断士の間で過当競争になっていることも大きな原因かと思います。
AI時代に消える診断士の価値



AIは既に平均的な診断士の能力を上回っていることが明らかです。
診断士がAIに勝てない理由として、まず情報処理速度の差があります。AIは膨大な情報を瞬時に処理できますが、人間には限界があります。客観性の面でも、AIは感情や先入観に左右されずデータに基づいた客観的な分析ができますが、人間は主観的になりがちです。最新情報への対応でも、AIは常に最新の情報にアップデートされますが、診断士の知識は古くなりがちです。コスト面では、AIのコストは急速に下がっています。さらに、AIは24時間対応で休まず働けますが、人間には労働時間の制限があります。



今のAIの知能だと、各分野で平均すると、大体経験10年くらいの知識量を持っているという感じでしょうか。それに加えて圧倒的なスピードや情報の網羅性、更新性を考えると、もはや人間が打ち勝つのは不可能です。
診断士業界では「AIにはできない人間らしい価値がある」と主張されますが、本当でしょうか?よく言われる「人間らしい価値」として、経営者との信頼関係構築、複雑な人間関係への対応、創造的なアイデアの提案、実行支援・伴走サポートが挙げられます。しかし、これらの価値を本当に提供できている診断士は、全体のごく一部です。
大多数の診断士は、経営者との信頼関係を築けておらず、人間関係の問題を解決できておらず、創造的なアイデアを出せておらず、実行支援のスキルが不足しています。つまり、「AIにはできない価値」を主張しながら、実際にはその価値を提供できていないのが実態です。



診断士業界はとにかく「ブレスト」を好む傾向がありますが、実務をよく分かってない診断士にブレストさせるよりも、AIに考えさせた方が遥かに優秀なのは間違いないです。僕は業務上、仕方なくブレストに出ることも多いですが「そんなのAIに考えさせろよ」と思うことが良くあります。
それでも診断士を目指すあなたへの最終警告
感情論を排除して、診断士資格の費用対効果を冷静に分析してみましょう。取得にかかる総コストとして、予備校受講料30万円、初回の実務補習費用15万円、勉強時間の機会費用240万円で総計約300万円となります。取得後の年間維持コストが約10万円で、10年間の総投資額は300万円プラス10年×10万円で、で400万円となります。もし、2次試験は大学校へ通うとすると、これに、200万円分のコストが更にかかります。
この600万円の投資に対して、どの程度のリターンが期待できるのでしょうか?現実的なリターン予測として、企業内診断士なら月額資格手当2万円で年間24万円、副業診断士なら年間副収入50万円くらいです。この分析から、診断士資格の投資効率は決して高くないことがわかります。



独立している診断士は収入はまちまちですが、年金診断士と呼ばれる、企業をすでに定年退職 or 早期退職した方を含めるとかなり低いです。60歳以下の現役世代であれば、体感的には、補助金バブルが弾けた今となっては、平均すると年収500万円下回るくらいではないかと。
すべてを否定するわけではありません。以下の条件が揃えば、診断士資格にも価値がある場合があります。既に豊富な実務経験がある人、大企業での管理職経験10年以上や特定業界での深い専門知識、起業・経営の成功体験を持っている人です。また、明確な目的がある人、本業でのキャリアアップツールとして使う、特定分野での差別化要素にする、人脈構築のきっかけにするという明確な目的を持っている人です。さらに、経済的余裕がある人、本業で十分な収入があり、投資失敗しても生活に影響せず、長期的な視点で取り組める人です。そして、現実的な期待値を持っている人、資格だけで人生が変わるとは思っておらず、副業レベルの収入で満足でき、自己啓発の一環として考えている人です。これらの条件を満たす人であれば、診断士資格は「プラスアルファ」の価値を提供する可能性があります。
診断士を目指す動機別に、より効果的な代替手段を提案します。年収アップしたいなら、現在の職場でのスキルアップ、転職活動、副業開始の方が確実です。独立開業したいなら、実務経験の蓄積、特定分野での専門性向上、起業準備に時間を使うべきです。転職を有利にしたいなら、業界特化資格、実績作り、ポートフォリオ充実の方が効果的です。コンサルタントになりたいなら、大手コンサル会社への転職、特定分野での実績作りに注力すべきです。これらの代替手段の方が、多くの場合により確実で効率的な結果をもたらします。



ただ、AIの発展によって、今後、コンサルティングという業界の9割はなくなるでしょう。なので、コンサル会社のビジネス方針にもよりますが、今からコンサル会社に入るのは、よっぽど何かに特化した会社とかでないと、正直オススメできません。
データで見る診断士の「本当の価値」を客観的に評価してみましょう。投資収益率(ROI)の比較として、診断士資格の10年間ROIは47%ですが、株式投資(S&P500)の10年間ROIは200%、不動産投資は10年間ROI150%、起業(成功時)は10年間ROI1000%以上、MBA取得は10年間ROI300%となります。
時間投資効率の比較として、診断士勉強は1200時間で年収プラス24万円ですが、プログラミング学習は400時間で年収プラス200万円、英語学習は600時間で年収プラス100万円、営業スキル向上は300時間で年収プラス150万円となります。これらのデータから、診断士資格は決してコストパフォーマンスの良い投資ではないことがわかります。



結局、独占業務という、いわば利権があまりない士業ですからね。一応、公的業務というアルバイト程度の仕事はあるものの、それにすら大量の診断士が群がっている感じで、需要に対して供給が多すぎます。
この記事を読んでも、それでも診断士を目指したいという人もいるでしょう。そのような方には、以下のことを強くお勧めします。現実的な期待値を設定することです。年収1000万円は期待せず、副業レベルの収入で満足し、長期的な視点で取り組むことです。他の選択肢も並行検討することです。十分な準備期間を設けることです。勉強期間だけでなく合格後の準備も含め、実務経験の蓄積を優先し、人脈作りにも時間を投資することです。家族の理解を得ることです。投資リスクを正直に説明し、失敗した場合の対策も検討し、家計への影響を最小限に抑えることです。



あとは、自学自習など、なるべくコストをかけない方法で診断士を取る感じでしょうか。繰り返しになりますが、診断士の試験内容は、試験の限界はあるものの、基礎能力の確認という意味では良くできてるので。
最後に、診断士以外の「本当に価値のある投資」を提案します。スキル投資として、プログラミング(Python、JavaScript等)、デザイン(Photoshop、Illustrator等)、マーケティング(Google広告、SNS運用等)、ライティング(コピーライティング、SEO等)があります。金融投資として、インデックスファンド投資、不動産投資(REIT含む)、などがあります。事業投資として、副業などを初めても良いでしょう。診断士資格よりもはるかに確実で高いリターンを期待できます。
この記事では、予備校や資格学校が決して語らない中小企業診断士の実態を、データと事実に基づいて詳細に分析しました。結論として言えることは、経済的価値は極めて低く、診断士資格だけで十分な収入を得ている人は全体の5%以下です。投資効率が悪く、同じ時間とお金を他の投資に回した方がはるかに高いリターンが期待できます。将来性に乏しく、AIの進歩により診断士の価値はさらに低下する可能性が高いです。リスクが高く、大きな投資をしても失敗する確率が90%以上です。機会費用が大きく、診断士を目指す時間で、より価値のあるスキルや経験を積めます。
ただし、既に豊富な実務経験がある、経済的余裕が十分にある、現実的な期待値を持っている、自己啓発の一環として考えているという条件を満たす人には価値がある場合もあります。
中小企業診断士が「意味ない」と言われるのは、感情論ではなく事実に基づいた正当な評価です。予備校のポジショントークに惑わされず、あなた自身の人生にとって本当に価値のある選択をしてください。