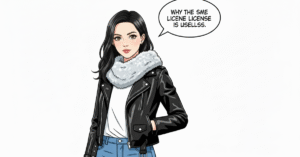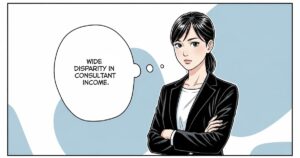【補助金バブルの終焉】なぜ「稼げる仕事」は「稼げない仕事」に変わったのか?誰も語らない祭りの後の現実
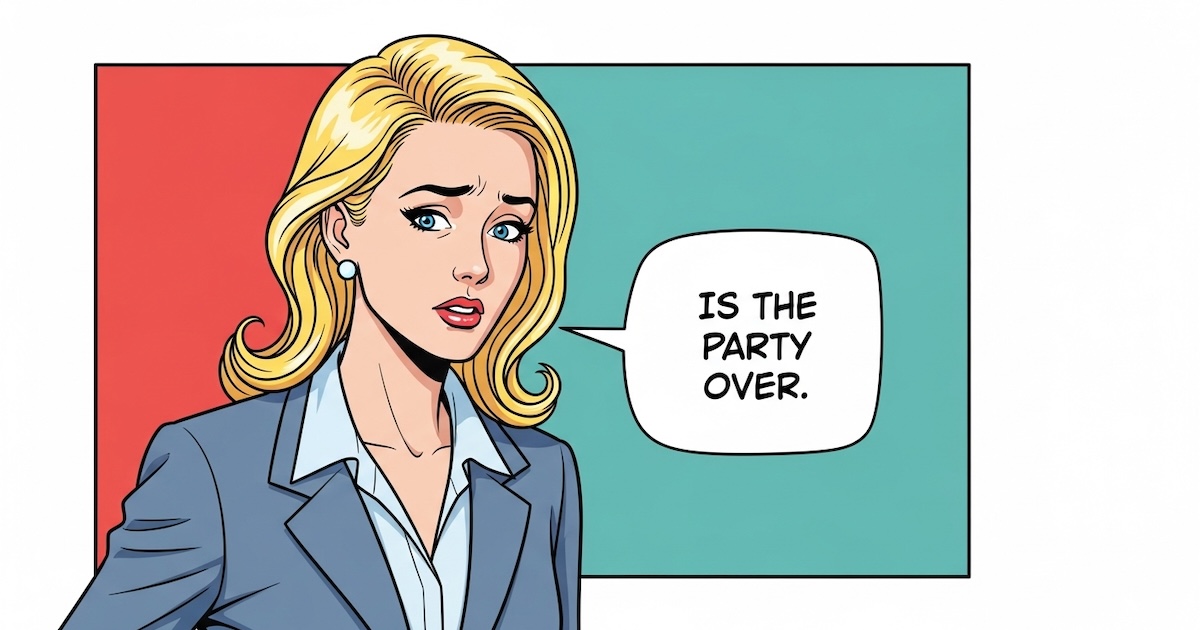
はじめに:あの「診断士の誰もが年収1000万円稼げた」狂乱の時代

こんにちは。中小企業診断士の与田太一です。
ほんの数年前まで、私たち中小企業診断士の世界には、一種の「バブル」が存在していました。それは、経験や営業力に関係なく、誰もが比較的容易に年収1000万円という大台を目指せた、狂乱の時代でした。
その中心にあったのが、国が主導する「補助金」の申請支援業務です。
当時は、まるで地面から石油が湧き出るかのように、仕事と報酬が溢れていました。多くの診断士がその恩恵にあずかり、「診断士は稼げる」という神話を現実のものとしていました。
しかし、その熱狂的な祭りは、あまりにも突然、そして静かに終わりを告げました。
かつての「稼げる仕事」は、今や「稼げない仕事」へとその姿を変え、多くの診断士が路頭に迷っています。一体、あの輝かしい日々から現在までの間に、何が起こったのでしょうか?
この記事では、私が本書『中小企業診断士やめとけ』で最も警鐘を鳴らしたかったテーマの一つである、「補助金バブルの発生から崩壊までの全貌」と、誰も語りたがらない「祭りの後の厳しい現実」について、私の経験と分析のすべてをお話ししたいと思います。
第一章:補助金バブルとは何だったのか?「濡れ手で粟」のメカニズム
すべての始まりは「事業再構築補助金」だった



補助金バブルの引き金となったのは、2021年に始まった「事業再構築補助金」です。これは、コロナ禍で打撃を受けた企業を支援するための、総予算1兆1485億円という戦後最大規模の補助金事業でした。
この補助金の凄まじさは、その採択率にありました。
「当時は採択率が50%以上もあってね。僕ら診断士が事業計画書を書けば、70%くらいの確率で採択されていた。まさに、やればやるだけ儲かる、という狂った時代だったんだ」
応募すれば2回に1回は通るという状況で、市場には仕事が溢れかえりました。
下請けでも年収1000万円が可能だった収益モデル
なぜ、これほどまでに稼げたのか。その理由は、補助金ビジネスの収益モデルにあります。
一般的に、補助金の申請支援は、着手金に加え、採択された補助金額の10%~15%を成功報酬として受け取る形が主流です。
事業再構築補助金は、平均的な補助額が2000万円ほどでした。仮に成功報酬を10%としても、1件採択されれば200万円の報酬になります。
「5件やれば、それだけで1000万円だ。この時期は、下請けでやっている診断士ですら、年収1000万円を軽く超える人が続出した。元請けに報酬の7割を抜かれても、だ。それくらい、異常なバブルだったんだよ」
この時代は、特別なスキルがなくても、ただ黙々と数をこなすだけで、誰もが成功と高収入を手にすることができたのです。
もう一つの収益源「IT導入補助金」
事業再構築補助金やものづくり補助金と並んで、もう一つ忘れてはならないのが「IT導入補助金」です。
こちらは補助額こそ100万円単位と小規模ですが、申請の労力が圧倒的に少なく、会社によっては主婦のパートさんが作業を担当していたほど簡単なものでした。
「おまけに、IT導入補助金のすごいところは、ほぼ毎月募集があったこと。他の補助金が年に数回なのに対して、これは毎月仕事になる」
この回転率の高さから、補助金コンサル会社は、このIT導入補助金だけで年間売上の半分近くを稼いでいるところが多いと思います。
第二章:祭りの終わり。バブルはなぜ、そして、どのように崩壊したのか
しかし、その夢のような時代は、永遠には続きませんでした。コロナが終息に向かうにつれて状況は一変し、バブルは壮絶な形で崩壊します。
私が本書で指摘している、その主な理由は3つです。
「一つは、コロナが終わったことによる予算の縮小。二つ目は、儲かる話に群がった診断士が増えすぎたことによる競争の激化。そして三つ目が、最も深刻な審査の厳格化と不正問題だ」
理由①:予算縮小と競争激化
最も直接的な原因は、コロナ禍の終焉に伴う国の予算縮小です。かつてのような巨大な予算が組まれなくなり、補助金案件そのものが減少。そこに、儲かる話に群がった多くの診断士がなだれ込んだため、競争は異常なほど激化しました。 17
理由②:深刻な「不正問題」の蔓延



そして、バブル崩壊を決定的にしたのが、業界に蔓延した深刻な「不正」です。
- 事業再構築補助金での不正
コンサルタントが本来企業が作成すべき事業計画の作成や申請そのものを代行するという不正が横行しました。
当時の審査は非常に甘く、飲食店がいきなりサウナ事業を始めるといった、どう見ても見通しの甘いずさんな計画でも採択されていました。 - IT導入補助金での不正
さらに悪質だったのが、IT導入補助金で横行したキックバックです。例えば、300万円のシステムを導入する際に150万円の補助金が出るとします。
本来、企業は残りの150万円を自己負担しなければなりません。ところが、IT会社が企業に裏で150万円以上のお金をキックバックすることで、企業は実質タダでシステムを手に入れるどころか、お小遣いまで貰える。そんな不正スキームが蔓延したのです。
2024年の調査では、無作為検査のわずか8%で不正が発覚しましたが、これは氷山の一角に過ぎません。
当然、国もこの事態を黙って見過ごすはずがなく、補助金の審査は、現在、驚くほど厳格化されています。
バブルが残した悲劇:「補助金ゾンビ」の大量発生
バブル崩壊は、診断士の収入を激減させただけではありません。より深刻なのは、安易に補助金に手を出したがために、逆に経営の泥沼に陥ってしまった企業の存在です。
補助金は、受給した事業を3年から5年間は継続する義務があります。 そのため、見通しの甘い事業計画で補助金を受給してしまった企業は、たとえ事業が赤字を垂れ流していても、途中でやめることができません。 やめれば、数千万円の補助金を返還しなければならないからです。
「結果として、事業再構築補助金を受けたがために倒産したり、毎月数百万円の赤字を垂れ流し続ける『補助金ゾンビ』のような事業者が、大量に生まれてしまった。これが、補助金バブルの悲しい結末なんだ」
良心的な診断士の間では、「事業再構築補助金は、史上最低最悪の補助金だった。誰も幸せにならず、診断士を儲けさせただけだった」とまで言われています。
これが、祭りの後の、誰も語りたがらない厳しい現実なのです。
第三章:祭りの後。「稼げる仕事」が「稼げない仕事」に変わった今
割に合わなくなった収益構造
バブル期には、どの規模の補助金でも事業計画書作成の手間はさほど変わらなかったため、補助額の大きい大型案件を手掛けるほど、労力に対するリターンは大きくなりました。
しかし、現在では要件そのものが厳格化しています。 例えば、昔のものづくり補助金は、数年で合計2%の賃上げをすればよかったものが、今では毎年2%の賃上げが義務付けられるなど、クリアすべきハードルは年々高くなっています。 手間が増え、採択率が下がったことで、かつてのような費用対効果はもはや望めません。



他にも、事業再構築補助金の後継である新事業進出補助金はとても厳格になっています。まず、必要な記入事項の分量も多いのですが、「任意提出資料」が山のようにあります。
(私は、任意提出資料だけで、Wordで90ページ分作成しました。)
IT導入補助金も、かなり厳格化されており、少しでも矛盾があると通らないようになっています。
崩壊寸前の下請け・元請け構造
さらに、バブル崩壊は業界の「下請け・元請け構造」にも深刻なダメージを与えました。
元請けの会社が営業だけを行い、中身をろくに確認もせず下請けに丸投げした結果、そもそも補助金の対象外である案件でトラブルになるケースが頻発しています。
また、成功報酬が欲しいがために、実現不可能な計画や数値を並べた「盛りすぎた事業計画書」を作成する「作文コンサル」も後を絶ちません。こうした計画は、たとえ採択されたとしても、その後の事業実行や実績報告の段階で破綻し、最終的に顧客を地獄に突き落とすことになります。
「結局、この補助金ビジネスの問題点は、顧客に価値を提供するという構造になっていないことだ。全てが丸投げで、誰も責任を取ろうとしない、無責任な体制なんだよ」
このように、かつて「稼げる仕事」の代名詞だった補助金業務は、その収益性、将来性、そして倫理性のすべてにおいて、もはや以前と同じ魅力を持つ仕事ではなくなってしまったのです。
下記記事で、中小企業診断士の年収については詳しく解説しています。


では、どうすればこの荒野で生き残れるのか?
補助金バブルという祭りは、終わりました。
かつての成功体験に固執し、同じやり方を続けていては、時代の変化に取り残され、淘汰されることは避けられません。
では、どうすればいいのか?
本書『中小企業診断士やめとけ』は、単に過去を嘆き、現実を告発するだけの本ではありません。このバブル崩壊後の荒野で、あなたが真のプロとして生き残り、そして稼いでいくための具体的な「サバイバル戦略」を提示するために書かれました。
- 今すぐ「脱下請け」を目指すための具体的なアクション
- 「会社」ではなく「個人」で戦うことの重要性とその戦術
- メーカーやIT会社と連携し、継続的な仕事を生み出す仕組み作り
補助金に頼らず、自らの専門性と営業力で、いかにして新たな価値と収益源を創造していくか。
祭りの後の静寂の中で、本当に価値あるキャリアを築きたいと願うすべての方へ。ぜひ本書を手に取り、次の一歩を踏み出すための羅針盤としてください。