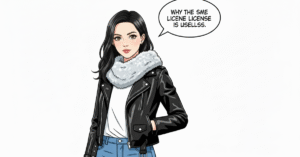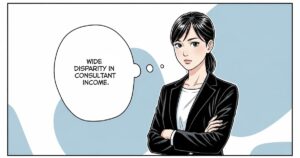中小企業診断士で「食えない」人は9割くらいいる


こんにちは。中小企業診断士の与田です。私の周りでもキチン食えている中小企業診断士はマレなので、本日はその話をしていきたいと思います。
あなたは今、中小企業診断士の資格取得を検討していますか?それとも、すでに資格を持っているけれど、思うように稼げていないと悩んでいますか?
もし、どちらかに当てはまるなら、この記事はあなたのために書きました。
私は長年、中小企業診断士の世界を見てきましたが、その実態は予備校や資格学校が描く「バラ色の未来」とは大きくかけ離れています。今日は、業界のタブーとも言える「本当の話」をお伝えします。
衝撃的な診断士の年収データが物語る現実
まず、中小企業診断士の年収について、衝撃的なデータをお見せしましょう。日本中小企業診断士協会連合会が公表している調査結果によると、診断士の年収分布は次のようになっています。
100万円未満が全体の約15%、100万円から300万円未満が約20%、300万円から500万円未満が約25%となっています。つまり、年収500万円未満の診断士が全体の約60%を占めているのです。
さらに驚くべきことに、年収1000万円以上の診断士は全体のわずか15%程度に過ぎません。これが「経営コンサルタントの国家資格」と呼ばれる中小企業診断士の現実なのです。
予備校のパンフレットには「年収1000万円も夢じゃない!」「独立開業で高収入!」といった華やかなキャッチコピーが踊っています。しかし、実際には多くの診断士が「食えない」状態に陥っているのです。
この数字をもう少し深く見てみましょう。年収300万円未満の診断士が全体の35%もいるということは、月収にすると25万円未満で生活している診断士が3人に1人以上いるということです。これでは家族を養うことも難しく、まさに「食えない」状態と言えるでしょう。
一方で、年収1500万円以上の診断士はわずか5%程度しかいません。つまり、20人に1人しか、いわゆる「成功した診断士」と呼べる収入を得ていないのです。これが診断士の世界の厳しい現実なのです。



これには大きな理由があって、診断士業界は独立している人の多くは「年金診断士」と言って、企業を定年退職、あるいは早期退職している人が多数を占めています。平たくいうと、「定年後のセカンドキャリア」としてコンサルティングをしたいと夢見ている人がかなりの割合を占めており、コンサルティングの実務もあまりできず、そこまで積極的に仕事を取りに行く訳でもない層というのが存在していることは、覚えておいて良いでしょう。
下記記事で、中小企業診断士の年収については詳しく解説しています。


なぜ予備校は真実を語らないのか
ここで疑問が湧きます。なぜ予備校や資格学校は、こうした厳しい現実を受講生に伝えないのでしょうか。
答えは簡単です。それが彼らのビジネスモデルだからです。
予備校にとって、受講生は「お客様」です。お客様に夢を売ることで、高額な受講料を払ってもらう。これが彼らの収益構造なのです。もし「診断士になっても9割は食えません」と正直に伝えたら、誰が25万円から40万円もの受講料を払うでしょうか。
だから彼らは成功事例ばかりを前面に押し出します。「○○さんは診断士になって年収が2倍になりました!」「独立して月収100万円を達成!」といった、ごく一部の成功者の話ばかりを紹介するのです。
これは典型的な「生存者バイアス」です。失敗した人、食えなくなった人の話は決して表に出てきません。なぜなら、そうした人たちは既に診断士の世界から去っているか、ひっそりと別の仕事で生計を立てているからです。



体感的には、廃業する診断士や事実上廃業状態の診断士も数多く存在します。特に2024年の補助金バブルの崩壊で、多くの診断士が食えなくなりました。
予備校の営業担当者も、この現実を知っているはずです。しかし、彼らも生活がかかっています。受講生を集めなければ、自分たちの給料も出ません。だから、良心の呵責を感じながらも、甘い夢を売り続けるのです。
さらに言えば、予備校の講師陣の多くも、実は診断士として成功していない人たちです。もし本当に診断士として稼げているなら、なぜ予備校で講師をしているのでしょうか。時給換算すれば、決して高くない講師料のために、貴重な時間を使っているのです。これも、診断士の厳しい現実を物語っています。
資格取得にかかる時間とコストの真実



中小企業診断士になるためには、膨大な時間とコストがかかります。
まず時間について。一般的に合格に必要な勉強時間は約1000時間と言われています。1次試験に800時間、2次試験に200時間。これを1年で達成しようとすれば、平日2時間、週末5時間の勉強が必要になります。仕事をしながらこのペースを維持するのは、並大抵のことではありません。
しかも、これは「最短」での話です。実際には、1次試験に2年、3年かかる人も珍しくありません。2次試験に至っては、5回、6回と挑戦してようやく合格する人もいます。そうなると、勉強時間は2000時間、3000時間と膨れ上がっていきます。
この時間を時給換算してみましょう。仮に時給2000円の仕事ができる人が、1000時間を勉強に費やしたとすると、機会損失は200万円です。これに加えて、実際の受講料や教材費がかかるのです。
費用面では、独学でも5万円から10万円、通信講座なら10万円から25万円、通学講座なら25万円から40万円かかります。さらに2次試験合格後の実務補習に18万円から21万円。トータルで見れば、最低でも23万円、場合によっては60万円以上の出費になります。
養成課程を選択すれば、2次試験は免除されますが、その代わりに200万円から300万円という莫大な費用がかかります。これだけの投資をして、年収500万円未満になる可能性が60%もあるのです。投資対効果として、これほど割に合わない話があるでしょうか。
さらに見落としがちなのが、受験期間中の「見えないコスト」です。家族との時間、友人との交流、趣味の時間、これらすべてを犠牲にして勉強に打ち込むことになります。



僕の場合は、自習で診断士を取ったので、帰りの電車の中や土日の片方でちょろちょろ勉強するくらい、300時間前後の勉強量で、お金も本屋で買ったテキスト代と模擬試験1回、本番の試験代くらいしかかかりませんでした。とはいえ、これは多分稀なケースなので、一般的にはそれなりに時間や費用などコストがそれなりにかかる資格だと思います。
資格を維持するだけでも費用がかかり続ける



さらに問題なのは、診断士の資格は取得して終わりではないということです。5年ごとの更新制で、資格を維持するためには継続的な費用と時間が必要になります。
理論政策更新研修を5年間で5回受講する必要があり、これだけで約25,000円かかります。しかし、これは最低限の話です。実際には、知識をアップデートするために、さまざまな研修やセミナーに参加することになります。



とはいえ、近年は大塚商会などの民間の参入によって、民間のセミナーに関してはかなり内容はマシになりました。まぁ1年に半日くらいの研修で、オンライン研修も解禁されたので、それくらいならいいかな?とは感じてます。
さらに実務要件として、5年間で30日以上の診断実務に従事しなければなりません。もし中小企業の実務の機会がなければ、実務従事サービスを利用することになり、これに約30万円かかることもあります。
ここで注意すべきは、この実務従事サービスの質です。形式的に実務要件を満たすだけのサービスも多く、実際のスキルアップにはつながらないことがほとんどです。つまり、資格維持のためだけに30万円を支払うことになるのです。



これは実務従事の担当講師次第ですかね。ある程度役に立つ講師もいるようですが、私が聞いている限りは概ね評判は悪いです。「後進の指導のため」と情熱を持ったしっかりしたコンサルタントが採算度外視で担当するケースもありますが、コンサル経験も希薄な年金診断士なども多く、そういう方に当たると「昔の栄光」を持ち出して、受講生に余計なことをさせて、時間もお金も使って大変な目に遭うこともあるようです。
診断士協会に入会すれば、入会金3万円から5万円、年会費5万円から6万円が必要です。5年間で約30万円の出費になります。協会主催のマスターコースなどを受講すれば、さらに年間20万円前後かかります。
また、診断士として活動するためには、名刺、ホームページ、各種ツールなども必要になります。これらの初期投資と維持費用も馬鹿になりません。プロフェッショナルとして活動するなら、年間20万円から30万円程度は見込んでおく必要があるでしょう。
つまり、診断士として活動を続けるだけで、5年間で数十万円から100万円近い維持費がかかるのです。年収500万円未満の診断士にとって、この維持費は決して軽い負担ではありません。



診断士の維持費については、下記にもまとめているので、ご参考ください。


診断士が「食えない」本当の理由
では、なぜ多くの診断士が「食えない」のでしょうか。その理由を深く掘り下げてみましょう。
第一に、診断士の資格自体に仕事を生み出す力がないことです。医師や弁護士のような業務独占資格ではないため、資格を持っているだけでは仕事は来ません。名称独占資格に過ぎないのです。
つまり、「中小企業診断士」と名乗ることはできても、診断士でなければできない仕事というものは存在しないのです。経営コンサルティングは、誰でもできる仕事なのです。
第二に、コンサルティング市場の競争が激化していることです。大手コンサルティングファームから独立系コンサルタントまで、プレイヤーは無数に存在します。その中で、経験も実績も乏しい新人診断士が徒手空拳で仕事を獲得するのは至難の業です。
特に最近は、元大手企業の管理職や、MBAホルダーなど、診断士資格を持たない優秀なコンサルタントが増えています。彼らは実務経験が豊富で、人脈も持っています。診断士資格だけが武器の新人診断士では、到底太刀打ちできません。
第三に、中小企業の多くがコンサルティングに対価を払う余裕がないことです。日本の中小企業の約7割が赤字経営と言われる中、高額なコンサルティングフィーを支払える企業は限られています。
仮に黒字企業であっても、目に見えない「コンサルティング」というサービスにお金を払うことに抵抗感を持つ経営者は多いです。「そんなお金があるなら、設備投資や人材採用に使いたい」というのが本音でしょう。
第四に、診断士の多くが営業力を持っていないことです。試験勉強で身につくのは知識であって、営業スキルではありません。いくら優秀な診断能力があっても、それを売り込む力がなければ仕事にはならないのです。



診断士に限った話ではないですが、「資格を持ってればそこそこお客さんは集められる」「良いサービスを提供すれば、自然と顧客は集まる」と考えています。しかし、現実はそう甘くありません。積極的に営業活動を行い、自分を売り込まなければ、誰もあなたの存在すら知らないのです。
第五に、診断士サービスの成果が見えにくいことです。コンサルティングの成果は、すぐには表れません。また、成功した場合でも、それがコンサルティングの成果なのか、経営者の努力の結果なのか、判断が難しいのです。
このため、クライアントは継続的にコンサルティングフィーを支払うことに躊躇します。「本当に効果があるのか分からないものに、毎月何十万円も払えない」というのが、多くの中小企業経営者の本音なのです。
独立開業の厳しい現実
「会社勤めでは稼げないなら、独立すればいい」と考える人もいるでしょう。しかし、独立開業の道はさらに険しいものです。
独立診断士の多くは、最初の1年間はほとんど収入がありません。人脈もなく、実績もない状態でスタートするため、仕事を獲得すること自体が困難なのです。貯金を切り崩しながら、必死に営業活動を続ける日々が続きます。
運良く仕事を獲得できても、単価は驚くほど低いことが多いです。中小企業の経営相談で、1日3万円から5万円程度が相場です。月に10日働いても、売上は30万円から50万円。ここから経費を差し引けば、手元に残るのはわずかです。
しかも、この単価を上げることは容易ではありません。「診断士なんて掃いて捨てるほどいる」という認識を持つ経営者も多く、「もっと安くやってくれる診断士を探す」と言われることもしばしばです。
さらに、仕事は安定しません。今月は忙しくても、来月の仕事があるかどうかは分かりません。この不安定さに耐えられず、多くの独立診断士が数年で廃業してしまうのです。



令和での診断士が稼げるゴールデンパターンとしては、まずは公的業務などの簡単な業務と、補助金のようなある程度稼げる業務を下請けで受ける業務を組み合わせて、ある程度食い繋ぐことができました。ただ、補助金バブルが崩壊したことと、市場に診断士が溢れかえってしまったので、どちらも仕事を取るのが難しい、レッドオーシャンなビジネスとなりました。
企業内診断士という選択肢の限界
では、企業に勤めながら診断士として活動する「企業内診断士」はどうでしょうか。確かに、安定した収入を確保しながら診断士活動ができるため、リスクは低いように見えます。
しかし、企業内診断士にも大きな問題があります。まず、本業が忙しく、診断士としての活動時間が確保できないことです。平日は会社の仕事、週末は家族サービス。診断士活動に充てられる時間はごくわずかです。
私の知る企業内診断士の多くは、年間の診断士活動日数が10日未満です。これでは、スキルの向上も望めませんし、人脈構築も進みません。結局、「資格を持っているだけ」の状態になってしまうのです。
また、多くの企業では診断士資格を評価しません。資格手当がつく企業は稀で、昇進や昇給に直結することもほとんどありません。つまり、企業内では診断士資格はほぼ「趣味」扱いなのです。
ある大手メーカーに勤める診断士は、こう嘆いていました。「資格を取得したことを上司に報告したら、『へえ、すごいね』で終わりでした。その後、何も変わりません。評価も給料も、まったく変わらないんです」



私もそんな感じでした。上司からの「すげーじゃん」の一言で終わり。転職の際も、「中小企業診断士」という肩書きは全く評価の対象とはなりませんでした。
さらに、副業規定の問題もあります。多くの企業では副業が制限されているため、診断士として報酬を得ることができません。ボランティアでの活動に限定されることが多く、経済的なメリットはほとんどありません。
最近は副業を解禁する企業も増えていますが、それでも「本業に支障がない範囲で」という条件付きです。結局、本格的な診断士活動はできず、小遣い稼ぎ程度に終わってしまうことがほとんどです。



まぁ小遣い程度でも稼ぐことができる人はまだマシですけどね。企業内診断士の大半は、診断士活動からの収入はゼロだと思います。
診断士ビジネスの構造的な問題
中小企業診断士が「食えない」のは、個人の努力不足だけが原因ではありません。診断士ビジネスそのものに構造的な問題があるのです。
まず、診断士の供給過剰です。毎年1000人以上の新規診断士が誕生していますが、それに見合うだけの需要はありません。パイの大きさは変わらないのに、分け合う人数だけが増えている状態です。
しかも、診断士の多くは定年退職後のシニア層です。彼らの中には、年金があるため、低単価でも仕事を受ける人がいます。これが、全体の単価下落を招いているのです。
次に、診断士サービスの差別化の難しさです。診断士が提供するサービスは、基本的に「経営相談」「経営診断」「経営計画策定支援」など、どれも似たり寄ったりです。クライアントから見れば、誰に頼んでも大差ないように見えてしまいます。



中小企業診断士の案件は9割は補助金関係です。残りの1割の人が企業コンサルや講師業で稼いでいるイメージです。公的業務もコンサルと言えなくもないですが、フィーは安いのに、診断協会やその中の採用者にコネがないと到底採用されないくらい、超激戦です。
また、成果の見えにくさも問題です。コンサルティングの成果は数値化しにくく、投資対効果が不明確です。そのため、クライアントは継続的に費用を払うことに躊躇してしまいます。
さらに、公的機関との競合もあります。商工会議所や中小企業支援センターなど、無料または低価格で経営相談を行う公的機関が数多く存在します。民間の診断士は、これらと競合しなければなりません。
公的機関の相談員の中には、診断士資格を持つ人も多くいます。彼らは公的機関から給料をもらいながら、実質的に診断士業務を行っているのです。民間の診断士から見れば、不公平な競争と言えるでしょう。
加えて、補助金ビジネスの問題もあります。多くの診断士が、補助金申請支援を主な収入源としています。しかし、これは本来の診断士業務とは言えません。単なる書類作成代行に過ぎないのです。
しかも、補助金ビジネスは競争が激しく、単価も下がり続けています。成功報酬型で受注しても、不採択になれば収入はゼロです。これでは、安定した事業とは言えません。



地方の公的機関の相談員の中には、無料で補助金の申請を支援するところもあるので、その辺りも診断士の食い扶持が奪われている原因の1つかと思います。あとは、信用金庫や地銀も似たようなサービスを展開しているので、そことの差別化も難しいところがあるかと思います。
診断士資格の本当の価値とは
ここまで厳しい現実を述べてきましたが、では診断士資格には全く価値がないのでしょうか。そうではありません。ただし、その価値は予備校が宣伝するようなものとは異なります。
診断士資格の本当の価値は、体系的な経営知識を身につけられることです。財務、マーケティング、生産管理、情報システムなど、幅広い分野の知識を学ぶことができます。これは、自身のキャリアにおいて確実にプラスになります。
ただし、この知識は「知っている」レベルに過ぎません。実務で使えるレベルになるには、さらなる学習と経験が必要です。診断士試験の勉強だけでは、実践的なスキルは身につかないのです。



例えば、僕の専門であるマーケティングは、確かに診断士のテキストの内容は基礎的な内容を網羅しており、初学者の教科書としてはとても良くできてますが、それを知っているから集客のアドバイスや実施をできるかというと、そういう訳ではありません。
また、診断士のネットワークも価値があります。同じ志を持つ仲間との出会いは、人生を豊かにしてくれます。ただし、それが直接的な収入につながるかどうかは別問題です。
多くの診断士は、「診断士同士のネットワークで仕事が回ってくる」と期待しています。しかし、現実には、診断士同士で仕事を奪い合っているのが実情です。



診断士経由で仕事が来るのは、本当にマレですね。診断士自体が、他人に仕事を回すほど稼げてないのが要因だと思います。
企業内で活用する場合、診断士の知識は確実に役立ちます。経営的な視点を持って仕事に取り組めるようになり、それが評価につながることもあります。ただし、それは診断士資格があるからではなく、身につけた知識とスキルがあるからです。
つまり、診断士資格の価値は、「資格そのもの」ではなく、「資格取得の過程で得られる知識と経験」にあるのです。この点を理解せずに、資格さえ取れば人生が変わると考えるのは、大きな間違いです。



この前も診断士と食事をしたのですが、「診断士受験サイト」の闇についての話題について盛り上がりました。ああいうサイトに書き込んでいる人は、診断士に受かればバラ色の景色が見えると思っているんでしょうけど、そんなバラ色の未来なんかある訳ないだろ、と。むしろ、現実とのギャップに落胆しないために、ああいうサイトは見ない方がいいんじゃないか、という話になりました。
診断士を目指す前に考えるべきこと
もしあなたが今、診断士資格の取得を検討しているなら、次のことを真剣に考えてください。
まず、なぜ診断士になりたいのか、その目的を明確にすることです。「稼ぎたい」「独立したい」という理由なら、他の選択肢も検討すべきです。診断士資格は、稼ぐための最短ルートではありません。
もし本当に稼ぎたいなら、需要の高いスキルを身につける方が確実です。例えば、プログラミング、データ分析、デジタルマーケティングなど、今の時代に求められるスキルは他にもたくさんあります。
次に、投資対効果を冷静に計算することです。取得にかかる時間とコスト、そして期待できるリターンを現実的に見積もってください。多くの場合、投資に見合うリターンは得られません。
1000時間の勉強時間を他のことに使ったら、どれだけの価値を生み出せるでしょうか。50万円の受講料を他の投資に回したら、どれだけのリターンが得られるでしょうか。こうした機会費用も含めて、総合的に判断する必要があります。
また、自分の強みと弱みを正直に評価することです。特に営業力、人脈構築力は診断士として成功するために不可欠です。これらが苦手なら、診断士として独立するのは避けた方が賢明です。



診断士に限った話でないですが、仕事をとってくるには、営業力やマーケティング力は必須です。特に診断士はバックオフィス系の仕事をしていた人が多いので、その点は仕事をとってくるのに致命的だと思います。
診断士として成功している人の多くは、もともと営業力があり、人脈も豊富な人たちです。診断士資格は、彼らの既存の強みを補強するツールに過ぎません。資格だけで成功できるほど、世の中は甘くないのです。
実際、大手コンサルティングファームで経験を積んでから独立する方が、診断士資格を取って独立するよりも成功確率は高いでしょう。実務経験と実績があれば、資格の有無は関係ないのです。



仮に戦略系かIT系のコンサルファーム出身なら、コンサル紹介会社に登録すれば案件はありますからね、今の所。まぁそれだと会社員時代と大して働き方自体は変わらないので、独立する意味あるのかと問われれば、若干疑問なところはありますが。
診断士資格ビジネスの闇
ここで、診断士資格を取り巻くビジネスの闇についても触れておきましょう。
予備校や資格学校だけでなく、診断士協会や各種研修機関も、診断士から収益を上げる構造になっています。更新研修、スキルアップ講座、交流会など、あらゆる名目で費用を徴収します。
特に問題なのは、「診断士として成功するための講座」と称して、高額なセミナーや教材を売りつける業者の存在です。成功していない診断士に「成功の秘訣」を売るという、矛盾に満ちたビジネスが横行しています。



これは業界にいるといろいろ見ますよね。補助金の申請書が書けないコンサルが主催する補助金コンサル要請講座、プログラミングが分からない人が主催するAI講座、動画ソフトのことがよく分かってない人が開催する動画マーケティング講座。まぁ酷い講座はいっぱいあります、てか、酷いのだらけです。
「月収100万円を稼ぐ診断士になる方法」「診断士で年収1000万円を実現する秘訣」といったタイトルのセミナーが、30万円、50万円という高額で販売されています。しかし、そのセミナー講師自身が、本当にそれだけ稼いでいるかは疑問です。



その人がどんだけ稼いでいるかとか、本当にどれだけノウハウを持っているかなどは、外からは分かりづらいですからね。講座を受講して、初めて内容がクソだと分かる感じです。まぁ中には講座受講しても気づかない業界用語で言うところの「洗脳が解けてない人」もいますが。
こうした構造の中で、多くの診断士は「資格を維持するために働く」という本末転倒な状態に陥っています。資格を活かして稼ぐのではなく、資格を維持するために稼がなければならないのです。
さらに深刻なのは、診断士資格を使った詐欺まがいのビジネスも存在することです。「診断士資格があれば、補助金が簡単に取れる」「診断士ネットワークで、確実に仕事が回ってくる」といった嘘を並べて、高額な加盟金を取る団体もあります。



こういう団体は、主催者だけ儲かって下々の人は会費とかだけ吸い上げられるいわば宗教ビジネスです。本来であれば、仕事がある分だけの採用に絞り込むとかなら良いのですが、大量の会員だけ集めて「当会にはこんだけ会員がいます!」とやるからタチが悪いです。
それでも診断士を目指すあなたへ
ここまで読んで、それでも診断士を目指したいと思うなら、私はそれを止めません。ただし、現実を直視した上で、戦略的にアプローチすることが重要です。
まず、診断士資格を「ゴール」ではなく「スタート」と考えることです。資格取得はあくまでも第一歩に過ぎません。そこから先の道のりの方がはるかに長く、険しいのです。
資格を取得したら、すぐに実務経験を積むことです。補助金申請支援でも、経営改善計画策定でも、何でもいいので、実際の仕事を経験することが重要です。机上の知識だけでは、クライアントの信頼は得られません。



一つ注意点をアドバイスとすると「補助金業務や公的業務にはのめり込みすぎるな」と言う点でしょうか。補助金業務や公的業務を主力にしている人や会社で、普通の経営コンサルタントにステップアップできた人や会社は見たことありません。勉強のために多少補助金業務をやるのはいいと思いますが、割り切ってそこだけに注力しない方がいいでしょう。そこに注力しちゃうと、他の業務への応用が効かず、収入が安定しないので。
次に、診断士資格以外の強みを必ず持つことです。特定業界の深い知識、ITスキル、語学力など、他の診断士と差別化できる要素が不可欠です。診断士資格だけでは勝負になりません。
例えば、製造業で20年の経験がある、IT企業で新規事業開発を担当していた、海外駐在経験があるなど、あなたにしかない強みを活かすことが重要です。診断士資格は、その強みを補強するツールとして使うのです。
また、まずは副業から始めることをお勧めします。いきなり独立するのではなく、本業を続けながら少しずつ実績を積み上げていく。これが最もリスクの低いアプローチです。
週末や夜間を使って、少しずつクライアントを増やしていく。そして、副業収入が本業収入の半分程度になったら、独立を検討する。このように、段階的にリスクを取っていくことが重要です。
さらに、過度な期待を持たないことです。診断士になれば人生が変わる、収入が倍増する、そんな夢物語を信じてはいけません。地道な努力の積み重ねしか、成功への道はありません。
診断士として成功するには、最低でも5年、10年という長期的な視点が必要です。すぐに結果を求めず、コツコツと実績を積み重ねていく覚悟が必要なのです。
診断士業界の未来予測
ここで、診断士業界の今後について、私なりの予測をお伝えしましょう。残念ながら、明るい未来は期待できません。
まず、AI技術の進化により、診断士の仕事の多くが代替される可能性があります。財務分析、市場分析、経営計画策定など、定型的な業務はAIの得意分野です。人間の診断士にしかできない仕事は、どんどん減っていくでしょう。
すでに、大手コンサルティングファームでは、AIを活用した経営診断サービスを開発しています。これが普及すれば、個人の診断士が提供できる価値は、さらに低下するでしょう。



まぁその大手コンサルファームも将来的には大幅な縮小・消滅の運命には逆らえないと思います。知識を武器にする職業・産業は、近々9割は消滅します。AIの優秀さに対抗できる人は、極少数しかいません。
また、中小企業の減少も深刻な問題です。日本の中小企業数は、年々減少しています。後継者不在による廃業、M&Aによる統合など、診断士の顧客となる中小企業そのものが減っているのです。
さらに、グローバル化の進展により、海外のコンサルタントとの競争も激化するでしょう。オンラインでのコンサルティングが一般化すれば、インドやフィリピンの優秀なコンサルタントが、日本市場に参入してくる可能性もあります。
こうした環境変化の中で、従来型の診断士ビジネスモデルは、確実に行き詰まります。「経営の知識がある」だけでは、もはや価値を提供できない時代が来ているのです。



と、言うより、2024年の補助金バブルの崩壊ですでに行き詰まってます。補助金バブルは診断士を稼げる職業に見せかけた儚い夢でした。この時独立しちゃった多数の診断士は、今後、地獄を見るでしょう。
まとめ:真実を知った上での選択を
中小企業診断士の資格は、決して「食える資格」ではありません。統計データが示すように、9割の診断士は思うように稼げていないのが現実です。
予備校や資格学校は、この真実を決して語りません。なぜなら、それが彼らのビジネスモデルを崩壊させるからです。成功事例ばかりを前面に出し、失敗例は隠蔽する。これが業界の実態なのです。
資格取得には膨大な時間とコストがかかり、取得後も継続的な出費が必要です。それにも関わらず、資格自体が仕事を生み出すわけではありません。結局は、個人の営業力、人脈、差別化要素が成否を分けるのです。
診断士ビジネスには構造的な問題があり、今後もその状況が改善される見込みは薄いでしょう。むしろ、AI技術の進化や中小企業の減少により、さらに厳しい環境になることが予想されます。
私がこの記事で伝えたいのは、「診断士を目指すな」ということではありません。真実を知った上で、冷静に判断してほしいということです。甘い幻想に惑わされることなく、現実的な選択をしてほしいのです。
もしあなたが本気で経営コンサルタントを目指すなら、診断士資格にこだわる必要はありません。実力さえあれば、資格なしでも成功できます。逆に、資格があっても実力がなければ、決して成功することはできません。
診断士資格は、あくまでも「手段」であって「目的」ではありません。あなたの人生の目的は何でしょうか。それを実現するために、本当に診断士資格が必要でしょうか。もう一度、じっくり考えてみてください。
資格ビジネスの甘い誘惑に惑わされず、自分の人生は自分で切り開く。そんな覚悟を持って、あなたの道を選んでください。どんな選択をするにせよ、後悔のない人生を送ることを心から願っています。