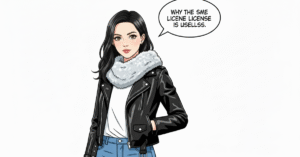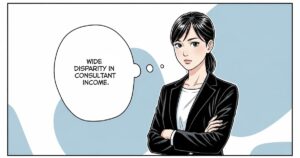中小企業診断士試験に合格しても稼げない理由|予備校が絶対に教えない年収の真実


実は、中小企業診断士の資格を取得しても、ほとんどの人は稼げていないというのが現実です。予備校や資格スクールは決して教えてくれない、中小企業診断士の年収の真実について、今回は包み隠さずお伝えします。
中小企業診断士の平均年収は本当に高いのか?



まず、よく引き合いに出される中小企業診断士の平均年収について見てみましょう。
一般的に言われている中小企業診断士の平均年収は約780万円。これは確かに日本の平均年収(約450万円)と比較すると高い数字です。しかし、この数字には大きなカラクリがあります。
平均年収のマジック
この780万円という数字は、実は企業内診断士の年収が大きく影響しています。企業内診断士とは、会社員として働きながら診断士資格を持っている人のことです。
彼らの多くは、もともと大企業や中堅企業で管理職として働いており、診断士資格を取る前から高い年収を得ていました。つまり、診断士資格があるから年収が高いのではなく、もともと年収が高い人が診断士資格を取っているだけなのです。
実際、企業内診断士の多くは40代以上の管理職クラスです。彼らは診断士資格を取る前から年収700万円以上を得ており、資格取得後も基本的には同じ会社で同じ仕事を続けています。資格手当が付く企業もありますが、せいぜい月1〜3万円程度。年収が劇的に上がるわけではありません。
さらに言えば、こうした統計には別のトリックも隠されています。診断士協会が実施するアンケート調査の回答率は決して高くありません。成功している診断士ほどアンケートに回答する傾向があり、苦戦している診断士はそもそも診断士協会から距離を置いていることが多いのです。つまり、統計データ自体が成功者に偏っている可能性が高いということです。
独立診断士の厳しい現実
では、独立して開業した診断士はどうでしょうか?
独立診断士の年収分布を見ると、衝撃的な事実が浮かび上がります。独立診断士の約30%が年収300万円未満、約25%が年収300万〜500万円、約20%が年収500万〜800万円、約15%が年収800万〜1000万円、そして年収1000万円以上はわずか約10%に過ぎません。
つまり、独立診断士の半数以上が年収500万円未満という厳しい現実があるのです。これは会社員の平均年収とほぼ同じか、それ以下の水準です。
しかも、この数字には売上と年収を混同している人も含まれている可能性があります。独立診断士の場合、売上から経費を引いた手取り収入はさらに少なくなります。事務所の家賃、交通費、書籍代、セミナー参加費、診断士協会の年会費など、さまざまな経費がかかります。売上500万円でも、手取りは300万円程度ということも珍しくありません。
実際に独立診断士の中には、開業3年目でも月収20万円に届かない人がいます。大手企業を早期退職して診断士として独立しましたが、退職金を切り崩しながら何とか生活している人もいます。早期退職自体はまことに結構ですが、診断士としての実力が伴わないうちに独立してしまう人も大勢いると感じています。
下記記事で、中小企業診断士の年収については詳しく解説しています。


なぜ中小企業診断士は稼げないのか?5つの理由



では、なぜ難関資格と言われる中小企業診断士が稼げないのでしょうか?その理由を詳しく見ていきましょう。
理由1:資格だけでは仕事は来ない
中小企業診断士の資格を取得しただけでは、仕事は一切来ません。これは医師や弁護士のような業務独占資格とは大きく異なる点です。
診断士は名称独占資格であり、資格がなくても経営コンサルティング業務を行うことは可能です。実際、多くの大手コンサルティングファームのコンサルタントは、診断士資格を持っていません。マッキンゼー、ボストンコンサルティンググループ、アクセンチュアなど、名だたるコンサルティング会社で診断士資格を重視しているところはほとんどありません。



その他、コンサルティング会社で、診断士資格を持っているからと言って、採用に有利になるとか一切聞いたことがありません。せいぜい、中小機構など、公的機関での採用が有利になるくらいでしょう。
つまり、資格を取ったからといって、自動的に仕事が舞い込んでくるわけではないのです。営業力、人脈、実績など、資格以外の要素が圧倒的に重要になります。
私が独立直後に痛感したのは、「診断士の看板」だけでは誰も振り向いてくれないという現実でした。名刺交換をしても「へぇ、診断士さんなんですね」で終わり。それだけでは具体的な仕事の話にはまったく発展しません。私は、幸運なことに、独立してから、かつての人脈や知人からの紹介で何とか最初の仕事を獲得しましたが、それは私がマーケティングの専門家だから仕事が来ただけで、全く診断士の資格とは関係ない部分で仕事を取っています。
理由2:競争の激化と市場の飽和
中小企業診断士の登録者数は年々増加しており、現在では約3万人を超えています。一方で、中小企業の数は減少傾向にあり、需要と供給のバランスが崩れているのが現状です。
特に都市部では診断士が飽和状態にあり、限られたパイを奪い合う激しい競争が繰り広げられています。東京都内だけで5000人以上の診断士が登録されており、その多くが同じような仕事を求めて営業活動を行っています。



正確には、仕事を口を空けて待っていると言う表現が正しく、自ら動いて仕事を取ってこようと言う人はかなり少ないです。診断協会や商工会など、どちらかというと安易な方法で仕事を取りに行く人が多い感じです。
あとは、診断士業界では、コンサルティングの単価も安い傾向にあります。コンサルティング単価としては、時給1万円から5000円くらいが相場ではないでしょうか。これは、公的機関が「診断士の時給は上限を1万円にすべし」的なところがあるので、それが定着しているからかな、と思います。
さらに深刻なのは、診断士同士の仕事の奪い合いです。公的機関の専門家派遣事業なども、応募者が殺到して倍率が10倍を超えることも珍しくありません。せっかく応募しても、実績のあるベテラン診断士に仕事を持っていかれることがほとんどです。新人診断士が入り込む余地はほとんどないのが実情です。



公的業務については、業務量の割にはフィーが安いのと、診断士内での競争がとてて激しいので、そこまでしてありつく仕事でもないのかな?と思います。その時間があるなら、他の業務を行った方が生産的でしょう。
理由3:中小企業の支払い能力の限界
中小企業診断士の主な顧客である中小企業は、そもそもコンサルティングに高額な費用を支払う余裕がないことが多いです。
大企業であれば、月額100万円以上のコンサルティングフィーを支払うことも珍しくありませんが、中小企業の場合、月額10万〜30万円が限界というケースがほとんどです。年商の企業が、年間360万円のコンサルティング費用を支払うことは現実的ではありません。
しかも、継続的な契約を獲得することは難しく、スポット的な仕事が中心になりがちです。3ヶ月の契約が終われば、また新しいクライアントを探さなければなりません。安定した収入を得ることが困難な構造になっているのです。



ただ、中小企業はいろいろ困っているので、コンサルティングについての需要自体はあります。ただ、見ず知らずのコンサルタントにいきなり仕事を発注したり、そもそもコンサルタントの使い方が分かっていなかったりするので、コンサルタントの起用には二の足を踏んでいるところが多い感じです。
理由4:公的業務の単価の低さ
中小企業診断士の仕事の中には、商工会議所や自治体からの公的な仕事があります。これらは比較的獲得しやすい仕事ですが、単価が非常に低いという問題があります。
経営相談は1日あたり1万円から2万円、セミナー講師は2時間で30,000円〜50,000円、補助金申請支援は成功報酬で10%〜20%といった具合です。これらの仕事だけで生計を立てようとすると、相当な数をこなさなければならず、結果的に時間単価が低くなってしまいます。
例えば、商工会議所の経営相談員として月10日勤務したとしても、日当1万円×10日=10万円です。これだけでは生活できないため、複数の商工会議所を掛け持ちしたり、他の仕事と組み合わせたりする必要があります。しかし、移動時間や準備時間を考慮すると、実質的な時給は2,000円〜3,000円程度になってしまうことも少なくありません。



実際に、経営相談員も普通に切られることはあります。いずれにせよ、基本的に公的機関は相談員に十分な予算が割けないので、単価はかなり安いです。それでも、公募は倍率がとても高く激戦なので、単価を上げるインセンティブも公的機関側には全くないです。
理由5:専門性の不足
中小企業診断士は「経営の総合医」と呼ばれますが、裏を返せば「何でも屋」で専門性に欠けるという見方もできます。
クライアントが本当に困った時、専門性の高い税理士、社労士、弁護士などに相談することが多く、診断士は「とりあえず相談する相手」という位置づけになりがちです。税務の問題なら税理士、労務の問題なら社労士、法的な問題なら弁護士というように、それぞれの専門家には明確な役割があります。
一方、診断士の役割は曖昧です。「経営全般のアドバイス」と言っても、具体的に何ができるのかがわかりにくい。結果として、「話を聞いてもらってスッキリした」程度の価値しか提供できないケースも多いのです。
高単価の仕事を獲得するためには、特定分野での深い専門性が必要ですが、診断士の試験勉強だけではそれを身につけることはできません。試験科目は広く浅く、実務で使えるレベルの知識とは程遠いのが実情です。



もちろん、社長のお茶飲み友達程度の「顧問契約」で仕事をできている診断士も一部にはいます。ただ、そういう仕事を取ってこれる営業力のある診断士は特殊で、再現性のあるやり方ではありません。
予備校が語らない不都合な真実
では、なぜ予備校や資格スクールは、こうした厳しい現実を伝えないのでしょうか?
ポジショントークの罠
答えは簡単です。受講生が減ってしまうからです。
予備校にとって、中小企業診断士講座は重要な収益源です。1人あたり20万〜50万円の受講料を支払ってもらうためには、「資格を取れば明るい未来が待っている」というストーリーを語る必要があります。
「資格を取っても稼げません」なんて正直に言ってしまったら、誰も高額な受講料を払ってくれません。だから、成功事例ばかりを強調し、都合の良い統計データを使って、バラ色の未来を描いてみせるのです。
予備校の営業担当者は、巧みな話術で夢を売ります。「診断士になれば、企業の経営者から頼りにされ、感謝されながら高収入を得られる」「定年後のセカンドキャリアとして最適」「AIに代替されない仕事」などなど。しかし、これらはすべて「可能性の話」であって、「確率の話」ではありません。
成功者バイアスの問題
予備校のパンフレットやウェブサイトには、必ず「成功した診断士」のインタビューが掲載されています。年収1000万円を超える独立診断士、大手企業から引く手あまたのコンサルタント…
しかし、これらはごく一部の成功者に過ぎません。その陰には、稼げずに廃業した診断士、副業レベルでしか活動できない診断士が大勢いるのです。
予備校は意図的にこうした「失敗例」を隠し、成功例だけを強調することで、受講生に誤った期待を抱かせているのです。これは、宝くじの当選者だけを見せて「あなたも億万長者になれる」と言っているようなものです。
さらに問題なのは、成功している診断士の多くが、診断士資格以外の強みを持っているという事実が隠されていることです。例えば、元大手企業の役員、特定業界での豊富な実務経験、すでに確立された人脈など。これらの要素が成功の主因であるにもかかわらず、あたかも診断士資格のおかげで成功したかのように語られるのです。



例えば、今であれば診断士資格を持っていて、きちんとプログラムも組める診断士であれば、それなりに稼ぐことはできます。ただこの場合は、診断士資格が評価されてるわけではなく、ITの知識が評価されてのことなので、診断士資格の価値としてはそこまで高くないのが現状です。
中小企業診断士が稼ぐために必要な現実的な戦略
ここまで厳しい現実をお伝えしてきましたが、だからといって中小企業診断士の資格が全く無意味というわけではありません。正しい戦略を持って活用すれば、資格を活かすことは可能です。
戦略1:認定支援機関を取る



僕が診断士を持っていて良かったと思えたところは、クレジットカードなどの審査が通りやすいところと、認定支援機関が取れたところです。
認定支援機関とは、国によって認められた中小企業を支援する機関のことです。この資格を持っていることで、特定の補助金の支援などを行うことができます。また、中型補助金などには、必須項目ではないものの、認定支援機関の記入欄があり、国も認定支援機関の支援のもとに補助金の申請書を作成することを奨励していたり、何かと使い勝手が良い認定です。
公認会計士、税理士、中小企業診断士は認定支援機関を割りかし簡単に取ることができます。なので、これが診断士資格を取得する最大のメリットになると思います。
戦略2:他の資格や専門性と組み合わせる
診断士資格単体では差別化が難しいため、他の資格や専門性と組み合わせることが重要です。
診断士と税理士の組み合わせなら、事業承継やM&Aのスペシャリストとして活躍できます。診断士と社労士なら、人事労務コンサルタントとして企業の組織改革を支援できます。診断士とITスキルがあれば、DXコンサルタントとして引く手あまたです。
また、特定の業界で長年の実務経験がある場合、その業界に特化したコンサルタントとして差別化できます。例えば、飲食業界で20年の経験がある診断士なら、飲食店専門のコンサルタントとして独自のポジションを築けるでしょう。
このように、診断士の知識をベースにしながら、プラスアルファの専門性を身につけることで、高単価の仕事を獲得しやすくなります。ただし、これには追加の投資(時間とお金)が必要になることも忘れてはいけません。
戦略3:情報発信とブランディング
現代において、情報発信力は必須のスキルです。
ブログ、YouTube、SNSなどを活用して、自分の専門分野について継続的に情報発信を行うことで、見込み客を集めることができます。重要なのは、単に診断士として発信するのではなく、特定の分野の専門家として認知されることです。
ただし、これも簡単ではありません。継続的な努力と、価値ある情報を提供し続ける忍耐力が必要です。多くの診断士が情報発信を始めても、3ヶ月も続かずに挫折してしまうのが現実です。



マーケティングの良いところは、正しい方向に努力すれば必ず結果が出るところです。ただ、結果が出るには、今は最低でも3ヶ月、長期的に見ると1年ほどの時間が必要です。なので、そこに行き着く前に辞めてしまう人がほとんどです。
成功している診断士の多くは、何年も継続的に情報発信を続けています。最初の1年はほとんど反応がなくても、あきらめずに続けることで、徐々にファンが増え、仕事の依頼も来るようになるのです。しかし、そこまで続けられる人は全体の1割にも満たないでしょう。
中小企業診断士を目指す前に考えるべきこと
ここまで読んで、「それでも診断士を目指したい」と思う方もいれば、「やめておこう」と思う方もいるでしょう。どちらの選択も間違いではありません。
大切なのは、現実を正しく認識した上で判断することです。
本当の目的は何か?
中小企業診断士を目指す前に、自分に問いかけてみてください。
なぜ診断士資格が欲しいのでしょうか。資格を取って何を実現したいのでしょうか。その目的は診断士資格でなければ達成できないのでしょうか。
もし「稼ぎたい」ということが主目的なら、診断士資格は最適な選択肢ではないかもしれません。ITスキルを身につけたり、営業力を磨いたり、他にも稼ぐ方法はたくさんあります。
私の場合、診断士を目指した理由は「網羅的に経営学の勉強がしたい」というものでした。しかし、今思えば、診断士資格がなくてもコンサルタントにはなれたはずです。あくまで実務経験があっての診断士資格なのです。
投資対効果を冷静に計算する
診断士試験に合格するまでには、平均して3〜5年の時間と100万円以上の費用がかかります。
予備校の受講料は20万〜50万円、教材費は5万〜10万円、受験料は約3万円を受験回数分、そして何より貴重なのは勉強時間です。1000〜2000時間という膨大な時間を投資することになります。
これだけの投資をして、本当にリターンが得られるのか。冷静に計算してみる必要があります。
同じ時間とお金を、プログラミング学習や英語学習、あるいは実務経験の積み重ねに投資した方が、より大きなリターンを得られる可能性もあるのです。
例えば、2000時間あれば、プログラミングをマスターしてフリーランスエンジニアとして独立することも可能です。英語をビジネスレベルまで引き上げて、外資系企業に転職することもできるでしょう。これらの選択肢と比較して、本当に診断士が最良の選択なのか、よく考えてみてください。
それでも診断士を目指すあなたへ
ここまで厳しい現実をお伝えしてきましたが、それでも「診断士を目指したい」という方もいるでしょう。
実は、それはそれで素晴らしいことです。なぜなら、幻想を抱かず、現実を見据えた上で挑戦する人こそが、本当の成功を掴む可能性が高いからです。
現実的な期待値を持つ
「資格を取れば稼げる」という幻想を捨て、「資格は活用次第」という現実的な認識を持つことが大切です。
診断士資格は、あくまでもツールの一つに過ぎません。そのツールをどう使うかは、あなた次第です。資格に過度な期待をせず、自分の強みと組み合わせて活用する方法を考えることが重要です。
また、すぐに結果を求めないことも大切です。診断士として軌道に乗るまでには、最低でも3〜5年はかかると覚悟しておくべきです。その間は収入が不安定になることも想定し、十分な準備をしておく必要があります。
学習プロセスを楽しむ
診断士試験の学習内容は、経営に関する幅広い知識を体系的に学べる良い機会でもあります。
試験合格を目的にするのではなく、学習プロセスそのものを楽しむという姿勢で臨めば、たとえ思うような収入が得られなくても、得るものは大きいはずです。
経済学、財務会計、企業経営理論など、診断士試験の科目は実際のビジネスに役立つ知識が満載です。これらの知識は、たとえ診断士として独立しなくても、会社員として働く上で必ず役に立ちます。
人脈形成の場として活用する
診断士の勉強会や研究会は、同じ志を持つ仲間と出会える貴重な場です。
そこで築いた人脈は、将来的にビジネスパートナーになったり、仕事を紹介し合ったりする関係に発展する可能性があります。資格そのものよりも、人脈の方が価値があるという見方もできます。
実際、私が診断士活動で得た最大の財産は、志を同じくする仲間たちとの出会いでした。彼らとは今でも定期的に情報交換をしており、お互いに仕事を紹介し合うこともあります。この人脈がなければ、とっくに診断士をあきらめていたかもしれません。



仕事をもらうと言うより、一緒に仕事をする仲間を探すと言う意味では、診断士の資格はかなり有効だと思います。現に私も、複数の診断士と一緒に業務を推進しています。
まとめ:真実を知った上で、賢い選択を
中小企業診断士試験に合格しても稼げない理由について、包み隠さずお伝えしてきました。
診断士の平均年収は統計のマジックで高く見えますが、実態は企業内診断士の年収に引き上げられているだけです。独立診断士の半数以上は年収500万円未満という厳しい現実があります。資格だけでは仕事は来ず、市場は飽和状態で競争が激化しています。予備校は都合の良い情報しか伝えず、受講生に誤った期待を抱かせています。
しかし、だからといって診断士資格が無価値というわけではありません。正しい戦略と現実的な期待値を持って活用すれば、キャリアアップのツールとして機能する可能性は十分にあります。
大切なのは、幻想に惑わされず、真実を知った上で判断することです。予備校の甘い言葉に踊らされることなく、自分の目的と照らし合わせて、冷静に判断してください。
もっと詳しく中小企業診断士の実態について知りたい方は、書籍「中小企業診断士はやめとけってホント?」をぜひお読みください。予備校が決して語らない診断士の裏側について、さらに詳しく解説しています。本書では、私自身の失敗談も含め、診断士として生き残るための具体的な戦略についても詳しく紹介しています。
最後に、これだけは覚えておいてください。資格は手段であって目的ではありません。本当に大切なのは、あなたが何を成し遂げたいのか、どんな価値を社会に提供したいのかということです。その目的が明確であれば、診断士資格が必要かどうかも自ずと見えてくるはずです。
あなたが賢明な選択をされることを願っています。そして、どんな道を選んだとしても、現実を直視し、地に足をつけて歩んでいけば、必ず道は開けるはずです。成功への近道はありません。しかし、正しい情報を持って正しい努力をすれば、遠回りは避けられるのです。