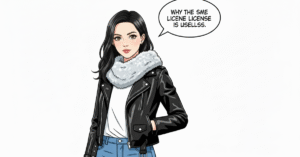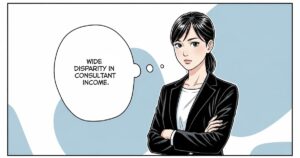【現役診断士が暴露】中小企業診断士は意味ない?食えないと言われる5つの理由


中小企業診断士の資格取得を目指している方、すでに合格した方、そして「診断士として独立したい」と考えている方へ。あなたは今、こんな悩みを抱えていませんか?
- 「中小企業診断士を取れば独立して稼げる」と聞いたけど本当?
- 予備校で言われる年収1000万円は現実的なの?
- 診断士として活動しているけど、思うように収入が上がらない
- 資格を活かした転職を考えているが、実際の市場価値が分からない
- 同期の診断士たちも「思っていたのと違う」と言っている
私は中小企業診断士として活動してきた中で、多くの診断士仲間と交流し、この資格の現実を目の当たりにしてきました。そして、残念ながら一つの結論に至ったのです。
中小企業診断士という資格は、多くの人にとってあまり意味がない。
この記事では、私が長年の経験と観察から導き出した「中小企業診断士が意味ない」と考える5つの理由を、予備校では絶対に教えてくれない現実とともにお伝えします。これから診断士を目指す方にとっては厳しい内容かもしれませんが、現実を知った上で判断していただきたいと思います。
この記事を読めば、中小企業診断士の資格取得や活用について、より現実的な判断ができるようになるでしょう。そして、もしあなたが本当に経営コンサルタントとして成功したいなら、診断士以外の道があることも理解できるはずです。
結論から申し上げると、中小企業診断士は2025年現在の時点では「資格ビジネス」の典型例であり、残念ながら多くの人にとって投資対効果の悪い資格だということです。
理由1:圧倒的に稼げない現実|年収300万円台が大多数



結論から言うと、診断士は、年々その資格だけで食べていくのが厳しくなっているのが現状です。
予備校が語らない診断士の年収実態
予備校や資格スクールでは「診断士になれば年収1000万円も夢じゃない」「独立すれば高収入が期待できる」といった甘い言葉が並びます。しかし、現実は全く違います。
私が所属する診断士協会での調査や、実際に多くの診断士と交流した経験から言えることは、大多数の診断士の年収は300万円台から500万円台だということです。
下記記事で、中小企業診断士の年収については詳しく解説しています。


なぜ診断士は稼げないのか
診断士が稼げない理由は明確です。
市場価値の低さが最大の要因です。中小企業の経営者から見れば、診断士の資格を持っているかどうかよりも「実際にどんな成果を出してくれるのか」が重要。ところが、多くの診断士は実務経験が乏しく、理論ばかりで実践的なアドバイスができません。



もちろん、中には実践的なノウハウを持っており、それによって稼いでいる人も一部います。ただ、一般的には、実務能力が低い人の方が多いでしょう。
成功している診断士の共通点



もちろん、中には年収1000万円を超える診断士もいます。しかし、彼らに共通しているのは「診断士の資格はあまり関係ない」ということです。
私が知っている診断士で稼いでいる人は、実務能力を持っています。例えば、アミューズメント企業が新規出店する際のコストを抑えるノウハウを持った人、創業融資に絞ってノウハウを持っている元公庫のコンサルタント、私であればマーケティングの実務、具体的なWebサイトの構築や広告運用のスキル。
中小企業の支援には、「コンサルタント」など、アドバイスするだけの人の需要はほとんどなく、「具体的に財務会計ソフトがいじれて適切な管理会計の実現できる」であったり、「生産現場の効率を高めるプログラミングが打てる」だったり、具体的な実務が求められます。
成功している診断士は例外なく以下の特徴を持っています:
- 診断士になる前から、特定の業界で豊富な実務経験を積んでいる
- 営業力やマーケティング力に長けている
- 診断士の肩書きではなく、実績で勝負している
- 資格に頼らず、独自のノウハウや手法を持っている
つまり、診断士として成功している人は、診断士の資格がなくても成功していたであろう人なのです。



正直私も、診断士資格は「無いよりあった方がいい」くらいな感じです。ただ、たまに質の悪いお客さん、例えば補助金の不正受給をしようと考えているお客さんとかには、「診断士としてそういうことは認められない」「それは公募要領違反です」と、より強く言いやすかったりするので、そういう点では資格は役に立ってますかね。
投資対効果を冷静に計算してみよう
診断士の資格取得には以下のような費用がかかります:
- 予備校費用:30〜50万円
- 教材費:10〜20万円
- 受験費用:数万円
- 勉強時間:1000〜1500時間



もし2次試験免除の養成課程に通うとすると、さらに追加で200万円から300万円超えのお金がかかります。
これだけの投資をして、仕事があればいいですが、残念ながら診断士は飽和状態で、口を開けて待っているだけで貰える仕事、例えば補助金の下請けや、公的業務は競争率が激戦となっています。なので、「資格を取ったから仕事が舞い込む」という状況には頼れないので、なかなか厳しいと思います。
理由2:資格の権威性が低すぎる|誰も知らない国家資格
一般認知度の絶望的な低さ
中小企業診断士は確かに国家資格です。しかし、その認知度は驚くほど低い。街で100人に聞いても、中小企業診断士を正確に説明できる人は5人もいないでしょう。
私自身、診断士として活動していて痛感するのは、この資格の認知度の低さです。



私は20年近く診断士をしてますが、診断士の名刺を渡して「ああ、診断士なんですね」と好意的な反応を示した人は、診断士を除いてはゼロです。
それが現実です。
企業からの評価も低い
転職市場での評価も期待できません。人事担当者の多くは中小企業診断士という資格を知りません。知っていたとしても「取得が比較的簡単な資格」という認識を持っている場合が多く、採用において大きなプラス要因にはなりません。
実際、私は、独立前に2回ほど大手転職エージェントを使って転職しましたが、「中小企業診断士の資格はアピールポイント」になることは全くありませんでした。面接などでも、資格について言及されたことは1度もありません。あくまで、見られるのは実務経験のみで、診断士資格は全く意味の無いものでした。



例外は、中小機構など、中小企業を支援する公的機関への就職と信用金庫の就職には中小企業診断士は効力を発揮します。ただ、どちらも採用数が多い訳ではないので、やはりあまり意味のある資格とは思えません。
独占業務がないことの致命的影響
中小企業診断士には独占業務がありません。これは単なる制度上の問題ではなく、ビジネスモデルそのものに関わる致命的な欠陥です。
独占業務がある資格(税理士、公認会計士、弁護士など)の場合、一定の需要が法的に保証されています。つまり、その資格がなければ絶対にできない仕事があるため、最低限の市場価値が担保されているのです。
一方、診断士の業務は誰でもできます。実際、大手コンサルティングファームの多くは診断士資格を持たないコンサルタントで構成されています。マッキンゼー、ボストン・コンサルティング・グループ、デロイトなどの一流ファームで働くコンサルタントの大部分は、MBA出身者であり、診断士資格を持っていません。



診断士を持ってない中小企業のコンサルタントもいっぱいいます。ただ、そういう人は、実務ができるか、とびきり営業ができるかのどちらかなので、どちらも無い人だとなかなか診断士で稼ぐのは厳しいかと思います。
企業が求める「本物のコンサルタント」との差
企業が本当に求めているのは、以下のような価値を提供できるコンサルタントです:
売上向上に直結する提案:理論的な知識ではなく、実際に売上を伸ばした経験と手法を持っている人。私が知る成功しているコンサルタントは、自身でビジネスを立ち上げて成功させた経験や、企業の営業部門でトップの実績を残した経験を持っています。
業界特有の課題への深い理解:例えば、製造業なら生産性向上、小売業なら店舗運営効率化、IT企業なら開発プロセス改善など、業界特有の専門知識が必要です。診断士試験で学ぶ一般的な経営知識では、こうした具体的な課題解決はできません。
人脈とネットワーク:優秀なコンサルタントは豊富な人脈を持っており、クライアントに適切な専門家や協力企業を紹介できます。しかし、多くの診断士は同業者との横のつながりはあっても、実際のビジネスに活用できる価値の高い人脈を持っていません。
資格取得後の「資格貧乏」現象
診断士資格を取得した後も、継続的な費用負担が発生します。これが「資格貧乏」と呼ばれる現象です。
更新研修費用:診断士資格を維持するためには、5年ごとに更新が必要で、その際に研修受講が義務付けられています。これらの研修費用は年間10万円以上になることも珍しくありません。



中小企業のコンサルを実際にしている人は、そこまで大変では無いですが、そうでない人は、診断士協会の研修を受ける必要があります。これは、5年で30日分、費用は1日1万円くらいなので、5年で30万円くらいかかる計算です。
各種セミナーや勉強会:スキルアップを名目とした有料セミナーが数多く開催されており、多くの診断士が「勉強熱心」という名目で参加し続けています。しかし、これらのセミナーの多くは理論中心で、実際の収入向上にはつながりません。
診断士会の年会費や各種活動費:地域の診断士会への参加費、各種研究会の参加費など、継続的な出費が発生します。診断協会の年会費は約5万円ほどです。
これらの費用を合計すると、年間20〜30万円程度の支出となります。しかも、かなりの時間も使う割には、その分の報酬がもらえる仕事が発生する訳では無いので、完全なマイナスの支出です。



診断士の維持費については、下記にまとめてるので、ご参考ください。


理由3:競合過多で差別化不可能|同じような診断士ばかり



結局、一番の問題は「診断士多すぎ」問題です。
診断士の供給過多問題
現在、中小企業診断士の登録者数は約2万8000人。毎年1000人以上が新たに登録されています。一方で、中小企業診断士に対する需要は限られており、明らかに供給過多の状態です。
特に都市部では診断士の密度が高く、案件の取り合いが激化しています。私が住む地域でも、診断士会の例会に参加すると、似たような経歴の診断士がずらりと並んでいます。



診断士の9割は、補助金業務と公的業務で稼いでいます。どちらも特別なスキルはそれほど必要ないですが、市場に大量の診断士が溢れているので、今や超激戦のレッドオーシャン市場です。
診断士の典型的な活動パターンと収益構造
実際の診断士がどのような活動をしているかを詳しく見てみましょう。私が観察してきた診断士の活動パターンは驚くほど画一的です。
補助金申請代行業務:多くの診断士が手がけるのが、ものづくり補助金や持続化補助金などの申請代行です。しかし、この業務は以下の問題があります:
- 競合が非常に多く、元請けも下請けも案件自体が激減している。
- 補助金が採択されたら成功報酬をもらうビジネスモデルなので、その時の補助金の公募状況に収入が依存する。
- 近年、補助金の不正受給が大問題となっており、提出書類や要件などが複雑化している。



まぁ、私は補助金をやる場合、今の公募内容ではあまりに工数がかかりすぎるので、ほぼAIに書かせてます。それでも、全然補助金の採択はされてるので、変化に対応していくやり方を取れば、やりようはあったりしますが。
セミナー講師業務:診断士会や商工会議所でのセミナー講師も一般的な活動です。しかし:
- 1回の講師料は2〜5万円程度
- 準備時間を考慮すると、実質的な時給は非常に低い
- 参加者の多くは同業者や公的機関の職員で、実際のビジネスにつながりにくい
- 同じような内容のセミナーが乱立しており、差別化が困難



セミナー講師は稼いでいる人は稼いでますが、個人の資質に左右されるところが大きいので、稼ぐという意味ではあまり再現性はないですかね。誰でもできるようなものではないと思います。
経営改善支援:理論上は最も価値の高い業務ですが:
- 成果が出なかった場合の責任問題
- 中小企業の多くは本格的なコンサルティング費用を支払う余力がない
- 月額10万円以下の安価な契約がほとんど
- 経営者との人間関係構築の困難さ



あとは、公的機関、例えば商工会だったり市の無料経営相談だったりとの競合も激しい感じでしょうか。「公」が無料で提供しているのに、わざわざお金払ったりしないですよね。
クライアント獲得の現実的な困難さ
診断士として最も困難なのが、継続的なクライアントの獲得です。多くの診断士が直面する課題を具体的に見てみましょう。
営業活動の難しさ:診断士の多くは元々サラリーマンで、営業経験が乏しい人が多数を占めます。



診断士に関わらず、士業はバックオフィス系の人が多く、そもそも営業経験がない人も多いです。まぁバリバリの技系なのに営業もゴリゴリできる診断士もいたりするので、個人の資質によるとことは大きいですが。
しかし、独立系コンサルタントとして成功するためには、高度な営業スキルが不可欠です。
- 見込み客の発掘方法が分からない
- 提案書の作成スキルが不足している
- クロージング(契約締結)の経験が乏しい
- 価格交渉のノウハウがない
信頼関係構築の困難さ:中小企業の経営者は、外部のコンサルタントに対して本質的に懐疑的です。特に以下の理由から、診断士への信頼は得にくい状況があります:
- 「実際にビジネスで成功した経験があるのか?」という疑問
- 「理論だけで実践経験がないのでは?」という不安
- 「本当に我が社の業界のことを理解しているのか?」という懸念
競合との差別化の困難さ:前述の通り、多くの診断士が同様のサービスを提供しているため、差別化が極めて困難です。結果として:
- 価格競争に巻き込まれやすい
- 「なぜあなたに依頼すべきなのか?」という質問に明確に答えられない
- 独自性のあるサービスを開発できない
診断士試験制度の構造的問題
診断士という資格そのものが抱える構造的な問題についても触れておく必要があります。
試験制度の歪み:現在の診断士試験は、経営学の基礎的な部分を学習するにはとても良い試験だと思いますが、以下の欠点も抱えています。:
- 1次試験は基礎的な知識の習得には役に立つが、実践的なスキルはまた別に磨く必要がある
- 2次試験は、良くはできているがこれも試験の限界がある。
資格制度の利権構造:診断士資格を維持するためのシステムが、既得権益化している側面があります:
- 更新研修の多くが、診断士会関係者によって運営されている
- 研修内容と実務との乖離が指摘されても改善されない
- 新たな研修制度やセミナーが次々と創設され、受講料収入が拡大している
中小企業側の本音と現実
一方で、中小企業側から見た診断士への評価も厳しいものがあります。私が中小企業経営者から直接聞いた本音をお伝えします。
費用対効果への疑問:
実務能力への不信:
- 「月20万円のコンサルティング料を払うなら、優秀なパート社員を1人雇った方がマシ」
- 「理論的な話はもういいから、明日から使える具体的な方法を教えてほしい」
- 「診断士さんに相談しても、結局『業界の常識』を説明されるだけ」
- 「うちの業界のことを本当に理解しているとは思えない」
- 「提案内容が教科書通りで、現場の実情に合わない」
- 「自分でビジネスをやったことがない人に、経営のアドバイスをされても説得力がない」
コミュニケーション面での課題:
- 「結果が出なくても、責任を取ってくれない」
- 「専門用語ばかりで、分かりやすく説明してくれない」
- 「現場の社員との関係構築ができない」



コミュニケーション面の課題であるあるなのは、「営業出身の人がコンサルサービスを売れない」ことが結構多いことでしょうか。個人的には、営業はユニバーサルな能力なので、むしろ何でも売れるだろ?と思っているのですが、意外に「モノ」を中心に売っていた人がサービスという「コト」を売ることができないのを、現場ではよく見ます。
成功している経営コンサルタントとの比較
一方で、診断士資格を持たずに成功している経営コンサルタントは数多く存在します。彼らと診断士との違いを分析してみましょう。
成功しているコンサルタントの特徴:
- 特定分野での深い専門性:例えば、EC事業専門、飲食店経営専門、製造業の生産性改善専門など、狭い分野で圧倒的な専門性を持っています。
- 実績に基づく信頼性:自身で会社を経営して成功させた、特定の業界で管理職として実績を残した、など具体的な成功体験を持っています。
- マーケティング力:SNSやブログ、書籍出版などを通じて効果的に自分をブランディングし、見込み客を獲得するスキルを持っています。
- 継続的な学習と進化:資格取得がゴールではなく、常に新しい知識やスキルを身につけ続けています。
- ネットワーク活用:業界内の人脈を活用して、クライアントに価値の高いサービスや情報を提供できます。
デジタル時代における診断士の立ち位置
現代のビジネス環境では、デジタル化への対応が中小企業にとって喫緊の課題となっています。しかし、多くの診断士はこの分野に対応できていません。
中小企業が直面するデジタル化の課題:
- EC事業の立ち上げとマーケティング
- SNSを活用した集客
- 業務のDX(デジタルトランスフォーメーション)
- データ分析に基づく意思決定
- AI・RPAの導入による業務効率化
これらの課題に対して、従来の診断士の知識体系では十分に対応できません。結果として、より実践的なスキルを持つWebマーケターやシステムコンサルタントに案件を奪われている状況があります。



個人的にはデジタル系やDX系の需要は、中小企業だからこそ多いと思います。どの社長も業務効率化には頭悩ましているのと、結果出すのも比較的ラクですし。なので、これからのコンサルで稼ぎたければ、まずはプログラミングを勉強するのが早いと感じています。
診断士資格の機会費用を考える
最後に、診断士資格取得の「機会費用」について考えてみましょう。機会費用とは、ある選択をすることで失われる他の選択肢の価値のことです。
時間の機会費用:診断士取得に必要な1000〜1500時間を他のスキル習得に使った場合:
- プログラミングスキル:Web開発やアプリ開発の基礎を身につけ、フリーランスとして活動可能
- デジタルマーケティング:SEO、広告運用、SNSマーケティングなど、需要の高いスキルを習得
- 確率・統計 : AIの理解や定量的に企業の業務を算定できるようになる
- 語学力:英語や中国語など、グローバル化に対応したスキル
- 業界特化の専門知識:特定業界での深い知識と人脈の構築



そう考えると、正直、中小企業診断士の勉強を今からするのは、あまりコスパが良いとは言えません。語学もイヤホンの同時通訳が始まる未来がすぐそこまで来ているので、ややリスクが高いでしょう。個人的にお勧めで、当面稼げそうなのは、プログラミング+統計数学ですかね。
中小企業が本当に必要としているサポートとは
中小企業が実際に求めているサポートと、診断士が提供できるサービスには大きなギャップがあります。このギャップを理解することで、なぜ診断士が市場で評価されないのかが明確になります。
即効性のある売上向上策:中小企業の経営者が最も関心を持つのは「明日からでも実行できて、3ヶ月以内に効果が見える施策」です。しかし、診断士の多くは長期的な経営計画や組織改革といった、効果が見えるまでに年単位の時間がかかる提案をしがちです。



もちろん、即効性のある施策など世の中にあまり存在しないので、ある程度の期間は必要となります。ただ、そのロードマップを具体的に描け、経営者を説得できる診断士がいるかというと、そう多くはないと感じています。
業界特有の実務ノウハウ:各業界には独特の商慣習や成功要因があります。例えば、飲食業なら立地選定のポイント、製造業なら効率的な生産計画の立て方、小売業なら効果的な商品陳列方法など。これらは教科書には載っていない、現場でしか学べない知識です。
しかし、診断士試験では業界横断的な一般論しか学びません。結果として「どの業界でも通用する薄い知識」しか身につかず、経営者からすると「うちの業界のことを本当に分かっているの?」という疑問を持たれてしまいます。



もちろん、「経験がないからこそ新たな提案ができる」という側面もあります。例えば、僕であれば、病院に行った場合は、美容院の成功事例の話をしたり、美容院に行った時は、化粧品販売の成功事例を話したりします。
人的ネットワークの提供:中小企業にとって、信頼できる取引先や協力者の紹介は非常に価値の高いサービスです。しかし、多くの診断士は同業者とのつながりはあっても、実際のビジネスで活用できる価値の高い人脈を持っていません。
成功しているコンサルタントは、クライアントに対して「この案件なら、○○さんを紹介します」「資金調達なら△△銀行の××さんに話を通しておきます」といった具体的な支援ができます。これこそが真の付加価値なのです。
診断士の「勉強病」という深刻な問題
診断士の世界には「勉強病」とも呼べる現象があります。これは資格取得後も継続的に勉強を続けるものの、それが実際の収入や成果に結びつかないという問題です。
セミナー依存症:多くの診断士が「スキルアップ」を名目として、次々とセミナーや研修に参加します。しかし、これらのセミナーの多くは理論中心で、実際のクライアント獲得や収入向上には直結しません。
私が観察してきた中で、セミナーに年間50万円以上投資しながら、診断士としての年収が100万円に満たない人を何人も見てきました。本来であれば、その50万円を営業活動や実際のビジネス投資に回すべきですが、「まだ勉強が足りない」という思考に陥ってしまうのです。



士業をターゲットにしたいわゆる情報商材だと、中央値で50万円くらいでしょうか。大した中身のない講座が多いですが。
資格コレクター化:診断士に加えて、さらに他の資格取得に走る人も少なくありません。ITコーディネーター、販売士、簿記などの関連資格を次々と取得しますが、結果として「器用貧乏」になってしまいます。
複数の資格を持っていることで一見すると専門性が高いように見えますが、実際には「何の専門家なのか分からない」という状況に陥りがちです。クライアントから見れば「この人は結局、何が得意なの?」という疑問を持たれてしまいます。
インプット過多、アウトプット不足:診断士の多くは知識のインプットには熱心ですが、それを実際のビジネスでアウトプットすることには消極的です。理由は明確で、失敗するリスクを恐れているからです。
しかし、コンサルタントとしての信頼は、成功事例の積み重ねによってのみ築かれます。どれだけ理論的な知識があっても、「実際にクライアントの業績を改善した」という実績がなければ、説得力を持つことはできません。
診断士業界の「エコーチェンバー現象」
診断士業界には「エコーチェンバー現象」と呼ばれる問題があります。これは同じような考えや意見を持つ人たちが集まることで、外部の客観的な視点を失ってしまう現象です。
受験者での慣れ合い:診断士受験者向けのサイトってありますよね?僕が20年近く前に、診断士を受験してた時も、そういうサイトがありました。僕は受験後にサイトの存在を知ったのですが、そこで受験生同士で語られている「輝かしい診断士像」は当時から違和感がありましたが、そのようなサイトにハマってしまった人を、我々は「入信者」と呼び、診断士の現実を知った人を「洗脳が解けた」と言ったりします(笑)。
成功事例の偏重:診断士業界では、数少ない成功事例が繰り返し紹介されます。しかし、これらの事例の多くは再現性に乏しく、特殊な条件や運に依存している場合が少なくありません。
例えば、「診断士として年収1000万円を達成」という事例があったとしても、その人が元々大手企業の役員だった、特殊な人脈を持っていた、たまたまタイミングが良かった、といった背景が語られることは稀です。



要するに、成功事例の再現性が薄いんですよ。なので、稼いでいる診断士は、事例にとらわれず自分の好き勝手にやって稼いでいる印象です。
これにより、根本的な問題点が改善されることなく、同じような課題が繰り返し発生し続けています。外部からの客観的な評価や批判に耳を傾けることで、初めて改善の道筋が見えてくるはずです。
真に価値あるコンサルタントになるための道筋
では、本当に価値のあるコンサルタントになるためには、どのような道筋を歩むべきでしょうか。成功しているコンサルタントの共通点から学ぶべき要素を整理してみます。
特定領域での圧倒的な専門性:成功しているコンサルタントは例外なく、狭い領域で圧倒的な専門性を持っています。「何でもできます」ではなく「この分野なら誰にも負けません」という明確なポジションを確立しています。
例えば、EC事業の立ち上げ専門、飲食店の多店舗展開専門、製造業のコスト削減専門など。狭い分野に特化することで、その分野での第一人者としての地位を築いています。
実績に基づく信頼性:理論的な知識ではなく、実際の成功事例に基づいて信頼を築いています。「私のアドバイスで売上が30%向上しました」「コスト削減により年間500万円の利益改善を実現しました」といった具体的な数字で成果を示しています。



僕であれば、「年商1億円くらいまでであれば、3年以内に利益を20%以上押しあげることは可能」といった感じです。中小企業は営業・マーケティングを系統立ててやっている所は少ないので、これくらいであれば、大してハードルは高くないです。
継続的な関係性の構築:一回限りのコンサルティングではなく、長期的な関係性を構築しています。クライアントの成長と共に歩み、継続的に価値を提供し続けることで、安定した収入を確保しています。
効果的なマーケティング:自分の専門性や実績を効果的に市場に伝えるマーケティングスキルを持っています。ブログ、SNS、書籍出版、講演活動などを通じて、見込み客に自分の存在を知ってもらい、信頼を築いています。
診断士業界の内部事情
診断士業界の内部には、外からは見えにくい問題が存在します。
派閥と利権構造:診断士会内部には様々な派閥があり、コネクションがないと公的業務などの案件にありつくことはできません。



今は診断士も飽和状態なので、診断協会経由で仕事を取ろうと思ったら、案件を振る権限を持った人とのコネクションは必須です。公的業務なのに、コネで採用を決めるとか、どこまで昭和なんだよ、と個人的には思いますが、実態としてそうなってるので、まぁ仕方ないですかね。
研修ビジネスの拡大:資格取得後も継続的に研修受講が必要ですが、これらの研修の多くは診断士会関係者が運営しており、一種の「内輪ビジネス」となっています。実務に本当に役立つかどうかよりも、制度的に受講が義務付けられているため、安定した収入源となっています。
新人診断士への支援不足:資格取得直後の診断士に対する実践的な支援は非常に限定的です。「自分で頑張れ」という風潮が強く、多くの新人診断士が孤立無援の状態で活動を始めることになります。



一番の課題は、「他の診断士に仕事を振るくらいの案件を持っている」診断士がほぼいないところでしょうか。だから、診断業界は、新人はほぼただ働きみたいな悪しき風習が色濃い業界でもあります。
社会情勢の変化と診断士の将来性
コロナ禍以降、ビジネス環境は大きく変化しており、診断士を取り巻く状況もさらに厳しくなっています。
リモートワークの普及:多くの企業がリモートワークを導入した結果、従来型の対面でのコンサルティングスタイルでは対応が困難になっています。オンラインでのコンサルティングスキルを持たない診断士は、競争力を失いつつあります。
DXの加速:企業のデジタル化が急速に進んでいますが、多くの診断士はこの分野に対応できていません。結果として、IT系のコンサルタントに案件を奪われる状況が続いています。
補助金制度の変化:診断士の重要な収入源の一つである補助金申請代行業務ですが、制度の電子化や申請要件の複雑化により、専門性の低い診断士は対応が困難になっています。
AI・ChatGPTの影響:簡単な経営相談や計画書作成などは、AIツールで対応可能になりつつあります。付加価値の低いサービスを提供している診断士は、今後さらに厳しい状況に置かれることが予想されます。



診断士に限った話ではないですが、AIやDXの対応はかなり遅れています。診断士はおじいちゃんが多いので、デジタルに対応できていない感じです。そのおじいちゃんしか周りにいないので、若手もそこまで対応できてはいないですね。
理由4:試験内容と実務のギャップが深刻|机上の空論ばかり
試験で問われる知識の実用性の低さ
中小企業診断士試験では確かに幅広い分野の知識が問われます。しかし、これらの知識が実際のコンサルティング現場でどれだけ役に立つかというと、正直なところ疑問です。
試験勉強で学ぶ内容の多くは教科書的な理論であり、現実のビジネスの複雑さや泥臭さとは程遠いものです。例えば、財務分析の手法は学びますが、実際の中小企業の財務状況は帳簿が不完全だったり、現金商売の比重が高かったりして、教科書通りの分析ができないことがほとんどです。



例えば会計で言うと、税理士が適当な法人税申告をしていたり、経理が平気で間違った勘定科目使って変な会計処理していたり、銀行からの営業に負けて変な借入しちゃっているとか、日常茶飯事です。帳簿がキチンとしている企業の方がマレなくらい、結構テキトーです。
現場で求められるスキルとの乖離
実際のコンサルティング現場で最も重要なのは以下のようなスキルです:
- 傾聴力:経営者の本音を引き出す能力
- 提案力:具体的で実行可能な改善策を示す能力
- 実行支援力:提案を実際に実行に移すまでサポートする能力
- 業界知識:特定の業界の事情を深く理解している専門性
しかし、診断士試験ではこれらのスキルは一切問われません。結果として、資格は取得したものの「実際に何をすればいいのか分からない」という診断士が量産されています。
2次試験の問題点
特に2次試験の事例問題は、現実離れした設定が多く、実務とのギャップが顕著です。試験では「正解」が存在しますが、現実のコンサルティングに正解はありません。クライアントの状況や業界特性、経営者の価値観などを総合的に考慮して、最適解を見つけ出す能力が求められます。
試験では論理的な思考プロセスを重視しますが、実務では人間関係や感情的な要素が大きく影響することが多い。この違いを理解せずに診断士になった人は、現場で大きく戸惑うことになります。
理由5:予備校のポジショントーク|資格ビジネスの餌食
予備校業界の利益構造
中小企業診断士の予備校業界は巨大なビジネスです。大手予備校だけでも年間数十億円の売上を上げており、この利益を維持するためには常に新たな受講生を獲得する必要があります。
そのため、予備校は診断士の魅力を過大に宣伝し、現実の厳しさには触れません。「独立可能」「高収入」「やりがいのある仕事」といったキラーワードを並べて、夢を売っているのが実情です。
合格者の声に隠された真実
予備校のパンフレットやウェブサイトには「合格者の声」として成功事例が掲載されています。しかし、これらは慎重に選ばれた極めて少数の事例であり、全体像を表していません。
実際には、以下のような声の方が圧倒的に多いのが現実です:
- 「思っていた仕事内容と全然違う」
- 「資格を取ったけど、何をすればいいか分からない」
- 「案件が全然取れない」
- 「結局、元の仕事を続けている」



僕もそうでしたし、周りの診断士も同じ意見ですけど、「診断士を取ってから何をしたら良いか分からない」と言う人が大半です。予備校などの話は「まずは診断協会などに入ってコネクションを作りましょう」程度の話しかなく、診断士の本当の所は分からずじまいでした。
継続的な収益モデル
予備校にとって診断士は「リピーター」を生み出しやすい資格でもあります。資格取得後も実務研修、継続教育、各種セミナーなどで継続的に収益を上げることができます。
私自身も資格取得後、「スキルアップ」を名目として追加で数十万円を予備校に支払いました。しかし、振り返ってみると、これらの研修で学んだ内容も結局は実務であまり役に立たないものばかりでした。
メディアとの癒着
経営関連の雑誌やウェブメディアでも、診断士関連の記事が頻繁に掲載されます。しかし、これらの多くは予備校からの広告収入に依存しており、客観的な視点での分析は期待できません。
「診断士として独立成功」といった記事も、よく読むと診断士の資格よりも、その人の元々の実力や人脈が成功の要因であることが分かります。
それでも診断士を目指すべき人とは?
ここまで厳しい現実をお伝えしてきましたが、それでも中小企業診断士が意味を持つ人もいます。以下のような方には一定の価値があるかもしれません:
企業内での昇進材料として
一部の大企業では、管理職昇進の際に診断士などの資格取得が評価される場合があります。ただし、これも企業の方針次第であり、事前に確認が必要です。
知識の体系化として
既に経営コンサルタントとして活動している方が、知識を体系化する目的で取得するのであれば意味があります。ただし、この場合も資格取得が目的ではなく、あくまで手段として捉えるべきです。
趣味・教養として
純粋に経営学に興味があり、趣味として学習したい方には価値があります。ただし、投資対効果を考えると、独学の方が効率的かもしれません。
より価値のある選択肢とは?
もしあなたが本当に経営コンサルタントとして成功したいなら、診断士以外の道を検討することをお勧めします。
実務経験の蓄積
最も重要なのは実務経験です。特定の業界で深い経験を積み、実績を作ることが何よりも価値があります。診断士の勉強に1000時間を費やすなら、その時間を実際のビジネス経験に充てる方が遥かに有益です。
デジタルマーケティングスキルの習得
現代のビジネスにおいて、デジタルマーケティングのスキルは極めて重要です。SEO、SNS運用、Web広告運用などのスキルは、中小企業が切実に求めており、高い報酬を期待できます。
プログラミングスキルの習得
IT化が遅れている中小企業にとって、システム導入や業務効率化の支援は喫緊の課題です。プログラミングスキルがあれば、より具体的で実効性の高いサービスを提供できます。
業界特化の専門家になる
特定の業界に特化して専門性を高めることで、その分野での権威となることができます。例えば、飲食業界専門、製造業専門、EC事業専門などです。
まとめ:現実を受け入れて賢い選択を
中小企業診断士という資格について、予備校では絶対に語られない現実をお伝えしました。
この資格が多くの人にとって意味がない理由は以下の通りです:
- 圧倒的に稼げない現実:大多数の診断士の年収は300万円台
- 権威性の低さ:一般認知度が低く、企業からの評価も期待できない
- 競合過多:供給過多で差別化が困難
- 実務とのギャップ:試験内容と現場で求められるスキルの乖離
- 予備校のポジショントーク:資格ビジネスの餌食になっている
もしあなたが本当に経営コンサルタントとして成功したいなら、診断士の資格取得よりも、実務経験の蓄積や市場価値の高いスキルの習得に時間と費用を投資することをお勧めします。
資格に頼らず、実力で勝負する。それが真の意味での経営コンサルタントへの道です。あなたの貴重な時間と費用を、本当に価値のあることに投資してください。