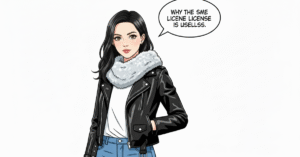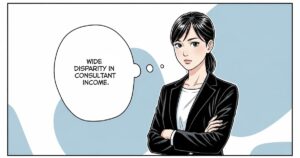なぜ中小企業診断士はやめとけと言われるのか?診断士が本音で語る


インターネットで「中小企業診断士」と検索すると、「中小企業診断士 やめとけ」「中小企業診断士 意味ない」「中小企業診断士 食えない」といった、ネガティブな検索候補が次々と表示されます。
なぜ、国家資格である中小企業診断士について、これほど否定的な意見が多いのでしょうか。
私は中小企業診断士として10年以上活動してきました。その間、多くの診断士仲間と出会い、成功事例も失敗事例も目の当たりにしてきました。そして、予備校や資格学校が決して語らない「診断士の現実」を、身をもって経験してきたのです。
この記事では、中小企業診断士を目指している方、すでに資格を取得したけれど活用方法に悩んでいる方に向けて、業界の実態を包み隠さずお伝えします。
きれいごとは一切言いません。診断士の世界の光と影、両方をしっかりとお見せします。
中小企業診断士の年収の実態
平均年収780万円の真実
日本中小企業診断士協会が公表している「中小企業診断士活動状況アンケート調査」によると、診断士の平均年収は約780万円とされています。
「なんだ、結構高いじゃないか」
そう思われたかもしれません。でも、この数字には大きな落とし穴があります。
まず、この調査に回答しているのは、主に診断士協会に所属している「活動的な診断士」です。つまり、診断士として何らかの形で活動し、収入を得ている人たちが中心なのです。
資格を取得したものの、診断士としての活動をほとんどしていない「ペーパー診断士」は、そもそもこの調査に参加していない可能性が高いでしょう。
さらに重要なのは、この780万円という数字が「診断士業務のみの収入」ではないということです。
診断士収入の内訳を見てみると
同調査をさらに詳しく見ていくと、診断士の収入構造が見えてきます。
年間診断士収入100万円未満:約40%
これが現実です。診断士の約4割は、診断士業務での年収が100万円に満たないのです。月収に換算すると8万円程度。これでは到底生活できません。
年間診断士収入100万円~300万円:約20%
この層を合わせると、全体の約6割が年収300万円未満ということになります。
年間診断士収入1000万円以上:約10%
確かに高収入を得ている診断士も存在します。しかし、それは全体の1割程度に過ぎません。
下記記事で、中小企業診断士の年収については詳しく解説しています。


なぜこんなに収入格差があるのか
診断士の収入格差が激しい理由は、主に以下の3つです。
1. 企業内診断士が多数を占める
診断士資格保有者の約7割は企業に勤務する「企業内診断士」です。彼らの主な収入源は勤務先からの給与であり、診断士としての活動は副業程度にとどまります。
2. 独立診断士の営業力の差
独立している診断士でも、営業力や人脈の差によって収入に大きな開きが生じます。診断士の資格があっても、仕事を獲得できなければ収入にはつながりません。
3. 専門分野の有無
IT、製造業、小売業など、特定の業界に精通している診断士は高収入を得やすい傾向にあります。一方、専門性が曖昧な診断士は価格競争に巻き込まれ、低単価の仕事しか受注できません。
「診断士は食えない」と言われる理由
仕事がない現実
「中小企業診断士の資格を取ったのに、仕事が全然ない」
こんな悩みを抱える診断士は少なくありません。



診断士同士でも、2024年くらいから「とにかく案件がなくなった」という話は良く聞きます。
なぜ国家資格を持っているのに仕事がないのでしょうか。
理由1:診断士の供給過多
2024年現在、中小企業診断士の登録者数は約3万人。毎年1000人以上が新たに診断士となっています。一方で、診断士を必要とする中小企業の数は限られています。



診断士の稼ぐ案件として大半を占めているのは「補助金の申請サポート」と「公的業務」です。ただ、両方とも、市場に大量の診断士が溢れていることと、言葉を選ばずに言えば、そこまで専門知識やノウハウが求められる訳ではないので、競争過多になっています。
理由2:中小企業の予算不足
そもそも中小企業の多くは、コンサルティングに高額な費用を支払う余裕がありません。「月50万円でコンサルティングします」と言っても、そんな予算を確保できる中小企業はごくわずかです。
理由3:信頼関係の構築が困難
中小企業の経営者は、見ず知らずの診断士よりも、長年の付き合いがある税理士や取引先の紹介を重視します。資格があるだけでは信頼を得られません。
公的業務の実態
「公的な仕事があるから大丈夫」と思われるかもしれません。確かに、商工会議所や中小企業支援センターなどから診断士向けの仕事はあります。
しかし、これらの仕事の単価は驚くほど低いのが現実です。
- 経営相談員:日当1万円~2万円
- セミナー講師:1回3万円~5万円
- 補助金申請支援:成功報酬10%~20%
しかも、これらの仕事は常にあるわけではありません。月に数回程度しか依頼がないことも珍しくありません。



そもそも、公的業務は案件自体がとても少ないです。なので、その少ない案件に大量の診断士が応募します。なので、案件を割り振る人間にコネがないと、まず採用されることはありません。
独立開業の厳しさ
「それなら独立してコンサルティング会社を立ち上げよう」
そう考える診断士も多いでしょう。しかし、独立開業にも大きな壁があります。
初期投資と運転資金
事務所の賃貸料、パソコンやソフトウェア、名刺や販促物の作成など、開業には最低でも100万円以上の初期投資が必要です。さらに、収入が安定するまでの生活費も確保しなければなりません。



上記はあくまで経費のみで、実際に、本当にコンサルティングとして軌道に乗せるなら、営業・マーケティング費用で最低300万円は必要かと思います。
営業活動の難しさ
診断士の資格は営業ツールにはなりません。実際のコンサルティング実績や成功事例がなければ、クライアントを獲得することは困難です。
資格維持にかかるコスト
見落としがちな維持費用
中小企業診断士の資格を維持するには、意外とコストがかかります。
更新要件
診断士資格は5年ごとに更新が必要です。更新するためには以下の要件を満たす必要があります。
- 実務従事:5年間で30日以上
- 理論政策更新研修:5回以上受講
実務従事の確保
企業内診断士の場合、診断士としての実務経験を積む機会が限られています。そのため、有料の実務従事機会を購入することになります。
- 実務従事の参加費:1回3万円~5万円
- 5年間で最低6回は必要:18万円~30万円
理論政策更新研修
研修の受講にも費用がかかります。
- 1回の受講料:6,000円~10,000円
- 5年間で5回受講:3万円~5万円
診断士協会の会費
多くの診断士は都道府県の診断士協会に所属しています。
- 入会金:3万円~5万円
- 年会費:5万円~8万円
5年間で計算すると、協会費だけで28万円~45万円かかります。
トータルコストを計算すると
5年間の資格維持にかかる最低限のコストを合計すると:
- 実務従事費:18万円~30万円
- 研修費:3万円~5万円
- 協会費:28万円~45万円
合計:49万円~80万円
年間にすると約10万円~16万円。これだけのコストをかけて資格を維持する価値があるかどうか、真剣に考える必要があります。



診断士の維持費については、下記にもまとめているので、ご参考ください。


診断士を取り巻く業界構造の問題
予備校ビジネスの実態
「中小企業診断士はやめとけ」という声が上がる一方で、予備校や資格学校は相変わらず「診断士の明るい未来」を謳い続けています。なぜでしょうか。
予備校の収益構造
大手資格予備校にとって、診断士講座は重要な収益源です。
- 受講生1人あたりの売上:25万円~35万円
- 年間受講生数:数千人規模
- 診断士講座の年間売上:数億円~十数億円
この巨大なビジネスを維持するためには、「診断士の夢」を売り続ける必要があるのです。
合格者の声の偏り
予備校のパンフレットには、華々しい成功事例が並びます。
「診断士になって独立し、年収2000万円を達成!」 「大手企業から引く手あまたのコンサルタントに!」
しかし、これらは全体のごく一部の特殊事例です。失敗事例や苦労している診断士の声が掲載されることはありません。
講師の利害関係
予備校の講師の多くは、診断士資格を持つ人たちです。彼らにとって、講師業は重要な収入源。「診断士なんて意味がない」とは口が裂けても言えません。



特に、診断士が飽和して潮目が変わった2024年以降の話は、診断士予備校にとっては不都合な話なので、彼らの口から語られることはないと思います。
診断士協会の構造的問題
中小企業診断士協会も、似たような構造的問題を抱えています。
会員数維持のプレッシャー
協会の運営は会費収入に依存しています。そのため、診断士の厳しい現実を公表することは、会員離れにつながりかねません。
既得権益の保護
協会の理事や幹部の多くは、診断士として成功している人たち。彼らにとって、新規参入者が増えることは競争激化を意味します。表向きは「診断士の地位向上」を謳いながら、実質的には既存会員の利益を優先する傾向があります。



一番の問題は、診断士の中に、他に仕事を振れるほど稼いでいる人はほぼいないことです。自分の稼ぎで精一杯なので、他の診断士の利益のことなど考えている余裕がないのが現実かと思います。
補助金ビジネスの功罪
近年、診断士の仕事として増えているのが「補助金申請支援」です。
補助金バブルの実態
- ものづくり補助金
- 事業再構築補助金
- IT導入補助金
これらの補助金申請を支援することで、成功報酬を得る診断士が増えています。一見、良いビジネスモデルに見えますが、問題も多いのです。
補助金依存のリスク
補助金は政策次第でいつなくなるか分かりません。補助金ビジネスに依存している診断士は、政策変更により一気に収入を失うリスクがあります。



これが2024年に起こったことです。政策の転換があり、補助金の予算は抑えられれ、審査は厳しくなりました。それにより、補助金を中心にやっている診断士の収入は1/3になるなど、激減しました。
診断士試験の投資対効果
試験対策にかかる費用と時間
中小企業診断士試験は、難関国家資格として知られています。合格までにかかる費用と時間を見てみましょう。
予備校費用
- 大手予備校の通学コース:25万円~35万円
- 通信教育コース:15万円~25万円
- 模擬試験や直前対策:5万円~10万円
学習時間
一般的に、診断士試験の合格には1000時間~1500時間の学習が必要と言われています。1日3時間勉強したとしても、1年~1年半かかる計算です。
機会費用
この学習時間を時給2000円で換算すると、200万円~300万円の機会費用が発生していることになります。
合格率の現実
- 1次試験合格率:約20%~30%
- 2次試験合格率:約20%
- ストレート合格率:約4%~6%
つまり、100人が勉強を始めても、ストレートで合格できるのは4人~6人程度。多くの受験生は複数年かけて合格を目指すことになります。
投資を回収できるか
仮に予備校費用30万円、2年間の学習で合格したとしましょう。機会費用を含めると、400万円以上の投資をしたことになります。
この投資を診断士としての収入で回収するには、どれくらいかかるでしょうか。
年間の診断士収入が100万円の場合、単純計算で4年以上。しかも、これは維持費用を考慮していません。
多くの診断士にとって、資格取得は「ペイしない投資」になっているのが現実です。
それでも診断士を目指す価値はあるか
ここまでネガティブな話ばかりしてきましたが
「じゃあ、診断士なんて目指す価値はないの?」
そう思われたかもしれません。確かに、収入面だけを見れば、診断士資格は魅力的とは言えません。しかし、診断士資格には収入以外の価値もあります。
体系的な経営知識の習得
診断士試験の学習を通じて、経営戦略、マーケティング、財務会計、生産管理など、幅広い経営知識を体系的に学べます。これは企業内で働く上でも大きな武器になります。
人脈の形成
診断士協会や研究会を通じて、様々な業界の専門家とネットワークを構築できます。この人脈は、ビジネスチャンスにつながることもあります。



診断士になって「仕事をもらう」という場合は、全く割に合わない資格となりましたが、「自分で仕事を取ってきて、知見を使う」という意味では、診断士コミュニティーはそれなりに使えます。上場企業で活躍されている人なども多いので、そういう知見を使えたりします。
自己研鑽の証
難関資格に挑戦し、合格したという事実は、自己研鑽に励む姿勢の証明になります。
診断士資格を活かすための現実的な戦略
診断士資格を取得するなら、以下のような現実的な戦略を持つことが重要です。
1. 本業との相乗効果を狙う
診断士資格を「独立の手段」ではなく、「本業を強化するツール」として活用する。例えば、営業職なら顧客への提案力向上、管理職なら部門経営の改善など。
2. 専門分野を明確にする
「何でもできる診断士」ではなく、「○○に強い診断士」を目指す。IT、製造業、飲食業など、特定分野での専門性を磨く。
3. 副業から始める
いきなり独立するのではなく、週末コンサルなど副業から始めて、実績と顧客基盤を築く。
4. 他の資格やスキルと組み合わせる
診断士資格単体ではなく、税理士、社労士、ITスキルなど、他の専門性と組み合わせて差別化を図る。
診断士業界の将来展望
AIとコンサルティング業務
今後、AI技術の発展により、診断士の仕事はどう変わるでしょうか。
AIに代替されやすい業務
- 財務分析
- 市場調査
- 競合分析
- 定型的な改善提案
これらの業務は、AIツールによって効率化され、単価が下がる可能性があります。
人間の診断士が強みを発揮できる業務
- 経営者の心理的サポート
- 組織文化の変革
- 利害関係者の調整
- 創造的な戦略立案
感情や人間関係が絡む領域では、人間の診断士の価値は残り続けるでしょう。
中小企業支援政策の動向
政府の中小企業支援政策も、診断士の需要に大きく影響します。
現在は補助金や助成金が充実していますが、財政状況によっては縮小される可能性もあります。公的な仕事に依存しすぎるのは危険です。
まとめ:診断士を目指す前に考えるべきこと
冷静な自己分析が必要
中小企業診断士を目指す前に、以下の点を冷静に分析してください。
1. 目的は何か
- 収入アップが目的なら、他の選択肢も検討すべき
- 知識習得が目的なら、独学やMBAも選択肢
- 人脈形成が目的なら、業界団体や勉強会でも可能
2. 投資できる時間と費用
- 1000時間以上の学習時間を確保できるか
- 50万円以上の費用を投資できるか
- 資格取得後も継続的に投資できるか
3. 活用プランはあるか
- 具体的にどう活用するかイメージできているか
- 専門分野や差別化ポイントは明確か
- 現実的な収支計画は立てられるか
診断士資格の本当の価値
診断士資格の本当の価値は、「資格そのもの」ではなく「資格を通じて得られる知識・経験・人脈」にあります。
資格を取れば自動的に仕事が来る、収入が上がる、という幻想は捨てるべきです。
診断士資格は「スタートライン」に過ぎません。そこから先は、自分の努力と工夫次第です。
最後に伝えたいこと
この記事では、診断士の厳しい現実を包み隠さずお伝えしました。
「診断士はやめとけ」という意見が多いのは、予備校が語る理想と現実のギャップが大きすぎるからです。
しかし、現実を知った上で、それでも診断士を目指すのであれば、それは価値ある選択だと思います。
大切なのは、幻想を抱かず、現実的な計画を立て、着実に実行することです。
診断士として生き残るための具体的戦略
成功している診断士の共通点
厳しい現実の中でも、確実に成功している診断士は存在します。彼らには共通点があります。
1. 診断士になる前から専門性を持っていた
- 元大手企業の事業企画部門責任者
- IT企業でのプロジェクトマネジメント経験者
- 製造業での生産管理のスペシャリスト
- 金融機関での企業融資担当者
これらの人々は、診断士資格を「既存の専門性を証明するツール」として活用しています。
2. 営業力とコミュニケーション能力が高い
成功している診断士は、例外なく高い営業力を持っています。
- 経営者の悩みを引き出す傾聴力
- 複雑な経営課題を分かりやすく説明する能力
- 人間関係を構築する社交性
- 断られても諦めない粘り強さ
3. 収入源を複数持っている
「診断士業務だけで食べている」人はごくわずか。成功している診断士の多くは、複数の収入源を持っています。
- 企業研修講師
- 執筆活動(書籍、雑誌寄稿)
- オンラインコンテンツ販売
- 顧問契約
- 補助金申請支援
失敗する診断士のパターン
逆に、失敗する診断士にも共通のパターンがあります。
1. 資格を取れば仕事が来ると思っている
「診断士の看板があれば、自然と仕事が舞い込んでくる」
この考えは完全に間違いです。資格は最低限の知識を証明するものに過ぎません。
2. 専門性が曖昧
「経営全般のコンサルティングができます」
このような漠然としたアピールでは、クライアントに選ばれません。
3. 実務経験が不足している
教科書的な知識しかない診断士は、経営者から信頼されません。
「そんな理論は知っている。でも、うちの会社では使えない」
こう言われて終わりです。
診断士×○○の可能性
診断士資格単体では差別化が難しい今、「診断士×○○」という組み合わせが重要になっています。
診断士×デジタルマーケティング
中小企業のデジタル化支援は今後も需要が見込まれます。Web集客、SNS活用、ECサイト構築などの知識があれば、強力な武器になります。
診断士×事業承継
後継者不足に悩む中小企業は増える一方。事業承継の知識と経験があれば、高単価の案件を獲得できる可能性があります。
診断士×SDGs
環境経営やSDGsへの取り組みを支援できる診断士は、今後需要が高まるでしょう。
診断士×地域特性
観光業、農業、伝統産業など、地域特有の産業に精通した診断士は、その地域で唯一無二の存在になれます。
これから診断士を目指す人へのアドバイス
まず自問自答すべき5つの質問
診断士を目指す前に、以下の質問に正直に答えてください。
1. なぜ診断士になりたいのか?
「なんとなくカッコいいから」では続きません。明確な目的意識が必要です。
2. 診断士以外の選択肢は検討したか?
MBA、税理士、社労士、行政書士など、他の選択肢と比較検討しましたか?
3. 1000時間の学習時間を確保できるか?
家族との時間、趣味の時間を犠牲にする覚悟はありますか?
4. 資格取得後の具体的なプランはあるか?
「とりあえず資格を取ってから考える」では遅すぎます。
5. 失敗した場合のリスクは許容できるか?
時間とお金を投資して、リターンが得られない可能性も考慮していますか?
診断士試験の効率的な学習方法
それでも診断士を目指すと決めたなら、効率的な学習方法をお教えします。
1. 独学か予備校か
- 独学のメリット:費用が安い(テキスト代のみ)
- 独学のデメリット:モチベーション維持が困難、情報収集に時間がかかる
- 予備校のメリット:体系的なカリキュラム、仲間ができる
- 予備校のデメリット:費用が高い、講義についていけないと脱落
2. 1次試験対策のポイント
- 7科目を均等に学習するのではなく、得意科目で稼ぐ戦略
- 過去問を徹底的に分析し、出題パターンを把握
- 暗記科目は直前期に集中
3. 2次試験対策の要点
- 事例問題の「型」を身につける
- 模範解答を暗記するのではなく、思考プロセスを理解
- 添削を受けて、自分の弱点を把握
診断士資格の活かし方・実例集
ケース1:企業内診断士として活躍するAさん
大手メーカーの営業部門で働くAさんは、診断士資格取得後、社内の新規事業開発プロジェクトに抜擢されました。診断士として学んだ知識を活かし、事業計画を策定。プロジェクトの成功により、部長に昇進しました。
ケース2:週末起業で成功したBさん
IT企業でエンジニアとして働くBさんは、診断士資格取得後、週末だけ中小製造業のIT化支援を行っています。本業の知識と診断士のスキルを組み合わせ、月20万円の副収入を得ています。
ケース3:セカンドキャリアとして活躍するCさん
大手企業を早期退職したCさんは、診断士資格を取得し、地元の商工会議所の経営指導員として再就職。年収は下がりましたが、地域貢献できる仕事にやりがいを感じています。
最後に:「やめとけ」を乗り越えて
この記事では、中小企業診断士の厳しい現実を赤裸々にお伝えしてきました。
確かに、「診断士はやめとけ」という意見には一理あります。甘い期待を抱いて診断士を目指せば、必ず失望することになるでしょう。
しかし、現実を直視した上で、戦略的に診断士資格を活用すれば、キャリアの可能性は確実に広がります。
大切なのは、診断士資格を「ゴール」ではなく「スタート」と捉えることです。
資格取得後も継続的に学び、実践し、ネットワークを広げ、専門性を磨き続ける。この努力を続けられる人だけが、診断士として成功できるのです。
「中小企業診断士はやめとけ」
この言葉は、安易な気持ちで診断士を目指す人への警告です。しかし、覚悟を持って挑戦する人にとっては、むしろチャンスかもしれません。
なぜなら、多くの人が「やめとけ」と言って諦める中で、本気で取り組む人には、より多くの機会が巡ってくるからです。