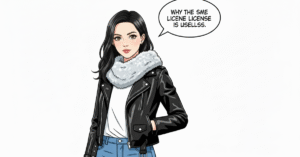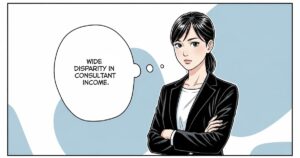中小企業診断士で食えない人の共通点|成功者との決定的な違い

- 中小企業診断士の資格を取得したのに、思うように稼げない……
- 周りの診断士も同じような状況で、本当に食べていけるのか不安……
- 予備校では「年収1000万円も夢じゃない」と言われたのに、現実は厳しすぎる……
そんな悩みを抱えているあなたは、決して珍しい存在ではありません。実際、中小企業診断士の資格を持ちながら「食えない」状況に陥っている人は想像以上に多いのが現実です。
しかし、一方で同じ資格を持ちながら年収1000万円以上を稼ぎ続ける診断士も確実に存在します。この記事では、食えない診断士と成功する診断士の決定的な違いを徹底解説します。
この記事を読めば「なぜ多くの診断士が稼げないのか」「成功する診断士の共通点とは何か」が全て分かります。
予備校が決して教えない診断士の厳しい現実と、その中で成功するための具体的な戦略をお伝えします。詳しくは「中小企業診断士はやめとけってホント?」もあわせてご覧ください。
【衝撃】中小企業診断士の90%が年収500万円以下の現実
予備校が決して語らない診断士の収入実態
中小企業診断士の予備校やスクールでは「独立すれば年収1000万円以上も可能」「コンサルタントとして高収入が期待できる」といった甘い宣伝文句が並んでいます。しかし、これは氷山の一角の成功事例を大げさに宣伝しているに過ぎません。
実際の調査データを見ると、中小企業診断士の約90%が年収500万円以下という厳しい現実があります。独立開業した診断士に限定すると、年収300万円以下が過半数を占めるという調査結果もあります。
「食えない診断士」が量産される理由

なぜこれほど多くの診断士が「食えない」状況に陥るのでしょうか。最大の原因は、中小企業診断士が「定年退職したあとに、お小遣い程度に企業コンサルティングをやりたい」という人が多い資格だからというのはあります。
実際に中小企業診断協会の調査データを見ると、この実態が浮き彫りになります。診断士の年齢構成は50歳代が最も多く27.21%、次いで40歳代が26.48%、60歳代が21.55%となっています。
つまり、40歳代から60歳代だけで実に75.24%を占めているのです。
この年齢構成が示しているのは、多くの診断士が「第二のキャリア」として資格を取得しているという現実です。40-50代でサラリーマンとしてのキャリアが一段落し、「将来の備えとして」「定年後の生きがいとして」診断士資格を取得する人が圧倒的多数なのです。
しかし、ここに大きな問題があります。「お小遣い程度に稼げればいい」という意識の人が市場に大量に参入することで、コンサルティング料金の相場が大幅に下落してしまうのです。本格的に診断士業で生計を立てたいと考えている人も、この低価格競争に巻き込まれてしまいます。
さらに深刻なのは、60歳代以上が30%以上も存在することです。これらのシニア診断士の多くは年金収入があるため、極端に安い料金でもコンサルティングを引き受けてしまいます。「社会貢献のため」「生きがいのため」という理由で、採算を度外視した価格設定をする人も少なくありません。



もう年金もらっている人からすれば、それこそ数万円でも稼げれば良いわけで、診断士業界のフィーが安い原因に直結していると思います。
このような市場環境では、真剣に診断士業で生計を立てようとする人にとって非常に厳しい状況になります。「副業・趣味レベル」の診断士と「本業」の診断士が同じ土俵で競争することになり、価格競争で劣勢に立たされてしまうのです。



次の原因として、資格取得と実際のビジネススキルが全く別物だということを、頭では分かっていながら、あまり理解していないことです。
診断士試験では財務分析や経営戦略の理論を学びますが、実際のコンサルティング現場で求められるのは「クライアントの売上を上げる」「コストを削減する」といった即効性のある成果です。理論と実践の間には大きなギャップがあります。
さらに、診断士になったとしても「営業」「集客」「単価設定」「継続的な学習」といったビジネス運営の基本スキルが身についていない人がほとんどです。どんなに優秀な知識を持っていても、クライアントに見つけてもらえなければ収入は0円です。
あとは、診断士取る人は、上場企業の人なども結構います。年を重ねた上場企業の人だと、そもそも、中小企業などを相手にする商売に疎い人も多いので、その辺りも、稼げてない診断士が量産される原因かと思います。
診断士資格だけでは稼げない時代の到来
現在は「診断士」という肩書きだけでクライアントが集まる時代ではありません。企業側も情報収集能力が高まり、本当に成果を出せるコンサルタントかどうかを厳しく見極めるようになっています。
また、AI技術の発達により、従来の診断士が行っていた財務分析や市場調査の多くが自動化されています。単純な分析業務では差別化が困難になり、より高度な付加価値を提供できなければ生き残れない時代になりました。
このような環境変化の中で、従来通りの「資格があるから大丈夫」という考えでは確実に淘汰されてしまいます。



AI時代になると、知識はもはや何の強みにもなりません。診断士だけではなく、弁護士、会計士、税理士なども、急速にニーズが減ってきています。近い将来、これら士業の9割は、実質、要らなくなるでしょうね。
下記記事で、中小企業診断士の年収については詳しく解説しています。


中小企業診断士で食えない人の5つの共通点
①資格取得すれば案件があると思っている
食えない診断士の最大の共通点は、「資格取得すれば多少は案件がある」と勘違いしていることです。資格を取得して、例えば診断士協会などに所属すれば、案件は多少は貰えると考えている人は多いかと思います。



これは、予備校や診断士協会のポジショントークの影響も大きいかと思います。ただ、実態としては、協会内で案件はゼロではないですが、熾烈な競争があるレッドオーシャンの案件ばかりです。しかも、基本、フィーは安いです。
確かに、診断協会の有力者とコネクションを持てば、そこから案件があることはあります。ただ、実態として、診断協会に所属している診断士の中で、他人に仕事を回せるほど案件を持っている診断士はほぼいないので、案件を餌に、体良くタダ働き、もしくはほぼタダに近いフィーで働かされる新人は多いです。
②独立開業すれば自動的に稼げると勘違いしている
多くの食えない診断士が抱いている幻想が「独立すれば自動的にクライアントが集まる」という考えです。サラリーマン時代は会社が営業や集客を行ってくれましたが、独立後は全て自分で行わなければなりません。
独立開業は「経営者になる」ということです。コンサルティングスキルだけでなく、営業、マーケティング、財務管理、人事管理など、経営に関わる全ての業務を習得する必要があります。
特に営業・集客スキルの不足は致命的です。どんなに優秀なコンサルタントでも、クライアントに認知されなければ仕事は発生しません。多くの診断士が「営業は苦手だから」と避けて通ろうとしますが、これでは絶対に成功できません。



営業も、モノを売る営業とサービスを売るコトを売る営業は手法などが少し違います。今までモノを売ってきた営業が診断士を取って独立したけど、コンサルというコトはさっぱり売れないということは良く起こります。
③営業・集客スキルが皆無
診断士試験では営業や集客について学ぶ機会がほとんどありません。そのため、多くの診断士が「良いサービスを提供すれば自然とクライアントが集まる」という幻想を抱いています。
しかし現実は正反対で、優秀なコンサルタントほど営業・集客に力を入れています。なぜなら、どんなに素晴らしいサービスでも、相手に伝わらなければ価値を認めてもらえないからです。
成功している診断士は、コンサルティング時間の30-50%を営業・集客活動に使っています。セミナー開催、ブログ執筆、SNS発信、人脈作りなど、常に見込み客との接点を作り続けています。



特に、診断士でビジョンを語れる人はほぼいないので、その辺りがコンサルを売る営業に苦戦している原因かと思います。自分もお客さんに対してもビジョンを示せないと、見透かされちゃいますので。
④専門性が浅く差別化できていない
食えない診断士の多くが「何でも屋」になってしまっています。「経営全般のことなら何でも相談に乗ります」というスタンスでは、クライアントから見て選ぶ理由がありません。
現在のコンサルティング市場では、深い専門性を持った「スペシャリスト」が圧倒的に有利です。「IT導入支援なら○○さん」「人事制度構築なら△△さん」というように、特定分野でのポジションを確立することが重要です。
専門性を深めるためには、特定の業界や機能に絞り込み、その分野で圧倒的な実績と知識を積み重ねる必要があります。浅く広い知識よりも、狭く深い専門性の方が高単価で仕事を受注できます。



その点、診断士は上場企業出身の人が多く、基本ジェネラリストなので、コンサルサービを売るには、スタートから不利な場合が多いです。
⑤維持費やコストを軽視している
診断士資格を維持するためには、年会費、継続的な研修費用、更新費用など、年間20万円以上のコストが発生します。さらに独立した場合は、事務所家賃、通信費、営業経費、税理士費用なども必要になります。
しかし、多くの食えない診断士がこれらのコストを甘く見積もっています。年収300万円でも実際の手取りは200万円以下になることも珍しくありません。サラリーマン時代と同じ生活水準を維持するためには、想像以上の売上が必要なのです。
成功する診断士は事業計画をしっかりと立て、必要なコストを全て計算した上で目標売上を設定しています。「なんとなく独立すれば稼げるだろう」という甘い考えでは確実に失敗します。
食えない診断士が陥る「3つの罠」
罠①:診断士同士の馴れ合いで成長が止まる
多くの食えない診断士が陥る最初の罠が、診断士協会や同業者コミュニティでの「馴れ合い」です。同じような境遇の診断士同士で集まり、愚痴を言い合ったり、慰め合ったりしているうちに、現実逃避の温床になってしまいます。
診断士の勉強会や交流会では「理論的な議論」に時間を費やすことが多く、実際のビジネス成果につながる活動が軽視されがちです。参加者同士で「勉強している感」を味わうことで満足してしまい、クライアント獲得や売上向上といった本来の目的から遠ざかってしまいます。



研究会や交流会も、「おままごとレベル」の内容であることも多く、何となく専門家になったつもりになれちゃう点もよくないところです。診断士業界は「自称○○に詳しい人」がいっぱいいます。
さらに問題なのは、成功している診断士ほどこのようなコミュニティに参加しないことです。本当に稼いでいる診断士は、クライアントとの時間や新規開拓に集中しており、同業者との交流に時間を割く余裕がありません。結果として、食えない診断士同士が集まって情報交換をする悪循環が生まれます。



特に、今は、数百年に一度の社会の大変革の時です。そんな中、稼いでいる診断士は、おままごとのような研究会や交流会に出席している時間などありません。
罠②:昭和ノリのままAI時代に取り残される
中小企業診断士制度は1953年に創設された歴史ある資格です。そのため、診断士コミュニティには昭和時代のビジネススタイルや価値観が根強く残っています。「根性論」「精神論」「年功序列」といった古い考え方が今でも幅を利かせているのが現実です。



僕が一番問題視しているのは「とにかく会議大好き」な点です。目的なども特に決めずにダラダラ会議を行う姿は、まさに昭和のノリです。
しかし、現代のビジネス環境はAI、DX、リモートワークなど急速にデジタル化が進んでいます。昭和の成功体験に基づいたアドバイスでは、現代の経営者から相手にされません。
特に深刻なのは、多くのベテラン診断士がデジタルマーケティングやデータ分析、AI活用などの最新手法を理解していないことです。「人間関係が全て」「足で稼ぐ営業」といった古い手法にこだわっているうちに、時代の変化についていけなくなってしまいます。
現代の経営者が求めているのは、最新のテクノロジーを活用した効率的で科学的な経営改善手法です。昭和の価値観にとらわれている診断士では、このニーズに応えることができません。



新しい現代的なマネージメント手法など、知識としてはあっても、実践的に具体的にどうしたら良いかなど語れる診断士はほぼいません。
罠③:浅い知識で専門家を名乗る危険性
診断士試験は幅広い経営知識を問う試験ですが、それぞれの分野については表面的な理解にとどまることが多いのが実情です。しかし、資格を取得すると「経営の専門家」という肩書きが与えられるため、自分の知識レベルを過大評価してしまう人が少なくありません。
実際のコンサルティング現場では、クライアントの業界特有の課題や、高度な専門知識が求められるケースが多々あります。診断士試験レベルの知識だけでは対応できない問題に直面した時、適切なアドバイスができず、クライアントの信頼を失ってしまいます。
特に危険なのは、ITやデジタル分野、法務、税務などの専門性が高い領域です。これらの分野で間違ったアドバイスをしてしまうと、クライアント企業に深刻な損害を与える可能性があります。
成功している診断士は、自分の専門領域を明確に定義し、それ以外の分野については適切な専門家を紹介するか、パートナーシップを組んで対応しています。「分からないことは分からない」と素直に認める謙虚さが、長期的な信頼関係構築には不可欠です。
一方、稼げる診断士の決定的な特徴とは
明確な専門分野を持っている
成功している診断士の最大の特徴は、明確で深い専門分野を持っていることです。「○○業界のDX支援なら△△さん」「人事制度構築なら□□さん」というように、特定分野でのポジションを確立しています。
専門分野を絞り込むことで、その分野での実績と知識が蓄積され、他の診断士との差別化が可能になります。クライアントから見ても「この分野の専門家」として認識されるため、高単価での受注が可能になります。
また、専門分野を持つことで効率的な営業活動も可能になります。ターゲット企業や業界が明確になるため、無駄な営業活動を削減し、成約率を大幅に向上させることができます。
営業・マーケティング能力が高い
成功している診断士は例外なく営業・マーケティング能力が高いのが特徴です。コンサルティングスキルと同じか、それ以上の時間とエネルギーを営業活動に投資しています。



コンサルサービスを売る営業・マーケティング力が強けば、正直、知識などは二の次です。
具体的には、定期的なセミナー開催、ブログやSNSでの情報発信、業界紙への寄稿、講演活動などを通じて、継続的に見込み客との接点を作り続けています。
また、既存クライアントからの紹介を増やすための仕組み作りも重要視しています。優良なクライアントとの関係を深め、継続的な案件受注と新規紹介の両方を実現しています。
継続的なスキルアップを怠らない
成功している診断士は、資格取得後も継続的な学習を続けています。年間数百万円を自己投資に使い、常に最新の知識とスキルを身につけています。
特に重要視しているのは、実践的なスキルの習得です。理論的な知識だけでなく、実際のコンサルティング現場で使えるツールや手法を積極的に学んでいます。
また、自分の専門分野だけでなく、隣接分野や最新のビジネストレンドについても幅広く情報収集を行っています。クライアントのニーズの変化に敏感に対応できるよう、常にアンテナを張り続けています。



診断士は勉強好きな人が多いので、セミナーや研究会にはよく顔を出しますが、努力の方向性が間違えている人は多く感じます。
複数の収入源を確保している
成功している診断士は、リスク分散のために複数の収入源を確保しています。コンサルティング業務だけでなく、研修講師、執筆活動、オンライン商品販売など、様々な収入チャネルを構築しています。
これにより、特定のクライアントに依存するリスクを回避し、安定した収入を確保しています。また、それぞれの活動が相互に宣伝効果を発揮し、全体的な知名度向上にもつながっています。
中小企業診断士の年収アップ戦略【具体的手法】
ニッチな専門分野を見つける方法
年収アップのための最初のステップは、自分だけの専門分野を見つけることです。以下の手順で専門分野を絞り込みましょう:
過去の職歴、業界経験、成功体験を全てリストアップします。他の診断士にはない独自の経験が専門分野の候補になります。
市場ニーズを調査する 自分の経験と市場ニーズが合致する分野を見つけます。Google検索、業界紙、セミナー参加などを通じて、企業が抱えている課題を調査します。また、とにかく顧客のもとに足を運んで、情報を取ることも重要です。
候補分野でセミナーを開催し、参加者の反応を確認します。問い合わせや相談が多い分野が有望です。
効果的な集客・営業手法
専門分野が決まったら、次は効果的な集客・営業手法を構築します:
- コンテンツマーケティング ブログ、YouTube、SNSなどで専門分野の有益な情報を継続的に発信します。見込み客との接点を作り、専門家としての認知度を高めます。
- セミナー・勉強会の開催 定期的にセミナーや勉強会を開催し、見込み客と直接会う機会を作ります。オンライン開催により、全国から参加者を集めることも可能です。
- 紹介システムの構築 既存クライアントや関連業者からの紹介を増やすための仕組みを作ります。紹介インセンティブの設定や、定期的なフォローアップが重要です。
- 業界団体への参加 ターゲット業界の団体や協会に積極的に参加し、人脈を構築します。講演機会や委員会活動を通じて、業界内での知名度を高めます。
単価を上げる価値提供の仕方
高単価での受注を実現するためには、以下の価値提供が必要です:
- 成果保証の提示 「売上○%アップ」「コスト○%削減」など、具体的な成果を約束します。成果が出なかった場合の返金保証なども検討します。
- トータルソリューションの提供 単発のコンサルティングではなく、課題解決から実行支援まで一貫したサービスを提供します。長期契約により安定収入を確保します。
- 独自ツールの開発 自分だけのフレームワークや分析ツールを開発し、他社との差別化を図ります。ツールのライセンス販売も収入源になります。
診断士になる前に知っておくべき「維持費」の現実
年会費・研修費で年間20万円超え
中小企業診断士の資格を維持するためには、想像以上の費用がかかります。中小企業診断協会への年会費だけで年間約3万円、各都道府県支部への会費が約2万円必要です。
さらに、5年ごとの更新に必要な研修費用が非常に高額です。更新研修は約15万円、実務補習や実務従事を選択する場合も同程度の費用が発生します。これらを年割りすると年間3万円程度の負担になります。
加えて、継続的な学習のためのセミナー参加費、書籍代、資格講座受講費なども必要です。真剣に診断士として活動するなら、年間20-30万円の自己投資は避けられません。
営業・集客にかかるコスト
独立した診断士にとって、営業・集客費用も大きな負担になります:
ウェブサイト制作・運営費: 年間20-50万円 セミナー開催費用: 会場費、資料作成費など月10-20万円 広告・宣伝費: ネット広告、業界紙広告など月5-10万円 営業ツール: 名刺、パンフレット、プレゼン資料作成費など年間10-20万円
これらのコストを回収できるだけの売上を上げられなければ、すぐに資金難に陥ってしまいます。
【結論】中小企業診断士で成功するための3つの条件
条件①:明確な戦略を持つ
中小企業診断士として成功するための最重要条件は、明確で具体的な戦略を持つことです。「なんとなく独立すれば稼げるだろう」という甘い考えでは確実に失敗します。
戦略に含めるべき要素は以下の通りです:
- ターゲット企業の明確化(業界、規模、地域など)
- 専門分野の設定(自分だけの強みを活かせる分野)
- 差別化ポイント(競合他社にない独自価値)
- 価格戦略(適正な単価設定と根拠)
- 営業・集客戦略(具体的な行動計画)
- 収支計画(3年間の売上・費用予測)
条件②:継続的な努力を惜しまない
診断士として成功するためには、資格取得後の継続的な努力が不可欠です。資格を取って満足してしまう人は確実に淘汰されてしまいます。
必要な努力の内容:
- 専門知識のアップデート:年間100万円以上の自己投資を継続
- 営業活動:週の30%以上を新規開拓に投入
- 実績作り:無償でも良いので成果の出る案件を積極的に受注
- 人脈構築:業界イベントや勉強会への積極的な参加
- 情報発信:ブログ、SNS、セミナーでの継続的な専門性アピール
成功している診断士は、これらの活動を3-5年間継続して初めて安定した収入を確保しています。短期間で結果を求める人には向かない職業です。
条件③:現実を受け入れる勇気を持つ
最後の条件は、診断士を取り巻く厳しい現実を正しく理解し、受け入れる勇気を持つことです。予備校や協会が宣伝する「バラ色の未来」は、ほんの一握りの成功者の話に過ぎません。
現実を受け入れるべき点:
- 90%の診断士が年収500万円以下という事実
- 独立後3年以内に70%が廃業するという統計
- 営業・集客が仕事の大部分を占めるという実態
- 年間数百万円の自己投資が必要だという現実
- 成果が出るまで3-5年かかるという時間軸
これらの現実を受け入れた上で、それでも挑戦する覚悟がある人だけが成功できます。「楽に稼げる」「資格があれば安泰」という幻想を抱いている人は、早めに軌道修正することをお勧めします。
まとめ:中小企業診断士で成功するなら覚悟を決めよ
中小企業診断士で「食える」ようになるためには、厳しい現実と向き合う必要があります。資格取得はゴールではなく、むしろ本当の挑戦の始まりです。
成功する診断士の条件:
- 明確な専門分野と差別化戦略
- 継続的な自己投資と努力
- 現実を受け入れる強いメンタル
失敗する診断士の特徴:
- 資格取得で満足してしまう
- 営業・集客を軽視する
- 同業者との馴れ合いに安住する
もしあなたが本気で診断士として成功したいなら、この記事で紹介した現実をしっかりと受け止め、長期的な視点で戦略を立ててください。