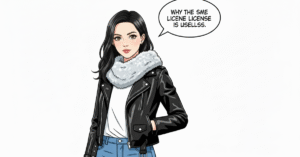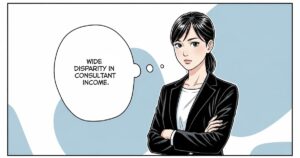中小企業診断士の維持費、年間最低10万円の内訳【企業内診断士が最も苦労する理由】

- 「中小企業診断士の資格を取ったら、毎年お金がかかるって本当?」
- 「予備校では維持費の話なんて詳しく教えてくれなかった…」
- 「サラリーマンだけど、診断士の資格を維持するのって大変なの?」
このような疑問を持っているあなたに、中小企業診断士の維持費について詳しく解説します。
実は、中小企業診断士の資格を維持するためには年間最低でも10万円がかかります。しかも、この金額は働き方によって大きく変わるのが現実です。特にサラリーマンとして働いている診断士にとっては、お金だけでなく時間的な負担も重くのしかかります。
【結論】中小企業診断士の維持費は年間最低10万円かかる
この記事では、中小企業診断士の維持費の詳細な内訳と、なぜサラリーマン診断士が最も苦労するのかを徹底解説します。

まず結論からお伝えします。中小企業診断士の資格を維持するためには、年間最低でも10万円の費用が必要です。
具体的な内訳は以下の通りです:
- 診断協会会費:5万円
- 理論更新研修:5,000円+半日の時間
- 実務従事がない場合:5万円(1日1万円×5日)
この金額は、中小企業のクライアントを持たないサラリーマン診断士の場合です。独立して中小企業の顧客を多数抱えている診断士であれば、実務従事ポイントは顧客への支援実績で満たせるため、実質的な維持費は5万5,000円程度に抑えられます。
つまり、同じ中小企業診断士の資格でも、働き方によって維持費が約2倍違うというのが現実なのです。
診断協会会費5万円は「任意だが皆入会してる」という微妙な立ち位置
中小企業診断協会への入会は、法的には任意です。診断士の資格を維持するために必須というわけではありません。
しかし現実問題として、ほとんどの診断士が協会に入会しています。なぜなら、協会に所属していないと以下のようなデメリットがあるからです:
- 診断士としての信頼性に疑問を持たれる可能性がある
- 診断士同士のネットワークから外れてしまう
- 各種研修や情報提供を受けられない
そのため、年会費5万円は事実上「払わざるを得ない費用」となっています。



特に後述の「実務従事ポイント」を自力で取得できない人は、協会からポイントを購入するしかないので、事実上、入会するこが必須となります。支部によっては、協会に入会しなくても実務従事ポイントの購入はできますが、割りかし研修はすぐに枠が埋まってしまうため、情報を取得する意味でも入会している人は多いです。
5万円払っても案件紹介はない現実
ここで重要なのは、年会費5万円を支払っても、協会から案件を紹介してもらえるわけではないという点です。
多くの人が勘違いしているのですが、診断協会は案件紹介業務を行っていません。会費を払ったからといって、「診断士として仕事をもらえる」ということはないのです。
それでは5万円で何が得られるのでしょうか?
- 各種研修への参加権利
- 診断士同士の交流機会
- 診断士としての身分証明 / 診断士バッジの貸与
正直なところ、年会費5万円に見合うメリットを感じている診断士は少ないというのが実情です。多くの診断士は惰性、もしくは、実務従事ポイントの購入のために入会している感じかと思います。
理論更新研修は選択肢が増えたものの、時間とお金は確実にかかる



診断士の資格を維持するためには、5年で5回の「理論更新研修」を受講する必要があります。
以前は選択肢が限られていた
以前は中小企業診断協会が主催する研修しか選択肢がありませんでした。この研修の問題点は:
- 内容が表面的で実務に活かしにくい
- 受講者のレベルがばらばらで効率が悪い
- 時間の割に得られるものが少ない
といった点でした。
現在は民間研修も選択可能
現在では民間企業が主催する研修も認定されるようになり、選択肢が広がりました。民間研修の中には:
- より実践的な内容を学べるもの
- 専門分野に特化したもの
- オンラインで受講できるもの
なども登場しており、質の向上が期待できます。
それでも最低5,000円+半日は必要
選択肢が増えたとはいえ、研修受講には最低でも以下の負担が発生します:
- 研修費:5,000円〜(研修により異なる)
- 時間:半日程度



民間の研修で、オンライン、1年で半日くらいならまぁいいかなとは個人的には思ってます。もちろん、それも面倒くさいと感じている診断士も多くいますが。
【サラリーマン診断士の最大の難関】実務従事で5万円の追加負担
サラリーマン診断士が最も頭を悩ませるのが、この「実務従事」の要件です。
実務従事ポイントとは
診断士は5年間で30ポイントの実務従事ポイントを取得する必要があります。このポイントは以下の方法で取得できます:
- 中小企業への診断・助言活動(実績による取得。1日1ポイントで換算。)
- 中小企業診断士協会が実施する、実務従事研修の受講(1日1万円×5日=5万円)
独立診断士は実績でポイント取得が可能
独立して中小企業をクライアントに持つ診断士であれば、日常の診断・助言活動でポイントを取得できます。そのため、追加の費用負担はほとんどありません。
サラリーマン診断士は研修受講が現実的
一方、サラリーマンとして働いている診断士の場合:
- 中小企業のクライアントを持つ機会が限られている
- 副業禁止の会社では診断業務ができない
- 時間的制約で営業活動が困難
といった理由で、実績によるポイント取得が困難です。
そのため、1日1万円×5日間=5万円の実務従事研修を受講するしか選択肢がないのが現実です。
実務従事研修の実態
実務従事研修について、実際に受講した診断士から聞く声があります。
「実務従事は有給とお金を使って受講しているにも関わらず、ハズレの講師の診断士も多く、そういう人に当たると、夜半まで細かい修正などが入り、役にも立たないのに徹夜に近い作業をさせられることもある」
5万円と貴重な有給休暇5日間を使って、このような状況に遭遇する可能性があるのは、サラリーマン診断士にとって大きなリスクです。
独立診断士 vs サラリーマン診断士:維持費負担の現実
ここで、働き方による維持費負担の違いを整理してみましょう。
独立診断士の場合
- 診断協会会費:5万円
- 理論更新研修:5,000円(1年に1回)
- 実務従事:0円(顧客への支援実績で取得)
年間維持費:約5万5,000円
サラリーマン診断士の場合
- 診断協会会費:5万円
- 理論更新研修:5,000円(1年に1回。5年で5回。)
- 実務従事研修:5万円(1年に5日。5年で30日。)
年間維持費:約10万円
同じ資格でありながら、働き方によって維持費が約2倍違うというのが現実です。
時間的負担の差も大きい
金銭的な負担だけでなく、時間的な負担も大きく異なります。
独立診断士の場合:
- 理論更新研修の半日のみ
企業内診断士の場合:
- 理論更新研修:半日
- 実務従事研修:5日間(有給休暇を使用)



企業内診断士は、多くの有給休暇を診断士の資格維持のために使わなければならないのです。
年間10万円の維持費を「投資」と考えられるのはどんな人?
年間10万円という維持費を「必要な投資」と考えられるのは、どのような診断士でしょうか?
維持費に見合うリターンを得られる診断士の特徴
- 独立して診断業務で安定収入を得ている
- 将来的に独立する明確な計画がある
- 数年以内に独立予定で、現在は準備期間
- 維持費を「将来への投資」として位置づけられる
- 会社内でのポジション向上に活用できる
サラリーマンが診断士を維持する意味はあるのか
正直なところ、以下のような状況のサラリーマンにとって、診断士の資格維持は費用対効果が悪いと言わざるを得ません:
- 独立予定がない
- 会社で診断士資格が評価されない
- 副業禁止で診断業務ができない
- 年収に対して10万円の負担が重い
このような状況の方は、資格維持をやめることも合理的な判断です。
予備校が教えない「診断士維持の分岐点」
多くの予備校は、資格取得後の維持費について詳しく説明しません。特に、働き方による負担の違いについては、ほとんど触れられることがありません。
資格取得前に考えるべきこと
診断士を目指す段階で、以下のことを明確にしておくべきです:
- 独立する予定はあるのか?
- 現在の会社で診断士資格は評価されるのか?
- 年間10万円の維持費を継続的に支払えるのか?
- 企業内診断士の場合、有給休暇を5.5日間、資格維持に使えるのか?
資格維持をやめる選択肢も視野に入れるべき理由



中小企業診断士の資格は、猶予措置があり、合計15年間は届出を出せば中断が可能です。その間も、中小企業診断士を名乗ることができます。
そのため、以下のような状況になった場合は、資格維持をやめることも合理的な判断です:
/
- 維持費の負担が重くなった
- 資格を活用する機会がない
- 将来的にも独立予定がない
資格にこだわりすぎて、毎年10万円を「どぶに捨てる」ような状況は避けるべきです。
まとめ:維持費10万円の重みは「働き方」で大きく変わる
中小企業診断士の維持費について、重要なポイントをまとめます:
維持費の現実
- 年間最低10万円の維持費が必要(企業内診断士の場合)
- 独立診断士は約5万5,000円で維持可能
- 金銭的負担だけでなく、時間的負担も大きい
働き方による格差
- 独立診断士には軽い負担
- サラリーマン診断士には重い負担。特に、お金の面だけでなく、有給を使う必要があるのが大きな負担。
- 同じ資格でも維持の難易度が大きく異なる
重要な判断基準
資格維持を続けるかどうかは、以下の基準で判断すべきです:
- 費用対効果が見込めるか
- 将来的な活用予定があるか
- 継続的な負担に耐えられるか
最後に
中小企業診断士の資格取得を目指している方、すでに取得して維持に悩んでいる方は、この現実をしっかりと理解した上で判断することが重要です。