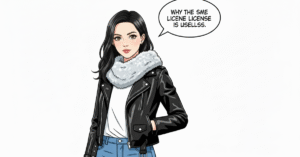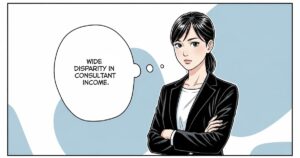「中小企業診断士は意味ない」論争に終止符。資格の価値を費用対効果で分析してみた


中小企業診断士の与田です。インターネット上で、中小企業診断士という資格ほど評価が真っ二つに分かれるものも珍しいでしょう。
一方では、「人生が変わる、最強の経営コンサルタント資格」「独立して年収1000万円も可能」といった、輝かしい成功譚が語られます。その一方で、「絶対にやめとけ」「食えない、意味ない資格の典型」といった、辛辣な批判も後を絶ちません。
一体、どちらが真実なのでしょうか。この長きにわたる論争は、感情的な意見や、一部の成功者・失敗者の体験談ばかりが先行し、本質的な議論がなされていないように感じます。
そこでこの記事では、一度そうした感情論から離れ、中小企業診断士という資格が持つ価値を「費用対効果(コストパフォーマンス)」という、極めて冷静な視点から徹底的に分析し、この論争に終止符を打ちたいと思います。
ここで言う「費用」とは、単なる受験料や登録料だけではありません。あなたの貴重な「時間」、他の可能性を犠牲にする「機会費用」、そしてキャリアにおける「リスク」もすべて含みます。同様に「効果」とは、収入という直接的なリターンだけでなく、人脈や信頼といった無形の資産も含みます。
【費用:COST】診断士になるため、そして維持するために支払う莫大な対価
まず、この資格を取得し、維持するために、あなたが支払わなければならない「費用」について、一つずつ見ていきましょう。その想像以上の重さに、驚くかもしれません。
費用①:資格取得までにかかる金銭的・時間的コスト
最初の費用は、資格取得そのものにかかるコストです。これには、予備校に通うのであれば数十万円の受講料、数多くのテキスト代、そして何より、合格までに必要とされる1000時間とも言われる、膨大な勉強時間が含まれます。



さらに、最近では二次試験免除の養成課程なんかもありますね。もし養成課程に通うとすると、費用は200万円から300万円くらいかかるらしいです。
あと、これはあまり言いたくないですが、養成課程出身者の方が診断士・コンサルのスキルが低い傾向にあるのは否定できません(もちろん養成課程出身の優秀な方もいますが)。養成課程出身の方は正直、思考力や記述力が弱い方が多く感じます。二次試験も「効果的に」勉強すればそこまで難しい試験ではなく、200万円~300万円のお金と、時間も使って養成課程に通うのは、スキルアップにも効果が薄いので、あまり割に合わないのではと個人的には感じてます。



後々診断士になったあとを考えると、二次試験にチャレンジして、論理的思考力と記述力をトレーニングした方がいいのではと思います。ちなみに、僕の場合は2008年診断し登録と、昔の登録なのであまり参考にならないかと思いますが、一次試験も二次試験も独学だったので、費やしたのは勉強時間200~300時間くらい、あとは市販の問題集代、1回の模擬試験代くらいでした。
40代、50代の方であれば、働きながらこの時間を捻出するのは、家族との時間や自身の健康を犠牲にしかねない、極めて大きな投資です。しかし、本当のコストは、合格した後に始まります。
費用②:資格維持に必須の「実務ポイント」という名の重税



中小企業診断士の資格は、5年ごとの更新制です。そして、この更新のために、多くの診断士が苦しめられているのが「実務ポイント」という制度です。5年間で30日分のコンサルティング実績を積まなければ、資格は失効してしまいます。
このポイントを、通常の業務で得られない企業内診断士などは、診断協会が提供する「実務補習」に参加することになります。この実態が、費用対効果を著しく悪化させる最大の要因です。
この補習は、信じられないことに、
- 自腹で5万円から6万円の費用を支払う(総額5年で30万円)
- 自身の有給休暇を使い、平日に参加する
- その上で、中小企業へ赴き、無報酬でコンサルティングを行う
という、「お金を払って、休みを潰して、タダ働きをする」という、常識では考えられないシステムなのです。あなたが汗水流して働いた対価は、報酬ではなく、わずか数日分の「ポイント」だけ。こんな理不尽なことが、国家資格の維持制度としてまかり通っているのです。
さらに、この補習には「講師ガチャ」が存在し、ハズレの講師に当たれば、本質的でない指導で精神をすり減らされるという追加コストまで発生します。これは、もはや投資ではなく、資格保有者から半強制的に徴収される「重税」と言っても過言ではありません。



中小企業診断士の維持費については、下記にまとめているので、ご参照ください。


費用③:キャリアにおける機会費用とリスク



費用対効果を考える上で、目に見える金額以上に重要なのが、「機会費用」と「リスク」です。
・転職市場での無力さ



断言しますが、「診断士資格は転職に有利」というのは真っ赤な嘘です。
「資格を取れば、より良い条件で転職できるはず」という期待は、ほぼ100%裏切られます。独占業務がないため、企業側は診断士資格を必須スキルとは見なしません。資格取得に費やした時間で、より市場価値の高い実務経験や専門スキル(語学、プログラミングなど)を磨いた方が、キャリアアップにはよほど効果的だったかもしれないのです。もちろん、信用金庫など、一部の業界では診断士の取得が奨励され、優遇されますが、ほとんどの企業においては、せいぜい、大手企業などで雀の涙程度の資格手当がもらえる程度でしょう。
・「やりがい搾取」のリスク
仮に独立・副業の道を選んでも、そこには「下請け地獄」が待っています。業界の慣習として、元請けに報酬の約7割を中抜きされるのが当たり前。あなたの専門知識と労働力は、驚くほど安く買い叩かれます。また、診断協会での活動も、そのほとんどが無給奉仕であり、「いつか仕事に繋がる」という淡い期待を抱きながら、貴重な時間を浪費するリスクを伴います。
これらのコストを合計すると、診断士資格の取得と維持には、金銭的にも時間的にも、そして精神的にも、計り知れないほどの費用がかかることがわかります。
【効果:BENEFIT】莫大な費用を支払って得られる、限定的なリターン



では、これほどの莫大なコストを支払って得られる「効果(リターン)」とは、一体何なのでしょうか。予備校が謳うような「高収入」や「安定」は本当にあるのか、冷静に見ていきましょう。
(幻想だった)効果①:年収1000万円という神話
まず、多くの人が期待する「高収入」ですが、これは幻想です。診断協会の「年収1000万超が3割」というデータは、前述の通り、調査対象がアクティブな層に限定された、実態とはかけ離れたものです。実際には、多くの診断士が補助金頼り、あるいはアルバイトに毛が生える程度の公的業務という不安定な収入構造にあります。
公的業務にありつくには、診断協会のお偉いさん、選抜する人とのコネが必要ですし、補助金バブルも崩壊しました。資格があるだけで高収入が約束される、という効果は、残念ながら存在しません。
では、本当の効果とは何でしょうか。本書の内容から分析すると、それは以下の3つに集約されます。
下記記事で、中小企業診断士の年収については詳しく解説しています。


真の効果①:「認定支援機関」という看板が、楽に手に入る
私がこの資格を取って最も大きなメリットだと感じたのは、「認定支援機関」という国のお墨付きを、比較的簡単に手に入れられることです。この認定がないと申請できない補助金(例:早期経営改善計画)や、税制上の優遇措置をクライアントに提案できるようになります。これは、コンサルタントとして活動の幅を広げる上で、明確で強力なメリットです。



ただし、冷静に分析するならば、この認定支援機関は、研修を受ければ診断士の資格がなくても取得は可能です。莫大なコストをかけて診断士になることが、唯一の道ではないという事実は、知っておくべきでしょう。
真の効果②:金融機関からの絶大な信頼
もう一つの大きなメリットは、銀行などの金融機関からの受けが非常に良いことです。銀行は融資先の経営状態を評価する上で、経営から財務まで理解している診断士が作成した事業計画書を高く評価します。そのため、「診断士の先生が間に入っているなら」と、融資の稟議が通りやすくなるのです。これは、クライアントの資金調達を支援する上で、絶大な効果を発揮します。
ただし、ここにも注意点があります。報酬をもらって融資の「交渉」を行えば、弁護士法に抵触するリスクがあることは、常に頭に入れておく必要があります。
真の効果③:「仕事仲間」を見つけるためのプラットフォーム
これまで、診断協会は「仕事をくれない場所」「やりがい搾取の温床」として批判的に述べてきました。しかし、一つだけ、明確な活用法があります。それは、「仕事をもらう場所」ではなく、「自分のチームを作る仲間を見つける場所」として活用することです。
協会には、様々な分野で、企業内専門家として豊富な経験を積んできた人たちが大勢います。例えば、自分がマーケティングの専門家であれば、人事のプロやITのプロと繋がり、自分の専門外の案件にもチームで対応できるようになるのです。これは、一人では決して得られない、貴重な無形資産と言えるでしょう。



僕も、診断士仲間と一緒にビジネスをしてて、いろいろ助かってます。上場企業の現役社員なども多く、業務スキルが高い人も多いので、そういう人と一緒にプロジェクトを進めていけるのは、けっこう大きなメリットです。
補足の効果:仕事の説明がラク
これは個人的に感じている部分ですが、独立後に自分の仕事を説明するのがラクというのはあります。独立後でも、住宅の購入や賃貸、クレジットカードの制作など生活の諸々で自分の職業を申告する機会は多くあります。その際、職業欄に「中小企業診断士」と書けば、職業に対して細かな質問を受けることもないので、実はここが一番の大きなメリットだったと個人的には感じています。



独立するとクレジットカードの審査が通りにくい、という話は良く聞きますが、自分の場合は何枚もクレジットカードを作ってますが、全て審査は通ってます。もちろん、それ以前にクレジットカードに変な履歴が残ってないから、というのも大きいかと思いますが。
【結論】費用対効果は、絶望的に悪い。ただし「条件付き」で価値は生まれる
さて、ここまで「費用」と「効果」を冷静に分析してきました。結論を導き出しましょう。
【費用】
- 数百万単位の金銭的コスト(受験・維持)
- 数千時間の時間的コスト(勉強・無給奉仕)
- キャリアにおける機会費用とリスク
【効果】
- 認定支援機関の看板
- 金融機関からの信頼
- 専門家との人脈形成



この天秤がどちらに傾くかは、火を見るより明らかです。「資格取得」そのものに対する費用対効果は、絶望的に悪い。これが、この論争に対する、私の最終的な答えです。
もしあなたが、「資格さえ取れば、自動的に仕事や高収入が手に入る」と考えているのであれば、中小企業診断士は、あなたにとって間違いなく「意味ない」資格です。今すぐ、目指すのをやめるべきです。



1つフォローしておくと、診断士試験の内容自体は、経営学全般を網羅的に勉強できるという点では、とてもクオリティーが高く、良い内容です。個人的には「なんちゃってMBA」なんか取得するよりは、良くも悪くも「質実剛健」で役に立つとは思います。とはいえ、あくまで「基本理論を網羅できる」という点のみなので、実践的なスキルはまた別に獲得する必要がありますが。
では、なぜ、それでも診断士として成功している人がいるのでしょうか。それは、彼らが「資格の価値」に依存していないからです。彼らは、この資格を、数ある武器の一つとして「活用」しているに過ぎません。
中小企業診断士という資格は、それ単体では価値をほとんど生み出しません。しかし、
- 自ら仕事を生み出す「営業・マーケティング能力」
- AIを奴隷として使いこなし、生産性を極限まで高める「ITスキル」
- 業界の未来を語り、顧客を導く「ビジョン」
といった、試験では決して問われない「別のスキル」と掛け合わせたとき、初めてその真価を発揮するのです。
この「意味ない」論争に終止符を打つ本当の答えは、「資格に価値があるか、ないか」ではありません。「あなたが、資格以外の価値を持っているか、いないか」なのです。
もしあなたが、その「資格以外の価値」を身につけ、厳しい現実の中で戦い抜く覚悟があるのなら。そのための具体的な戦略と戦術のすべてを、拙著『中小企業診断士はやめとけってホント? 予備校や診断協会が教えてくれない年収のリアル』に、記しました。
費用対効果という冷静な分析の先で、それでも挑戦の道を選ぶあなたを、本書は全力でサポートします。