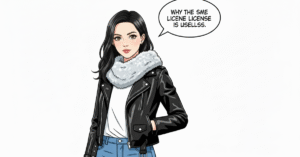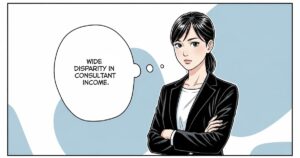【本当の価値】中小企業診断士は転職に有利は嘘。診断士資格を最強の武器に変える3つの活用法

はじめに:「転職に有利」という、あまりにも甘い幻想

こんにちは。中小企業診断士の与田太一です。
あなたがもし、中小企業診断士という難関資格の取得を考えているとしたら、その動機の一つに「キャリアアップ」や「より良い条件での転職」という期待があるのではないでしょうか。
「これだけ難しい資格なのだから、持っているだけで市場価値が上がり、引く手あまたになるはずだ」
そう考えるのは、ごく自然なことです。予備校や一部の合格体験記も、そうした「資格がもたらす輝かしい未来」を語りがちです。
しかし、私が本書『中小企業診断士やめとけ』を通じて、どうしても伝えたかった不都合な真実の一つ。それは、「中小企業診断士の資格は、転職にほとんど有利に働かない」という、あまりにも厳しい現実です。



私自身、独立するまでに2度の転職を経験していますが、診断士資格があったから有利になったと感じたことは一度もありませんでした。
面接で「診断士資格をお持ちなのですね、ではこんな仕事はどうですか?」といった話になったことなど、ただの一度もなかったですし、診断士資格を持っていることが面接の話題にすら登りませんでした。
この記事では、なぜ「転職に有利」が嘘だと言い切れるのか、その構造的な理由を明らかにします。そして、単に絶望を語るのではなく、その上で、この資格が持つ「本当の価値」を見出し、あなたのキャリアにとって「最強の武器」に変えるための、具体的で実践的な3つの活用法を、本書の内容を基に余すところなくお話ししたいと思います。
なぜ「診断士資格は転職に有利」が真っ赤な嘘なのか?
理由①:致命的な「独占業務」の不在



私が、転職においてこの資格の価値は「基本的にはゼロだと考えてくれていい」 とまで断言するのには、明確な理由があります。その最大の理由が、他の多くの士業と異なり、中小企業診断士には「独占業務」がないことです。これが、キャリア市場において致命的な弱点となります。
例えば、弁護士には訴訟代理、税理士には税務申告の代理といった、その資格がなければ法的に行うことのできない独占業務があります。企業が法務部員や経理部員を採用する際、これらの資格を持つ人材を求めるのは、その専門性と独占業務の価値を認めているからです。
しかし、中小企業診断士が行う経営コンサルティングは、極論すれば誰でも「経営コンサルタント」と名乗って行うことができます。資格がなくても罰せられることはありません。そのため、採用する企業側から見れば、「中小企業診断士でなければならない理由」が存在しないのです。これが、他の士業資格と比べて、転職市場でのアピールが格段に弱くなる根本的な原因です。
理由②:転職市場では「資格」より「実務経験」が圧倒的に重視される
もう一つの理由は、より本質的です。それは、現代の転職市場、特に専門性が問われるキャリア採用において、企業は「資格」そのものよりも、あなたがこれまで何をやってきたかという「具体的な実務経験」を圧倒的に重視するからです。
例えば、採用担当者の立場になって考えてみてください。
「中小企業診断士の資格を持っています」とアピールするAさんと、「前職で子会社の社長として、人事、経理、営業の全てをマネージメントし、3年で売上を倍にした経験があります」 7 と語るBさん。あなたが採用したいのは、どちらでしょうか。
答えは明白です。診断士の資格は、経営に関する幅広い知識を持っていることの「証明」にはなりますが、それを使って具体的な成果を出したという「実績」の証明にはなりません。転職市場という戦場では、ペーパー上の知識よりも、泥臭い現場で培われた経験と実績こそが、何よりも雄弁にあなたの価値を物語るのです。
例外:それでも「診断士」が輝くニッチな世界



もちろん、この原則にも例外はあります。
本書でも触れていますが、診断士資格が昇進や転職で明確に有利に働く、ニッチな世界も確かに存在するのです。
その代表格が、「信用金庫」や一部の「地方銀行」です。
「信用金庫も付加価値サービスを展開しないと生き残っていけないからね。診断士がいれば、補助金の申請から事業承継・M&Aなどの付加サービスを展開することができる」
これらの金融機関では、融資先の経営を支援することが自らの収益に直結するため、診断士の取得を奨励していたり、専門部署を設けていたりと、資格保持者が活躍できる土壌が用意されています。こうした特定のフィールドにおいては、診断士資格は間違いなくあなたのキャリアを後押ししてくれるでしょう。しかし、それが一般の事業会社ではレアケースであるという現実は、冷静に認識しておく必要があります。
診断士資格を「最強の武器」に変える3つの活用法
「転職に有利は嘘」。この厳しい現実を直視した上で、では、私たちはこの資格をどう活かせばいいのでしょうか。本書で私が提示するのは、資格を「キャリアのゴール」として捉えるのではなく、自らのビジネスを有利に進めるための「武器」として戦略的に活用する視点です。
ここからは、そのための具体的な3つの活用法をご紹介します。
活用法①:「認定支援機関」という看板が、楽に手に入る
私が、この資格を取得して最も大きなメリットだと感じたのは、国からのお墨付きである「認定支援機関」の資格が、非常に取得しやすくなるという点です。
「これは国からのお墨付きがもらえるようなもので、この認定支援機関じゃないとできない仕事、というのがあるんだ」



私も認定支援機関の承認をもらっています。承認IDは108213005710で調べると私の名前が出てくると思います。
認定支援機関とは、中小企業の経営支援を行う能力が一定レベル以上あると、国(経済産業省)が認定した専門家のことです。税理士や公認会計士も取得できますが、診断士も非常に有利です。
この「看板」がもたらすメリットは絶大です。
- 独占業務の獲得:「早期経営改善計画」という、コンサルティング費用を国が補助してくれる制度がありますが、これは認定支援機関でなければ扱うことができません。これにより、「国の補助金でお試しコンサルが受けられますよ」という強力な営業ツールが手に入ります。
- 補助金申請での優位性:他の補助金を申請する際も、認定支援機関が支援しているというだけで、申請書に「格」がつきます。もっと言うと、大抵の事務局は認定支援機関の支援を受けて補助金の申請を出すことを勧めています。
- 直接の問い合わせ:国の登録サイトに名前が載るため、「サイトを見て連絡しました」という直接の問い合わせが舞い込んでくることもあります。
これは、まさにビジネスの戦場に立つための「入場券」です。転職市場では役に立たなくても、独立してビジネスを行う上では、これ以上ない武器となるのです。
活用法②:なぜか「銀行員」にモテる?金融機関からの絶大な信頼



二つ目の武器は、一見すると意外に思えるかもしれません。それは「金融機関からの受けが非常に良い」ということです。
「金融機関は、診断士が関わる話をものすごく喜ぶ。もう、ウェルカム状態だよ」
なぜ、銀行は診断士をこれほどまでに歓迎するのでしょうか。その理由は、銀行側のビジネスモデルにあります。銀行は、融資を実行して初めて利益が生まれます。 その際、最も大きなハードルとなるのが、融資の妥当性を判断する「稟議」です。
経営から財務までを理解している診断士が、企業の事業計画作成に関与してくれると、その計画の信頼性が増し、銀行としては稟議を通しやすくなるのです。だからこそ、私たちが「クライアントの融資の件で…」と銀行に電話をすれば、「ぜひぜひ!」と大歓迎してくれるのです。



ただし、ここで絶対に守らなければならない鉄則があります。
「一つだけ、絶対に守らなければならないことがある。それは、金融機関に対する『交渉』はしちゃいけない、ということだ。もし報酬をもらって交渉をしてしまうと、弁護士法違反になる可能性がある」
私たちの役割は、あくまで銀行と連携し、融資がスムーズに進むようにサポートすること。この強力な信頼関係を武器に、クライアントの資金調達を支援できることは、診断士ならではの大きな価値です。
活用法③:協会は「仕事をもらう場所」ではなく「仲間を見つける場所」だ
本書では、診断協会が抱える問題点について厳しく指摘しています。しかし、その協会も、使い方を180度変えれば、強力な武器となり得ます。その逆転の発想とは、「仕事をもらいに行く」のではなく、「自分のチームを作る仲間を見つけに行く」という視点です。



僕も、診断士のマスターコースに関わっていますが、半分は新たな知見や経験を持った仲間を見つけに行ってるような感じです。
「これまで散々、診断協会の悪口を言ってきたけど(笑)、唯一、使いようがあるとしたらここだね。
協会や研究会に参加すると、企業の中でバリバリ実績を上げてきた、経験豊富な人たちと出会えるんだ」
診断協会で直接クライアントを見つけるのは至難の業です。しかし、そこには、人事、法務、IT、製造など、様々な分野で深い専門知識と実務経験を積んできたプロフェッショナルたちが大勢います。
例えば、あなたがマーケティングを専門とする診断士だとしましょう。あるクライアントから人事制度に関する相談を受けた時、一人で抱え込む必要はありません。「人事のプロなら、協会で知り合ったあの人がいる」と、信頼できる専門家を紹介し、チームを組んで対応することができるのです。
このように、協会を「自分の専門外の分野をカバーしてくれる、信頼できるパートナーを見つける場所」として活用する。そう考えれば、年会費も決して高い投資ではないはずです。
「武器」の本当の価値は、使い方次第で決まる
「転職に有利」という幻想を捨てること。それは、資格の価値を否定することではありません。資格という一枚の「許可証」に自分のキャリアを委ねるのではなく、それを自らの手で研ぎ澄まし、戦略的に活用する「武器」として捉え直すことなのです。
- 「認定支援機関」という公的な看板で、信用の土台を築く。
- 「金融機関」との連携で、クライアントの資金調達という根源的な課題を解決する。
- 「診断協会」というプラットフォームで、自らの弱点を補う最強のチームを編成する。
これら3つの活用法は、診断士資格が持つ、眠れる価値を呼び覚ますための鍵です。
本書『中小企業診断士やめとけ』では、これらの活用法をさらに深掘りすると同時に、では、そうして手に入れた武器を使って「具体的にどうやって仕事を見つけ、稼いでいくのか」という、最も重要な戦術について、私の経験のすべてを注ぎ込んで解説しています。
資格の本当の価値は、あなたがそれをどう使いこなすかにかかっています。ぜひ本書を手に取り、あなたの診断士資格を、宝の持ち腐れではなく、未来を切り拓くための最強の武器に変えてください。